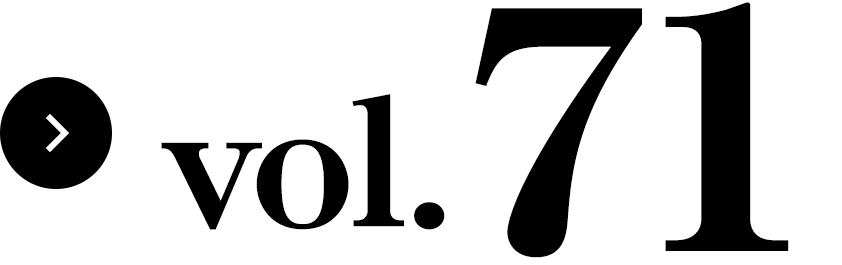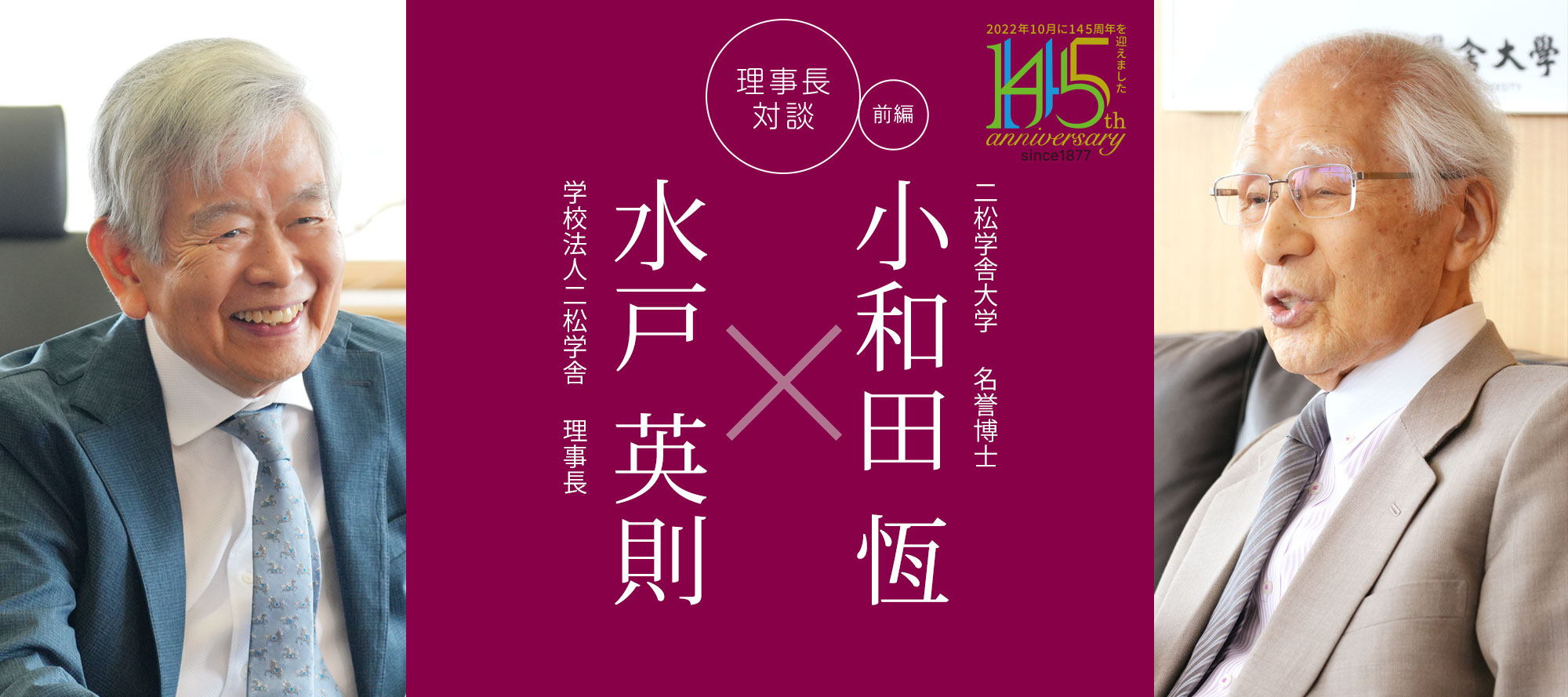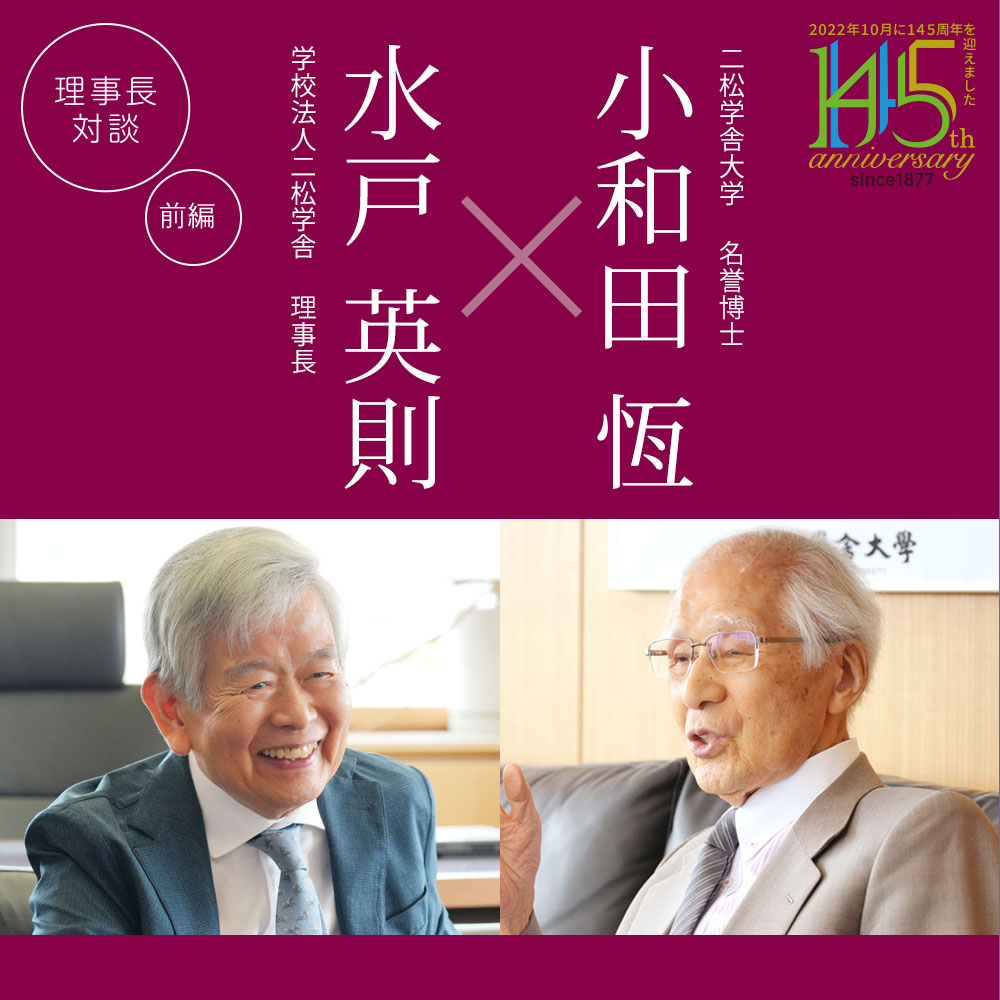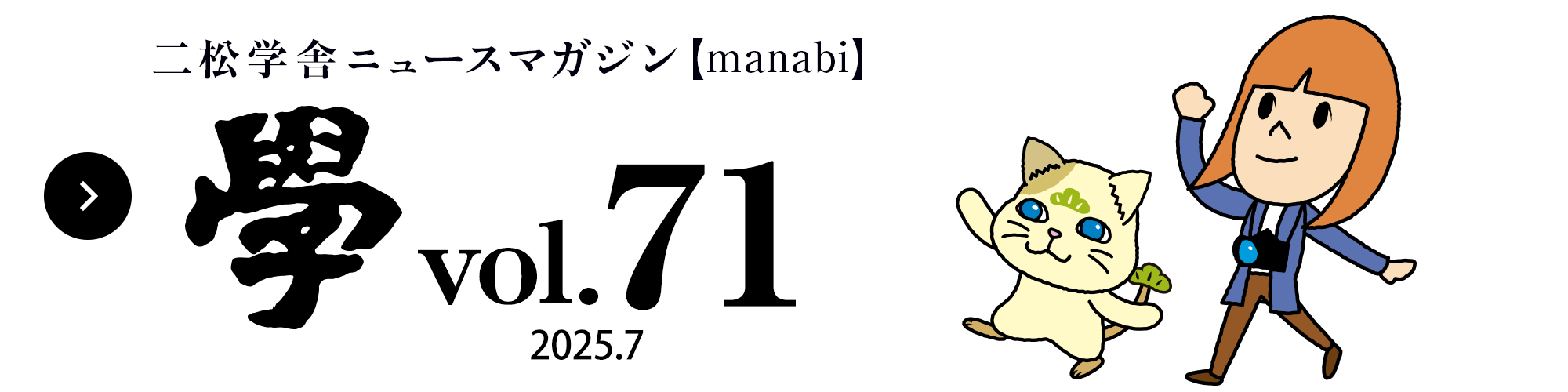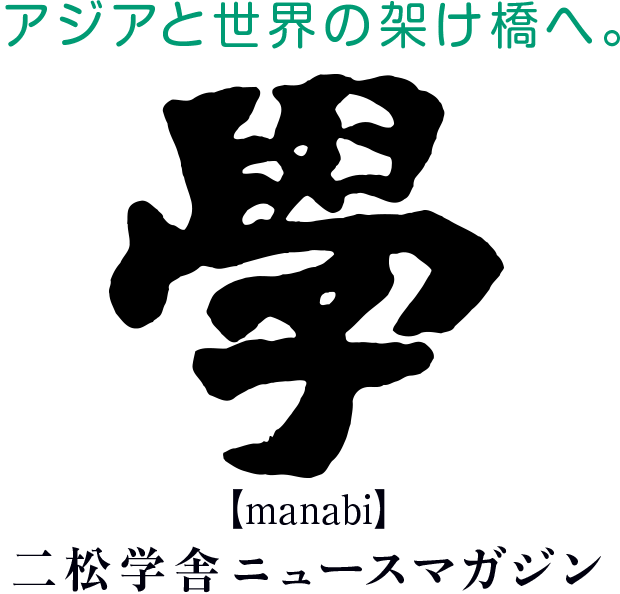国際秩序の礎「ウエストファリア体制」は主権平等を掲げていながら、現実には戦争が繰り返されています。なぜ、そのような矛盾が生じるのでしょうか――。本学名誉博士で国際法の権威・小和田恆先生と、水戸英則理事長が、4世紀にわたる国際社会の変遷をたどりつつ、戦争が繰り返される「構造的な矛盾」の本質に迫ります。今回は、対談全2回の前編をお届けします。
水戸 世界各地で続く戦争。その現実を前に「ひとはなぜ戦争をするのか」という根源的な問いを、誰もが一度は考えるのではないでしょうか。本日は小和田先生と、このテーマについて語り合いたいと思います。
小和田 物理学者アインシュタインと精神分析学者フロイドの往復書簡『ひとはなぜ戦争をするのか』(講談社学術文庫)では、人間が戦争をする理由は生存本能に由来すると述べています。人間同士の争い(紛争)ということで言えば、夫婦喧嘩から組織内、学校内における対立まで、人間が存在する限り必ず争いは発生し、それは人間という動物にとって避けることができない本能的なものと言えるかもしれません。しかし、そうした争いは個人間の「紛争」であって、国家間の「紛争」としての「戦争」とは必ずしも同じ要因に支配されるものではないことに注意する必要があります。ナポレオン時代、その軍事戦略家として名を馳せたカール・フォン・クラウゼヴィッツは「戦争は形を変えた外交の延長である」という有名な言葉を残しました。国家は、外交で紛争が解決しない時にはその究極的な解決のために戦争という手段を正当化します。戦争も個人の紛争と同様に避けられないのかと問われれば、私はそうではないと考えています。
水戸 それはどういう意味ですか?
小和田 まず国内社会と国際社会とでは統治組織の仕組みに違いがあることを理解することが大切です。個人が統治の対象である国内社会は、社会秩序に違反すれば警察に拘束され、裁判にかけられるという「他律的」秩序を持つ社会です。イギリスの政治哲学者トマス・ホッブズは、国内社会の他律性を「リヴァイアサン」という概念で説明しました。リヴァイアサンとは旧約聖書に登場する怪物で、ホッブズは国家主権をこの巨大な存在になぞらえたのです。人々は本来持っている自由を主権者に委ね、その権威のもとで自らの権利を保障する秩序を維持するという「他律的」秩序による統治組織だと言えます(社会契約説)。
他方、国際社会という社会には警察権や司法権といった他律的秩序は存在しません。唯一の根本原則が「約束は守られなければならない」(パクタ・スント・セルヴァンダ)※という自己規制によって社会秩序が維持されるという「自律的」秩序です。実際に約束を守るかどうかは主権国家に委ねられていますから、国際的な合意を破り、戦争を起こすことも可能になっています。
※pacta sunt servanda…ラテン語を起源とする成句。国際法の基本ルールを定めたウィーン条約法条約第26条に規定されている。
水戸 現代の国際社会には、リヴァイアサンがいないわけですね。
小和田 その通りです。ルネサンス以前のキリスト教ヨーロッパが宗教的にはローマ法王、世俗的には神聖ローマ帝国の支配下に置かれていた時代は、世界はある意味で他律的な社会でした。皇帝(ハインリヒ4世)がローマ法王のもとに行ってひざまずき、その許しを請うた「カノッサの屈辱」という有名な出来事はこの状況を象徴する事件です。それくらい法王の権威は絶対的でした。ところが、15世紀のルネッサンスとそれと連動する宗教革命の結果、この統治システムに大変動が起きることになりました。1618年から1948年まで続くヨーロッパ全体を巻き込む大戦争―カトリック派とプロテスタント派の対立による宗教戦争が起こりました。文字通り30年間続いたことから「三十年戦争」と呼ばれています。1648年「ウエストファリアの講和」によって、(ヨーロッパ)世界という国際社会の新しい統治システムが生まれたのです。それが、今日まで四世紀にわたって続く国際社会の秩序を構成する「ウエストファリア体制」の基盤となりました。
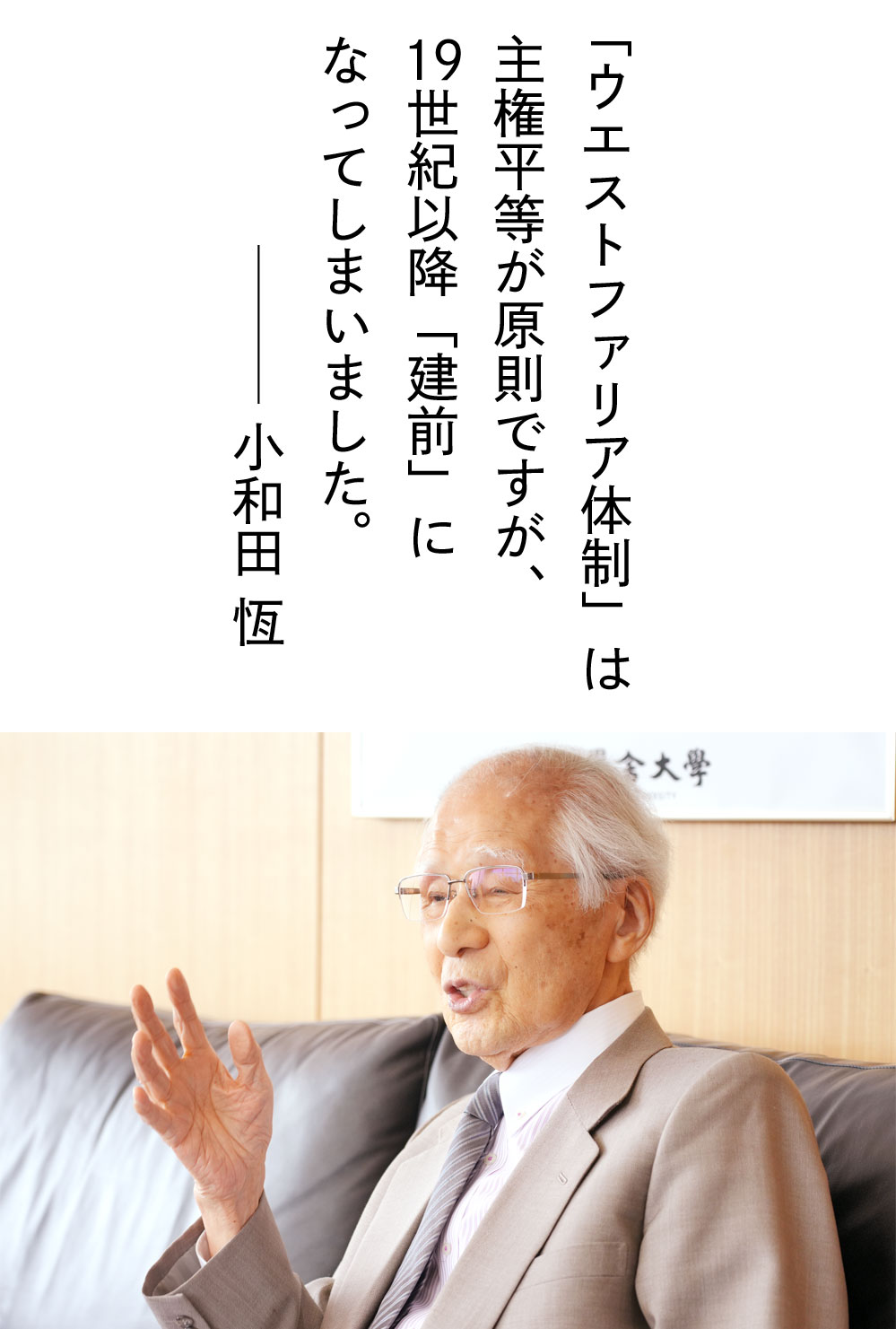
おわだ・ひさし 東京大学教養学部卒業。ケンブリッジ大学法学部大学院修了。現在、公益財団法人日本国際問題研究所顧問、二松学舎大学名誉博士。外務省外務事務次官、国際司法裁判所裁判官、同所所長などを歴任。学術分野では、東京大学で30年以上教鞭を執り、早稲田大学大学院教授を務める。ハーバード大学、ニューヨーク大学、コロンビア大学等で招聘教授を歴任。ライデン大学名誉教授。主な著作に、『国際関係と法の支配(小和田恆国際司法裁判所裁判官退任記念論文集)』(共著、信山社、2021年)など。
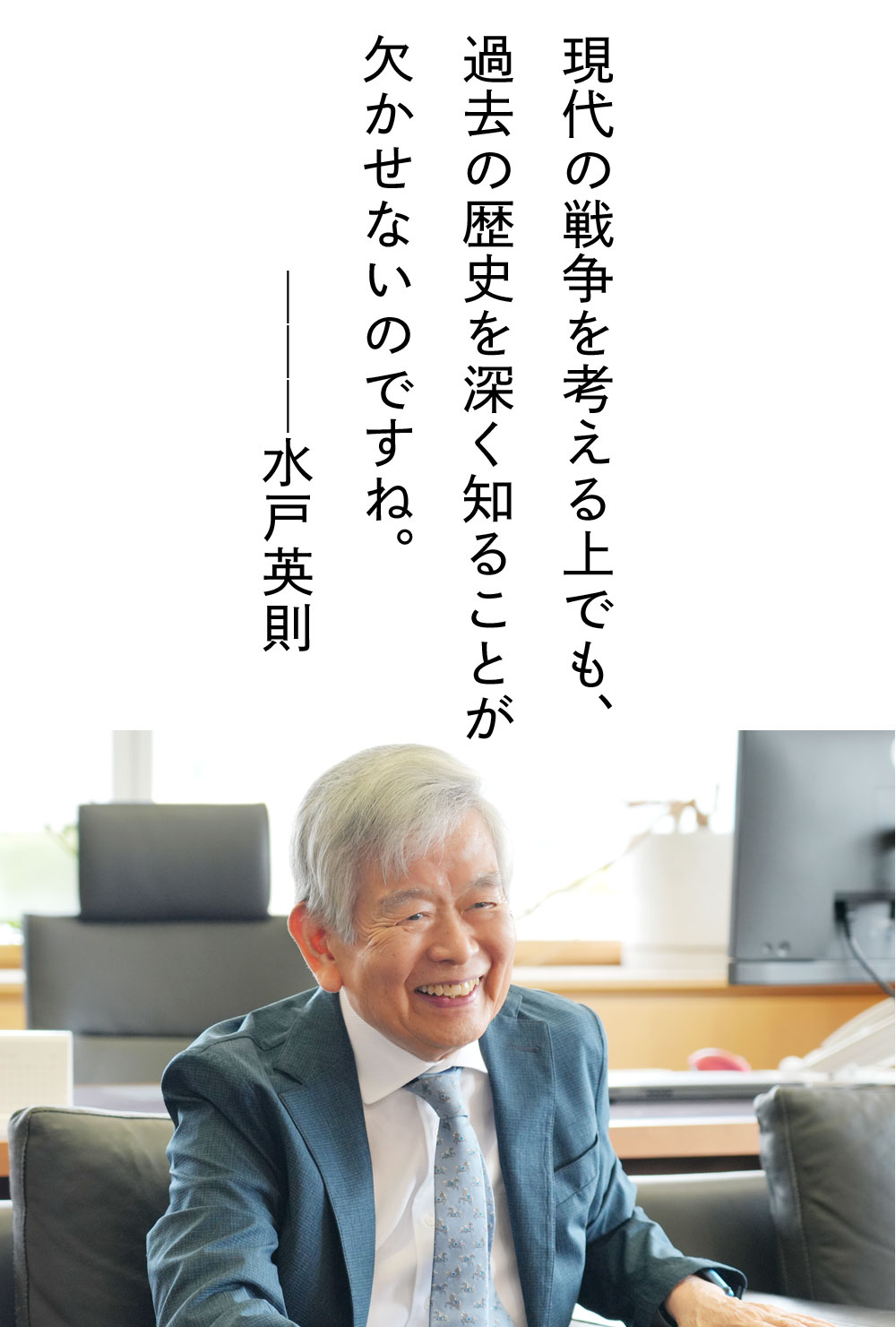
みと・ひでのり●1969年九州大学経済学部卒業。日本銀行入行、フランス政府留学、青森支店長、参事考査役などを歴任。2004年、二松学舎に入り、11年理事長に就任。文部科学省学校法人運営調査委員、日本私立大学協会常務理事、日本高等教育評価機構理事などを務める。
水戸 ウエストファリア体制とは主権平等が原則で、それぞれの国が自国の統治権を持ち、他国の干渉を受けないという自律的な考え方ですね。そこから国際社会のあり方はどう変わったのでしょう。
小和田 17世紀のウエストファリア体制は、もともとはヨーロッパ内の秩序として生まれたものでした。その後、18世紀からヨーロッパで産業革命が進み、帝国主義時代の植民地統治体制を作ったことで、ウエストファリア体制が世界全体を支配する国際秩序の中核となる今日の状況に至りました。神聖ローマ帝国の版図内における国々の関係と、拡大した世界の大国対アジア・アフリカ・中南米の小国との関係とでは、国力の差が非常に大きいわけです。主権平等の原則は徐々に崩れ、法的枠組みとしての建前と社会政治的実体としての現実との乖離が生まれるようになってしまいました。ウエストファリア体制の自律的秩序に依拠する限り、戦争は起きてしまいます。
水戸 その崩れた主権平等を回復する動きもあったのでしょうか?
小和田 19世紀にはクリミア戦争、露土戦争、普仏戦争、イタリア独立戦争など多くの大戦争が絶え間なく続き、そのため、「国家の論理」とは無縁な多数の人々がその犠牲者となる状況が生じたのです。その中で生まれたのが、戦争で無辜の市民が命を落とすことを深刻な問題としてとらえ、「人間の倫理」を重視する歴史の流れだったと言えます。アンリ・デュナンやナイチンゲイルの赤十字運動をはじめ、主権国家間でも1898年のハーグ平和会議では、「戦争を完全に廃止することは困難だとしても戦争についてのルールを定めるべきだ」という国際世論が高まり、戦時国際法(現在の国際人道法)が整備されます。戦闘員と非戦闘員の区別、傷病者の保護、戦闘手段の制限などの規則が合意されました。また、紛争が戦争に至らないよう、「国際紛争ノ平和的処理ニ閑スル条約」が出来たのもこの時でした。
水戸 現代の戦争を考える上でも、長い歴史の中で構築されてきた仕組みを知ることが大切なのですね。次号でも詳しくお聞かせください。
(後編につづきます)