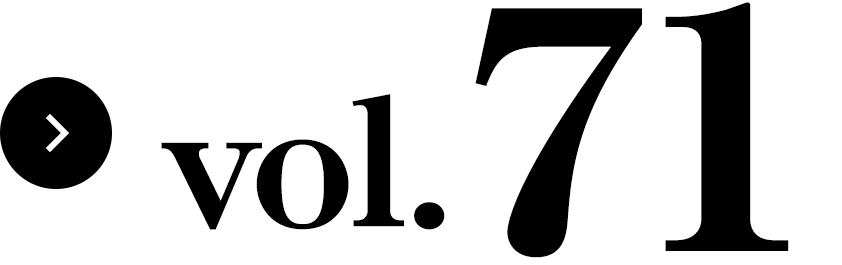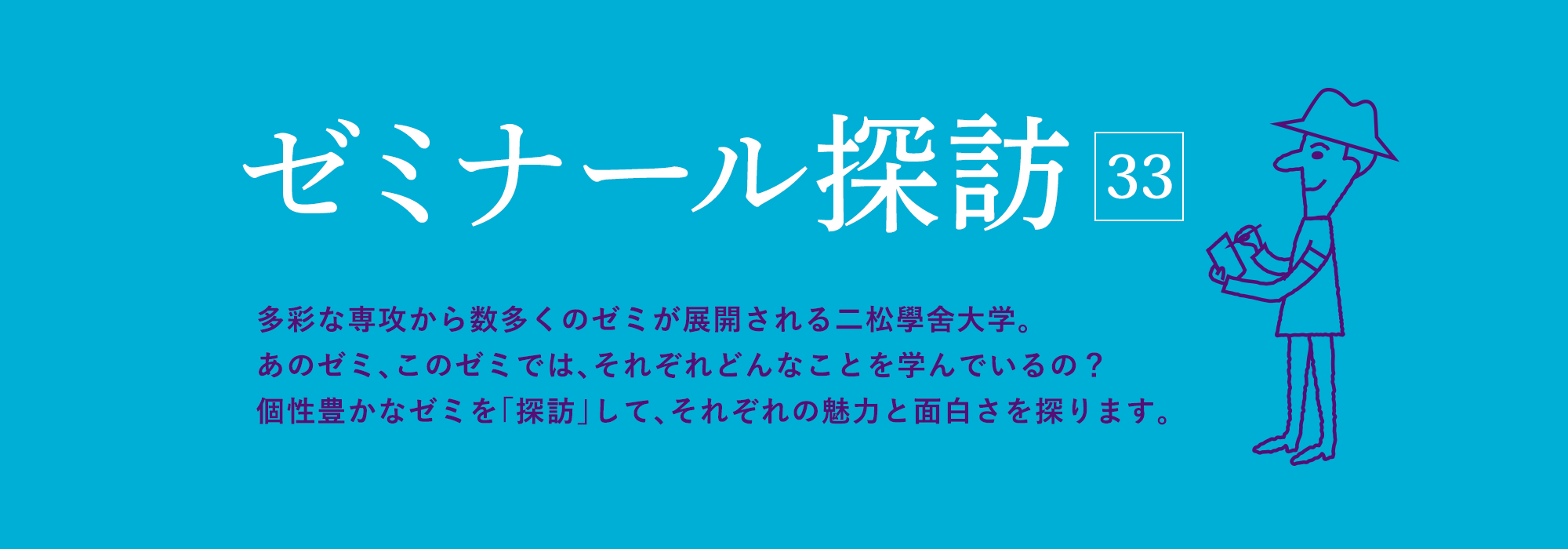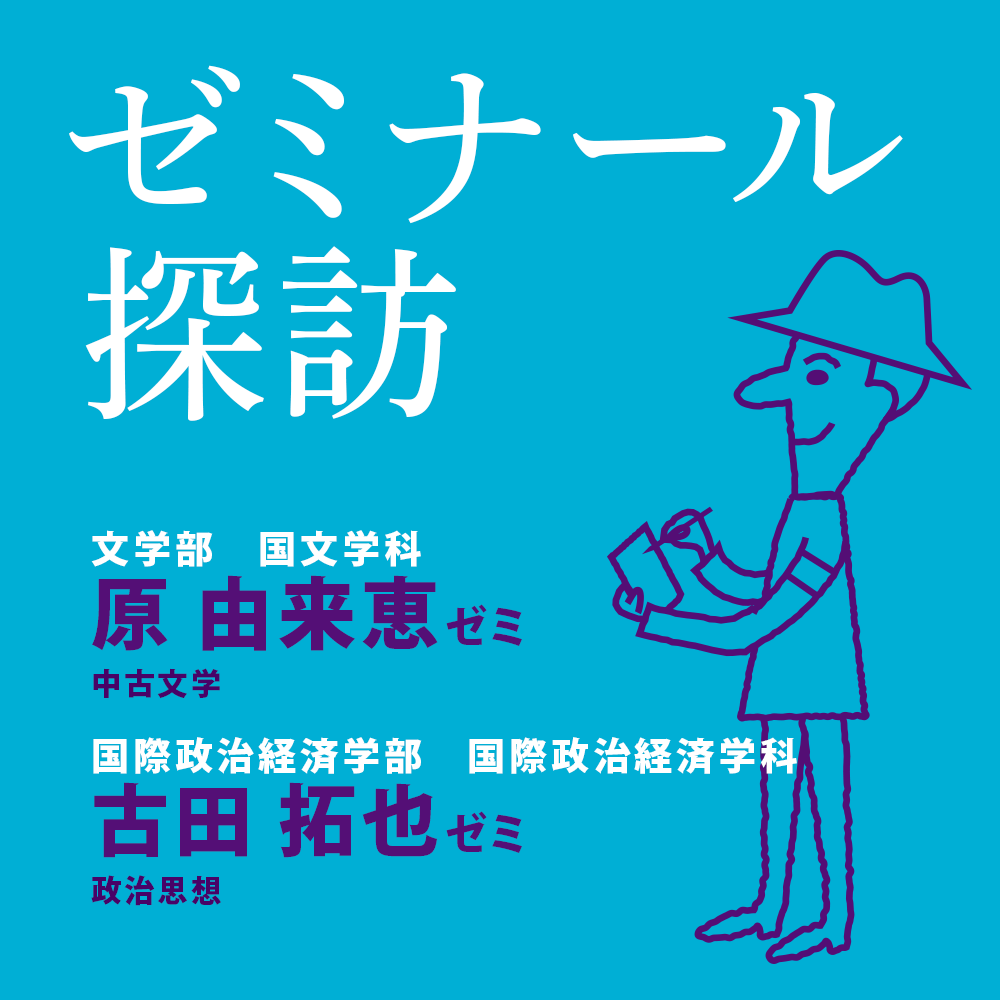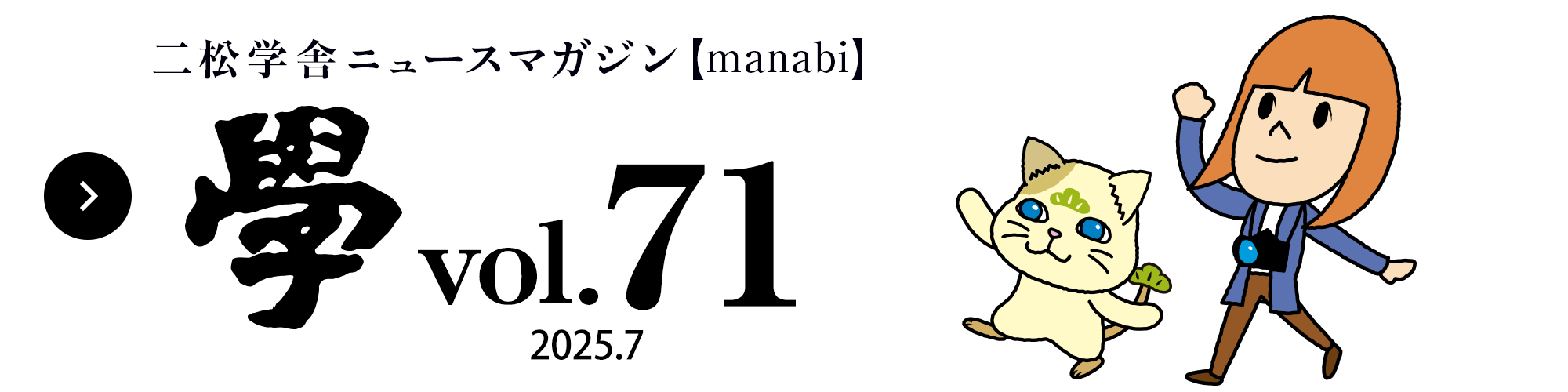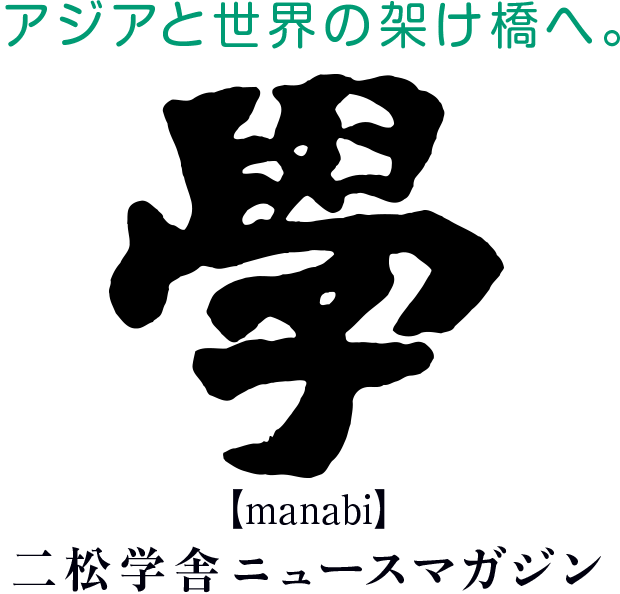文学は「総合科学」。
柔軟な感性や観察力を育む
「枕草子の『星は』の章段には星座についての記述があるように、文学にはその時代の科学的なものも反映されています。文学研究は、作品の背景にある風土や歴史など様々な知識があってこそ深まっていきます。文学は『総合科学』だと私は思っています」
という原由来恵先生の言葉を、ゼミ生たちはしっかり理解しているようです。「平安時代の華やかな宮廷文化に惹かれた」「どうして和泉式部日記は恋愛の歌で構成されているのかに興味をもった」など、二松学舎大学に入り、本ゼミを選んだ理由を明確に語ります。
ゼミは座学だけではありません。夏休みの合宿では京都でフィールドワークを行いました。グループに分かれて平安文学の舞台となった地に足を運び、自分の目で見る。その成果を夜の勉強会で報告し合い、足りない部分は合宿後の文献調査につなげていきます。ゼミ生の一人は、原ゼミの魅力を「いろいろなタイプの人が集まり、各々が得意分野を活かして目的に向かっていくところ」と表しました。ゼミが始まった3年次の春は、互いに遠慮していたけれど、合宿などで協力関係が築かれていくうちに率直になり、多様な視点を取り入れながら考える姿勢が培われたとのこと。
卒業後は「出版社に勤めて、古典の魅力を解説する書籍をつくりたい」「教員になって生徒たちに古典の面白さを伝えたい」「公務員として文化振興に携わりたい」との具体的なイメージを持っています。
「仕事のスキルは社会に出てから身についていきますが、そのための柔軟な感性や観察力、探求心をこのゼミで身につけてほしい。AIが進化し、人間とは何かがますます問われる時代です。だからこそ生まれ育った国の文化や環境、そこでの変化と多様性を理解し、自分の言葉で語れる人材が求められます。そのための日本という国のアイデンティティ、ルーツを学べるのが二松学舎の強みです」
自身もこの学び舎出身である原先生の言葉には説得力がこもっていました。

先人たちの偉大な書物を読み
現代の私たちも賢くなろう
なぜ古田ゼミを選んだのか、という問いに、あるゼミ生は「少人数と聞いたので、活発な議論ができると思った」と答えました。他のゼミ生は本ゼミで「いかに自分ができないかを知る。そこから学びが始まる」と表します。
政治思想史を深掘りする古田ゼミのモットーは“賢くなろう”。今年度のテキストは政治哲学の古典、ジョン・スチュアート・ミルの『自由論』(刊行は19世紀半ば)、トマス・ホッブズの『リヴァイアサン』(同17世紀半ば)、ジョン・ロックの『統治二論』(同17世紀後半)です。
「数世紀にわたって世界の人々に読み継がれている古典です。それらを前にしたら、どんな有名大学の学生でも未熟な存在にすぎません。スタート地点は同じです。だからまずは作品を読み込み、理解できるようになることが大切です」(古田先生)
ゼミでは毎回担当者を決め、テキストをどう解釈したのかを発表します。自分がどこまで理解でき、どこからできていないかを明確にするのです。この日の『自由論』に関する議論は、他者による好ましからざる行為に対して、処罰などの強制力を伴うことなく止めさせるにはどんな方法があるか、という問いでした。本ゼミの目的の一つである「現代の政治から距離をとり、そこから今を見直すきっかけを得る」が実践されているようでした。
古典からの学びは、卒業後にも生きてくると古田先生は考えています。
「どんな仕事でも、相手の話を聞き、それを理解するところから始まります。それでもわからないことがあれば調べる。このゼミで行っていることと変わりません」(古田先生)
ゼミ生に卒業後の進路を問うと、「企業の営業職に就き、相手が何を求めているのかを知り、こちらが提供したいことを豊富な語彙で伝えられるようになりたい」という声も。そのモチベーションにも十分応えているようです。