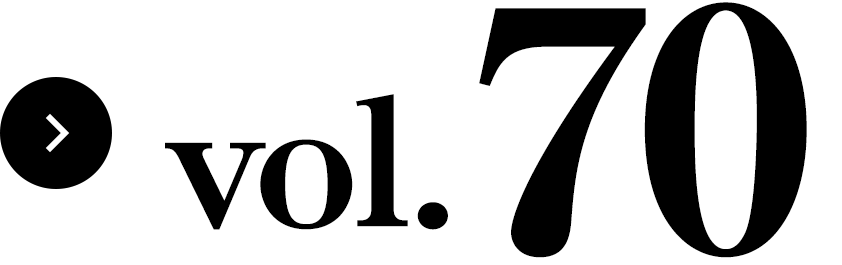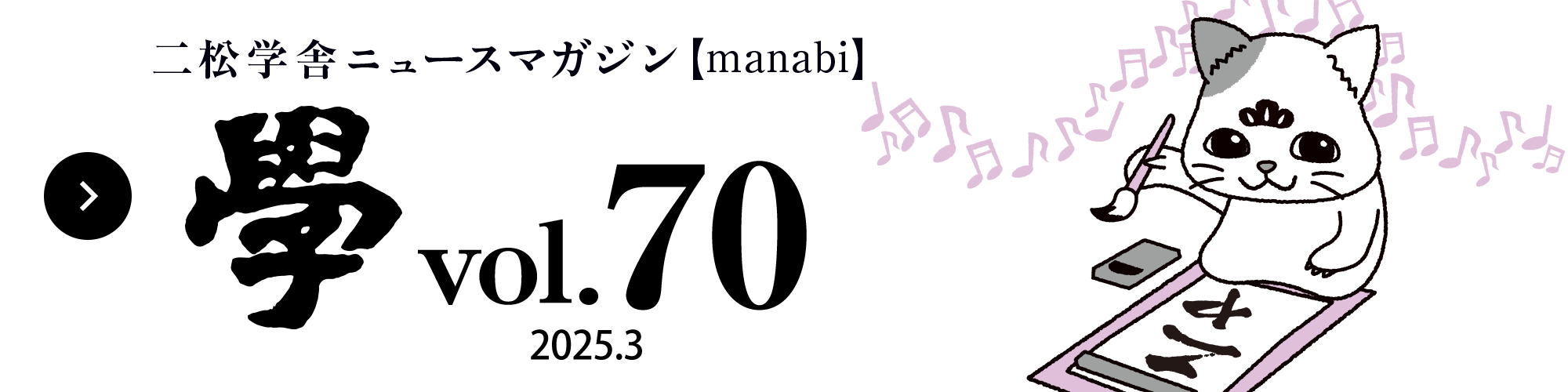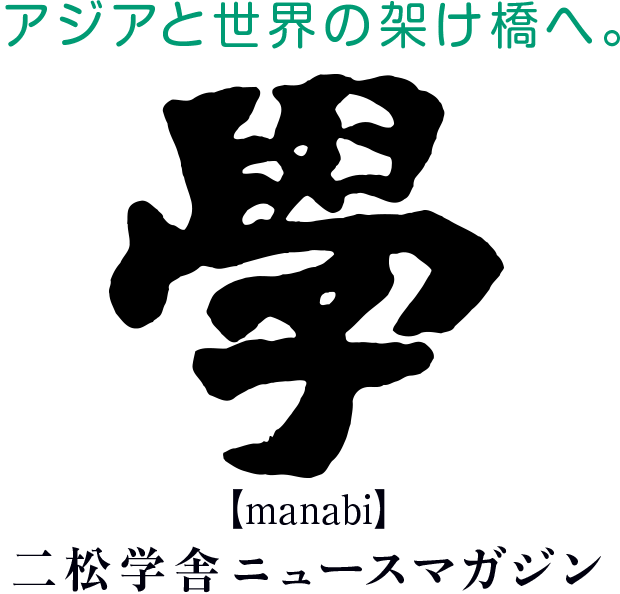「近代日本経済の父」として知られ、本学第三代舎長でもある渋沢栄一の肖像が描かれた新紙幣が、昨年7月に発行されました。これを記念し渋沢とゆかりの深い企業を学生が訪ねる特別企画。今回は東京・内幸町の帝国ホテル東京を国際政治経済学部3年次生の松﨑友香さんが訪問しました。渋沢が同ホテルに残したおもてなしの心や今に生きる言葉などについて、総支配人室次長兼広報課長の山田純平さんに教えていただきました。

株式会社帝国ホテル
帝国ホテル 東京
総支配人室次長兼広報課長山田純平さん
帝国ホテル初代会長を務めた渋沢栄一
松﨑 本日はよろしくお願いいたします。渋沢栄一先生は、御社の設立に深い関わりがあると伺っています。
山田 渋沢栄一翁は、1890(明治23)年に開業した「帝国ホテル」の設立発起人の総代であり、初代会長を務めました。当時の日本は、明治維新の混乱も落ち着き、近代国家としての地位を築こうとしていた頃です。帝国ホテルは「日本の迎賓館」としての役割を担っていました。帝都・東京を訪れる国内外の賓客をもてなすのにふさわしい宿泊施設の整備が急務となり、渋沢翁のほか大倉喜八郎などの大実業家に明治政府が要請したのです。
松﨑 当時はそういった宿泊施設が東京になかったのですね。
山田 たくさんのホテルが建ち並ぶ今では考えられないことですが、帝国ホテルはそのような時代背景の中、開業しました。その後渋沢翁には、およそ19年にわたり経営の舵取りをしていただきました。

企画展示「写真で綴る、帝国ホテル初代会長 渋沢栄一」(現在は終了)
日本の「おもてなし」の心を世界へ
松﨑 渋沢先生は、帝国ホテルの経営についてどのような考えを持っていたのでしょうか。
山田 ホテルの開業式でのお話(東京府知事の祝辞に対する答辞)に、「建物や設備・什器は美を尽くしたものではないが、数百名の賓客をおもてなしするに不足はなく、皿や器も贅をきわめてはいないが、用命があれば世界のどんなものでも調達して便宜を図る。これこそ帝国ホテル自身の果たすべき役割と心得、絶対に譲らないところだ」という言葉があります。
これは、現代社会で帝国ホテルのスタッフとして働く私たちにとっても忘れてはならない〝志〟ではないかと思います。お客様のご要望に誠心誠意向き合い、できる限りそれをかなえる――それこそがホテリエの仕事であり、日本の「おもてなし」の心です。

国際政治経済学部
国際経営学科3年次生松﨑友香さん
今回のインタビューを通して、渋沢栄一先生には先を見据える力があり、様々な面において現代にまで影響を与えていることがわかりました。
インバウンドが拡大している今、「帝国ホテル 東京」のサービスや商品を通して、渋沢先生の教えが、日本だけでなく海外へも自然と広がって欲しいと感じました。

ホテル敷地内に建つ渋沢栄一の石像
松﨑 130年以上前から、今の世にも通じる考え方をされていたのですね。
山田 本当にその通りです。今を生きる私たちへのメッセージのようにも感じられます。当社の役員も年賀式や入社式など社員へ発信する際に、渋沢翁の言葉を引用することが多いです。現代でも通じる言葉を残されているというのは、先見性とともに、物事の本質をとらえていたのだと感じています。

初代会長の渋沢栄一オマージュメニュー。出身地である埼玉県深谷市の名産品、深谷ねぎを丸ごと1本使用した見た目も鮮やかな“渋沢カリー”
インバウンドの増加と観光業の意義
松﨑 コロナ禍、そして東京オリンピック(2021年開催)を経た今、日本は世界中からの観光客で溢れています。ホテル業界も忙しさを取り戻していることと思います。
山田 渋沢翁は海外からのお客様を迎えるにあたり次のような言葉を残しています。「色々の風俗習慣の、色々の国のお客を送迎することは、大変にご苦労なことである。然乍ら君達が丁寧に能く尽して呉れれば、世界中から集り世界の隅々に帰つて行く人達に日本を忘れずに帰らせ、一生日本をなつかしく思出させることの出来る、国家の為にも非常に大切な仕事である。精進してやつて下さいよ」
これは渋沢翁が引退後、従業員を激励された時の言葉ですが、インバウンドのお客様をお迎えするための心構えを的確に表している言葉だと思います。
そして、インバウンドの増加で、観光業の意義を改めて考えさせられています。お客様に優れたサービスと商品を提供することはもちろん、公益性や地域性を重視しながら文化的な発信をすることもホテルの大事な役割ではないでしょうか。例えば、日本の食材を使った料理をレストランで提供すれば、味わい、楽しみながらその国の文化に触れていただくことができます。加えて、その経験がお客様の生活に彩りや豊かさをプラスすることにつながれば、とても意義のあることではないかと思います。
松﨑 今日はたくさんの貴重なお話をお伺いすることができ、とても勉強になりました。ありがとうございました。
※2025年3月(発行月)時点