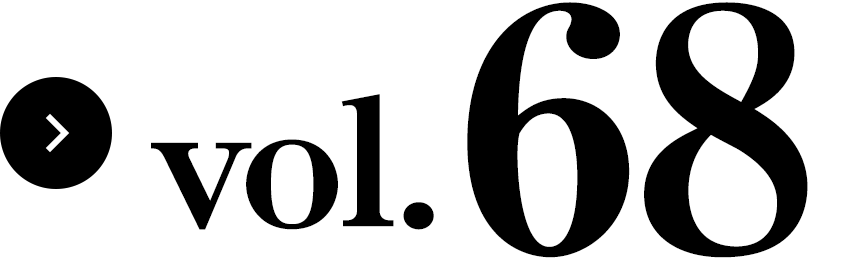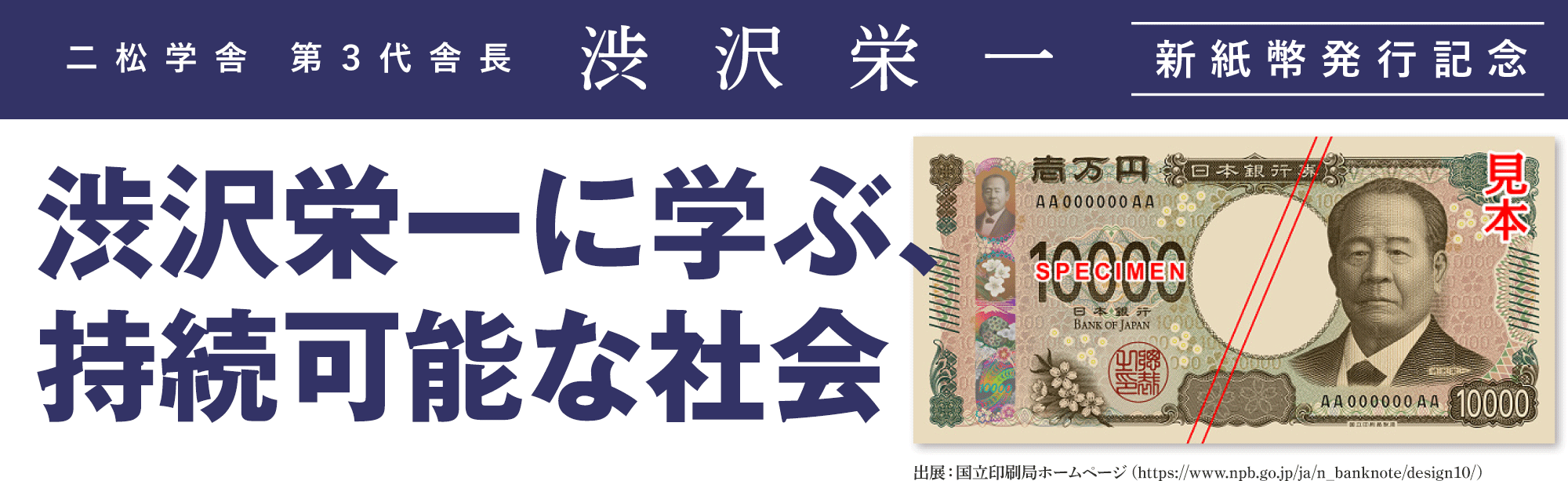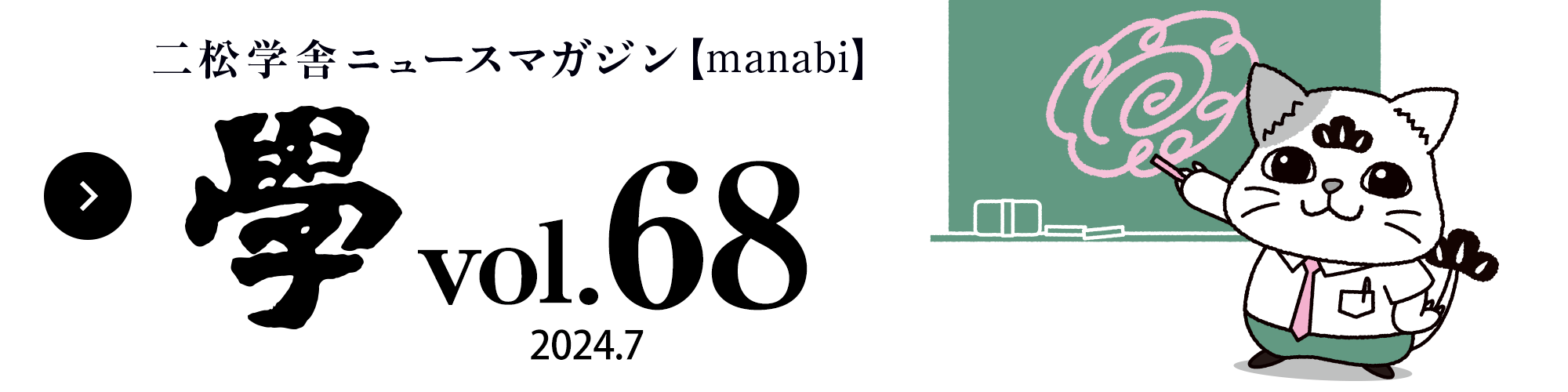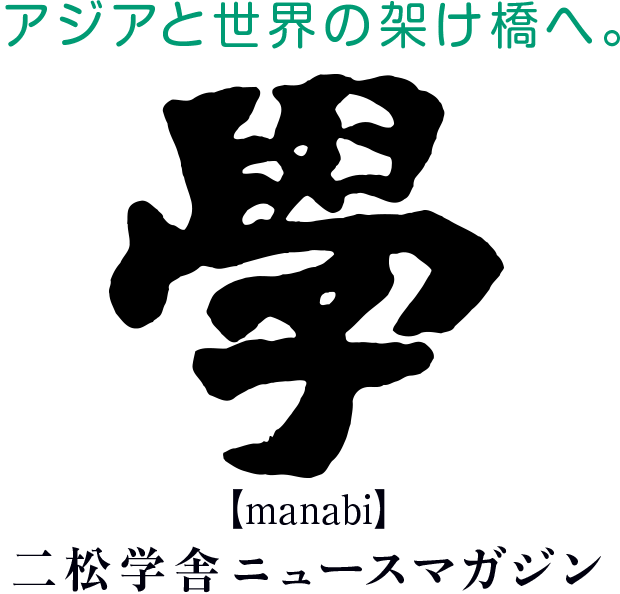渋沢栄一の新一万円札の流通がいよいよ始まります。二松学舎第3代舎長を務めた渋沢の人となりや功績については、この「學」でも何度か取り上げてきました。今号ではこれまで紹介したエピソードや関係者の方のお話を再掲載します。

『學vol.59/2021年7月号』特集より
渋沢栄一の言葉
『論語と算盤』より
正しい道理の富でなければ、
その富は完全に永続することができぬ
『論語と算盤』の冒頭の言葉です。正しい道理の富をなし永続させるためには、道徳と経済というかけ離れたものを一致させることこそ極めて大切だと訴えました。
私の素志は適所に適材を得ることに
存するのである
「素志」とは平素からのこころざしという意味。適材を適所に配置することが、人が国家社会に貢献する本来の道であるということを常に心に置き、自身も実践しました。権力を守るため、能力のある人を閉じ込めてしまうことは決してせず、活動する世界は自由であり、人は平等でなければならないと力強く述べています。
真に理財に長ずる人は、
よく集むると同時によく散ずる
ようでなくてはならぬ
お金は「社会の力を表彰する要具」である。よく集めると同時に善用し、社会を活発にしなければならないと説きました。むやみに物惜しみするだけの「守銭奴(金銭に執着する人)」にならないよう注意を促しています。
※参考文献 渋沢栄一 『論語と算盤』(角川ソフィア文庫)/発行:株式会社KADOKAWA
***

『學vol.54/2019年12月号』渋沢栄一特集より
「論語と算盤」—その目的の現代的意義
渋澤 健(コモンズ投信株式会社取締役会長/シブサワ・アンド・カンパニー株式会社代表取締役)
渋沢栄一は合本主義によって会社の利益が多数へ還元され、国が富むことを目指していました。――一人ひとりが豊かになれば、国が豊かになる。民間力の向上によって、国力が高まる。そして、その未来を実現させる主役は民間の一人ひとりである――渋沢栄一は、「未来を信じる力」の持ち主でした。
その民間人が導く豊かな国の未来を実現させるために渋沢栄一が唱えたのが「論語と算盤」でした。「論語と算盤」の目的の現代的意義とはサステナビリティ(持続可能性)だと思います。論語「か」算盤ではなく、あくまでも論語「と」算盤です。この二つは、未来へ前進する車の両輪のような関係であり、片方が大きくて、片方が小さければ、同じところを回るだけで前進することができません。
そして、ここで大事な要素となるのは、経済社会の原動力となる大河のようにお金が循環することです。それは自分の身丈に合った消費をすること。よりよい社会のために自分の想いを抱いた寄付をすること。そして、持続的な価値創造を対象とした投資を実践すること。
私たち一人ひとりも「未来を信じる力」を少なからず持っています。その微力な未来を信じる力が一滴一滴と寄り合って流れ始めれば「今日よりもよい明日」を実現させる勢力になることでしょう。
※「シブサワ・レター」(2019年5月号)より
***

※三島中洲:漢学者であり、二松学舎創立者。
竹田エリ:二松学舎大学文学部卒業生。『學』にて4コマ漫画「二松のマナビ」連載中。