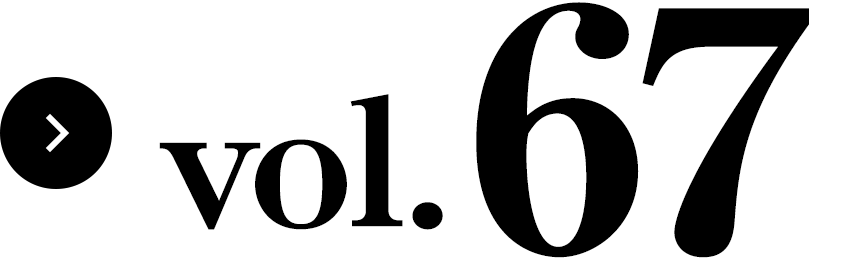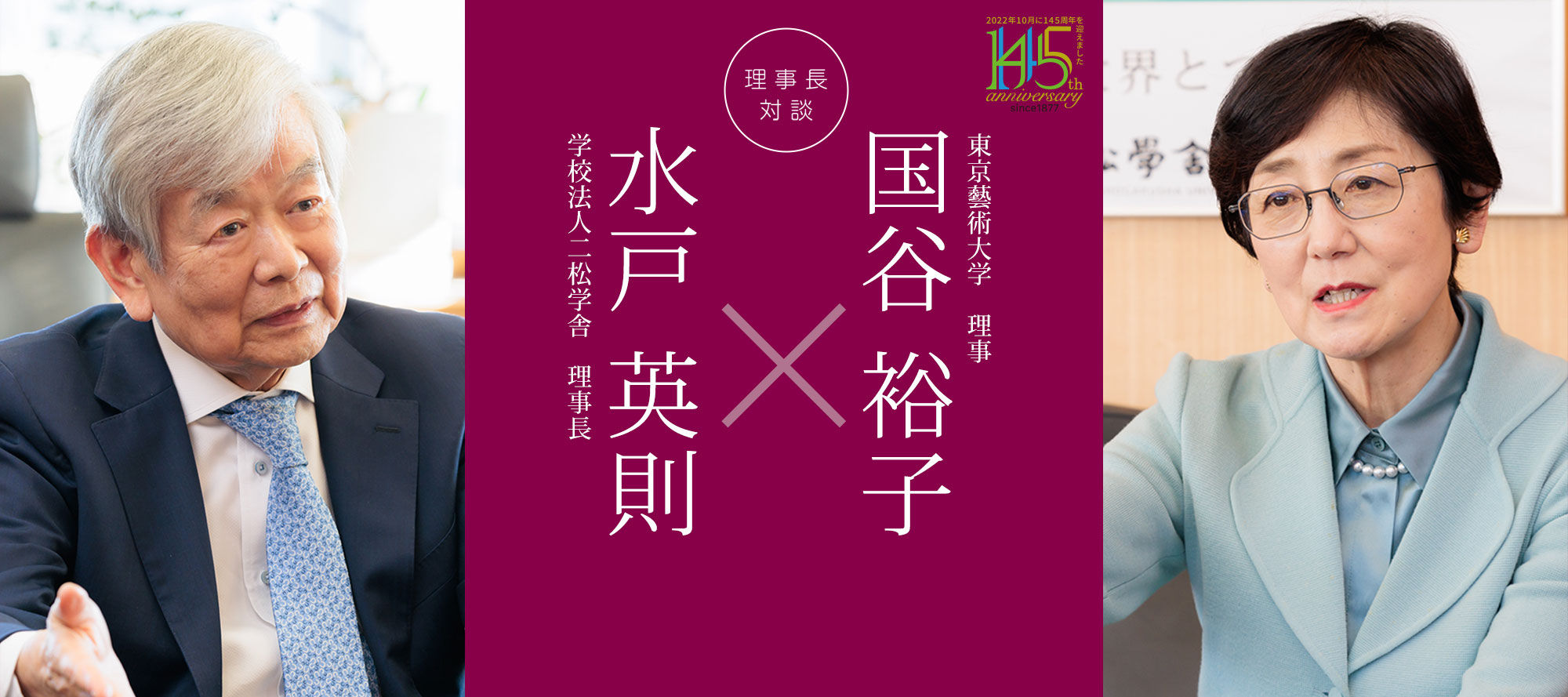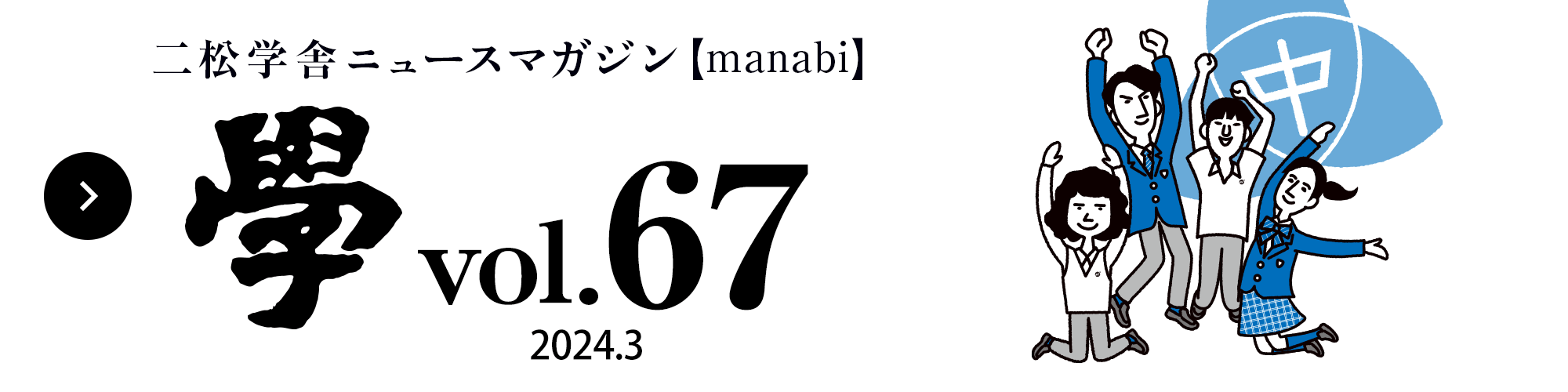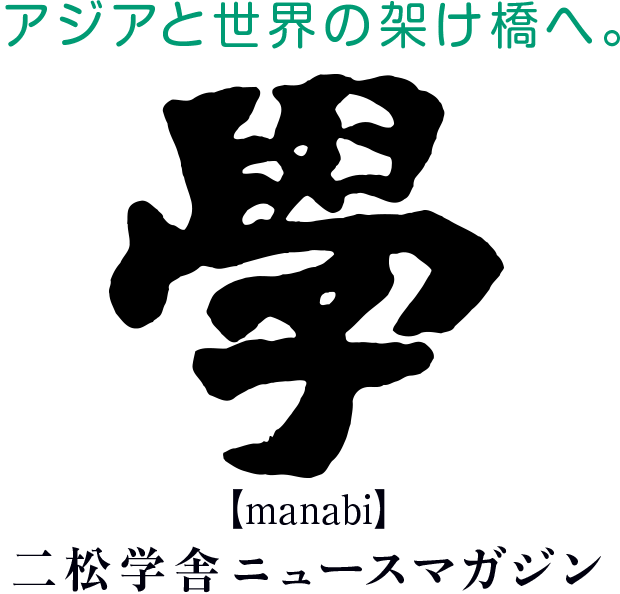NHKの報道番組「クローズアップ現代」の放送開始から23年間にわたり、キャスターを務められた国谷裕子さん。2015年の国連総会へ向けての取材で「SDGs」と出会い、現在もその取材・発信に力を入れています。国谷さんは「今の状況を変えなければ、地球は後戻りできない状態になってしまう」と警鐘を鳴らします。学校教育や若者世代に何ができるのか、水戸英則理事長と語り合いました。
水戸 国谷先生が「クローズアップ現代」のキャスターを務められた23年間で、特に印象に残っている放送はございますか?
国谷 やはり阪神・淡路大震災や東日本大震災の現場は忘れることができません。人々の生活がすべて破壊されたような被害を目の当たりにし、どのような言葉で伝えたらいいのか非常に悩みました。また、イランの映画監督モフセン・マフマルバフさんへのインタビューも、印象深く残っています。アフガニスタンが国際社会から忘れられていく中で、多くの人々がタリバン政権下で苦しみ、難民となって隣国のイランまで何百キロも歩いていくという実情を、涙ながらに語りました。その人でなければ語ることができない言葉と出会った放送は、決して忘れられません。
水戸 番組を離れられてからは、SDGsの啓発に尽力されています。
国谷 SDGsが掲げる17の目標の中でも、気候変動への対応は他の課題解決に連関するものが多く、とりわけ重要だと考えています。また、気候変動は危機的状況を迎えています。2015年に採択されたパリ協定では、世界の平均気温の上昇幅を産業革命前に比べて1・5度に抑えることが目標と定められましたが、すでに1・2度上昇しています。
水戸 SDGsの達成年限は2030年で、残すところあと6年です。日本では国全体としての施策があまり広がっていませんが、ヨーロッパではかなり進んでいるそうですね。
国谷 EUは循環型経済に転換していくためのルールなどをどんどん作っています。例えば、農地に占める有機農業比率の30年目標を25%と掲げ、また売れ残った衣料品の破棄を禁止する法律も作りました。炭素税も導入して化石燃料からの脱却を促進しています。SDGsの正式名称(※1)にTransforming our worldとあるように、変わらなくてはならないのです。
水戸 なぜ日本はTransforming ができないのでしょうか。
※1 「Transforming our world : the 2030 Agenda for Sustainable Development」(我々の世界を変革する:持続可能な開発のための2030アジェンダ)
国谷 一つは大量生産、大量消費、大量廃棄から企業がなかなか脱却できないこと。それから、危機感の欠如も関係していると思います。若い世代で言えば、SDGsの認知度は約9割で、世界に比べても突出して高いんです。でも、イギリスのバース大学などが行った調査では、「気候変動が人々や地球を脅かすことを心配していますか」という問いに「極度に心配している」「とても心配している」と答えた割合は、日本が16.4%と最少。最多のフィリピンは84%、次のインドは68%でした。日本人はSDGsを知っていても自分事になっていない。そこが一番の問題です。
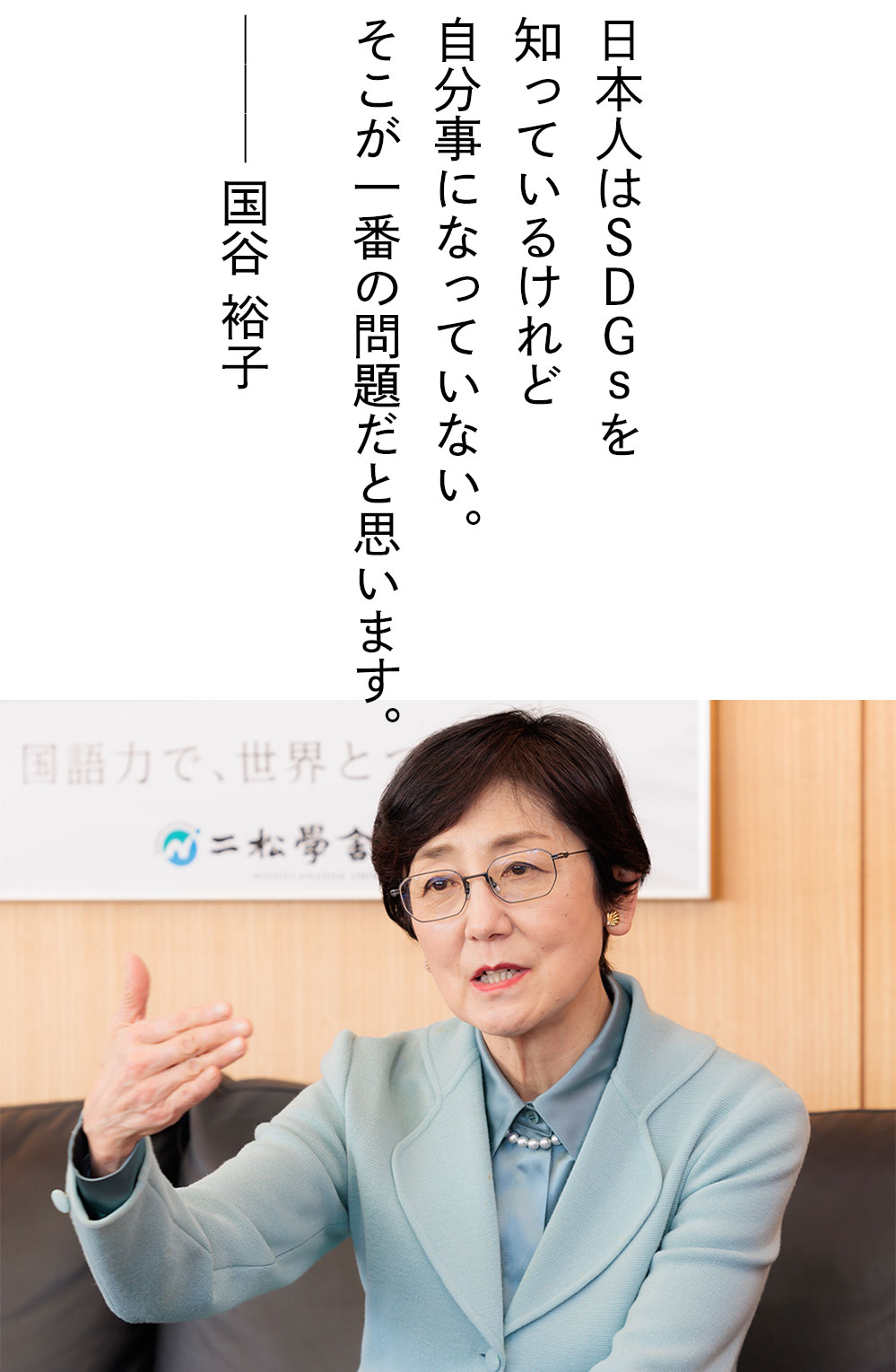
くにや・ひろこ●大阪府出身。米ブラウン大学卒業。NHK『7時のニュース』英語放送の翻訳、アナウンスなどを経て、89年からNHK衛星放送『ワールドニュース』キャスター。93年4月から2016年3月まで『クローズアップ現代』のキャスターとして現代社会の多様な問題を伝えた。現在は、SDGsの取材・啓発を中心に活動。東京藝術大学理事、慶應義塾大学大学院特別招聘教授。著書に『キャスターという仕事』(岩波新書)『クローズアップ藝大』(河出新書)など。
水戸 学校における環境教育では、何が最も重要だと思われますか?
国谷 科学的事実をしっかりと伝えてください。例えば、日本の上空の大気中の二酸化炭素濃度は、1987年の観測開始から35年間で2割も高まっています(※2)。しかも10年毎の濃度の増え方を見ると、増え幅は加速度的に増加しています。この事実だけでも危機感を持つべきです。
※2 気象庁 綾里観測地点(岩手県)の年平均
水戸 エビデンスに基づいて、地球の危機的状況を教えていくのですね。
国谷 それに加えて、若者たちが話し合いやすい仕組みも大切だと思います。私が関係する慶應義塾大学では、学生がディスカッションする「塾生会議」があります。SDGsが掲げている17目標に即して、慶應義塾で何ができるか徹底的に議論し、塾長に提案しています。ペットボトルを学内から減らすためにウォーターサーバーを置く提案は実現しました。自分たちで考えたことが学校で実現したら、ものすごい成功体験になりますよ。
水戸 若者たちが主体的に考える環境教育は非常に有意義ですね。
国谷 昨今のメディアは、ものごとの白黒をはっきりつけ、分かったような気にさせる傾向があります。でも、実際には無限のグレーがあり、そこが大事なわけです。よく分からないけれどざらついたものが頭の中に残ると、何か関連する情報を得た時に「そういえば」と再び考え始めます。ですから、学校の授業もあまり分かりやすくしない方がいいと思います。
水戸 仰る通りです。疑問を持って探究するマインドが起きると学びが深まり、思考能力も高まります。
国谷 二松学舎には、生徒や学生が自ら考え、活発な議論ができる学び舎になってほしいですね。先生への質問の多い教室を評価するのもいいのではないでしょうか。そこから、豊かな対話が始まっていきます。
水戸 まさにアクティブラーニングですね。学校にできることはまだまだ多いことを、改めて考えさせていただきました。

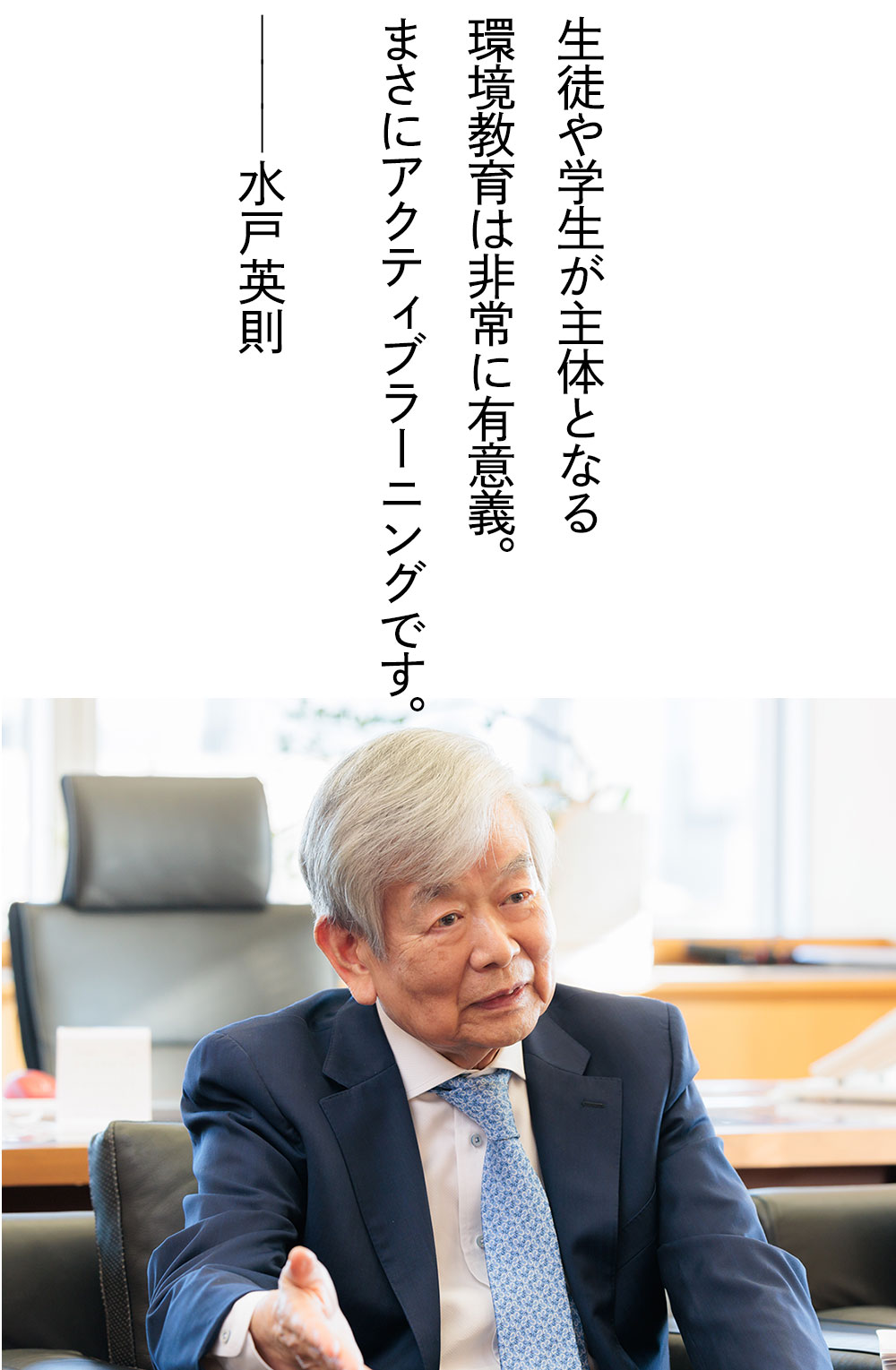
みと・ひでのり●1969年九州大学経済学部卒業。日本銀行入行、フランス政府留学、青森支店長、参事考査役などを歴任。2004年、二松学舎に入り、11年理事長に就任。文部科学省学校法人運営調査委員、日本私立大学協会常務理事、日本高等教育評価機構理事などを務める。