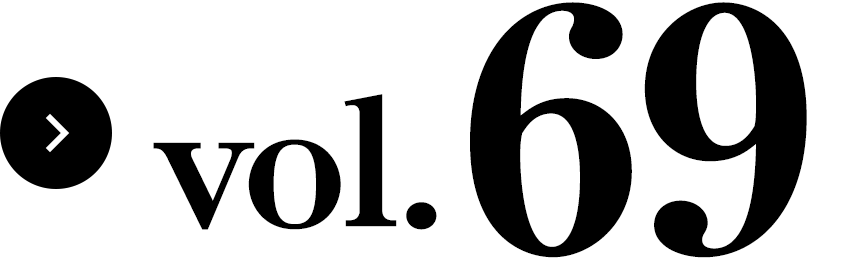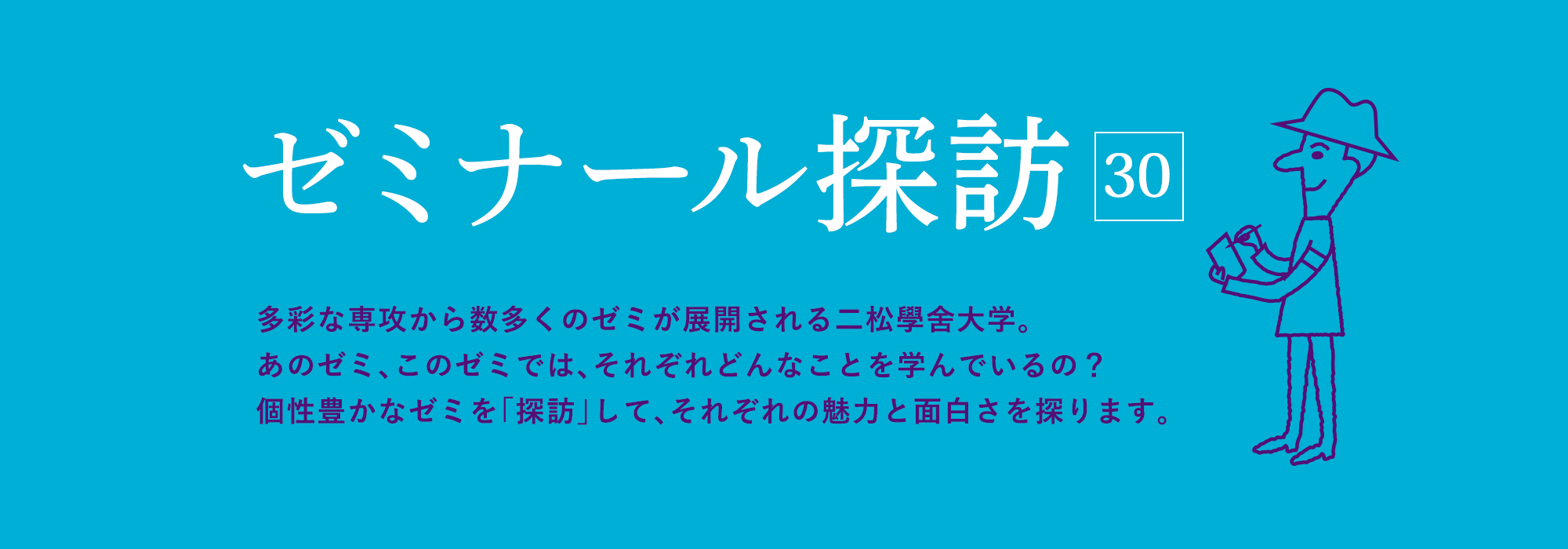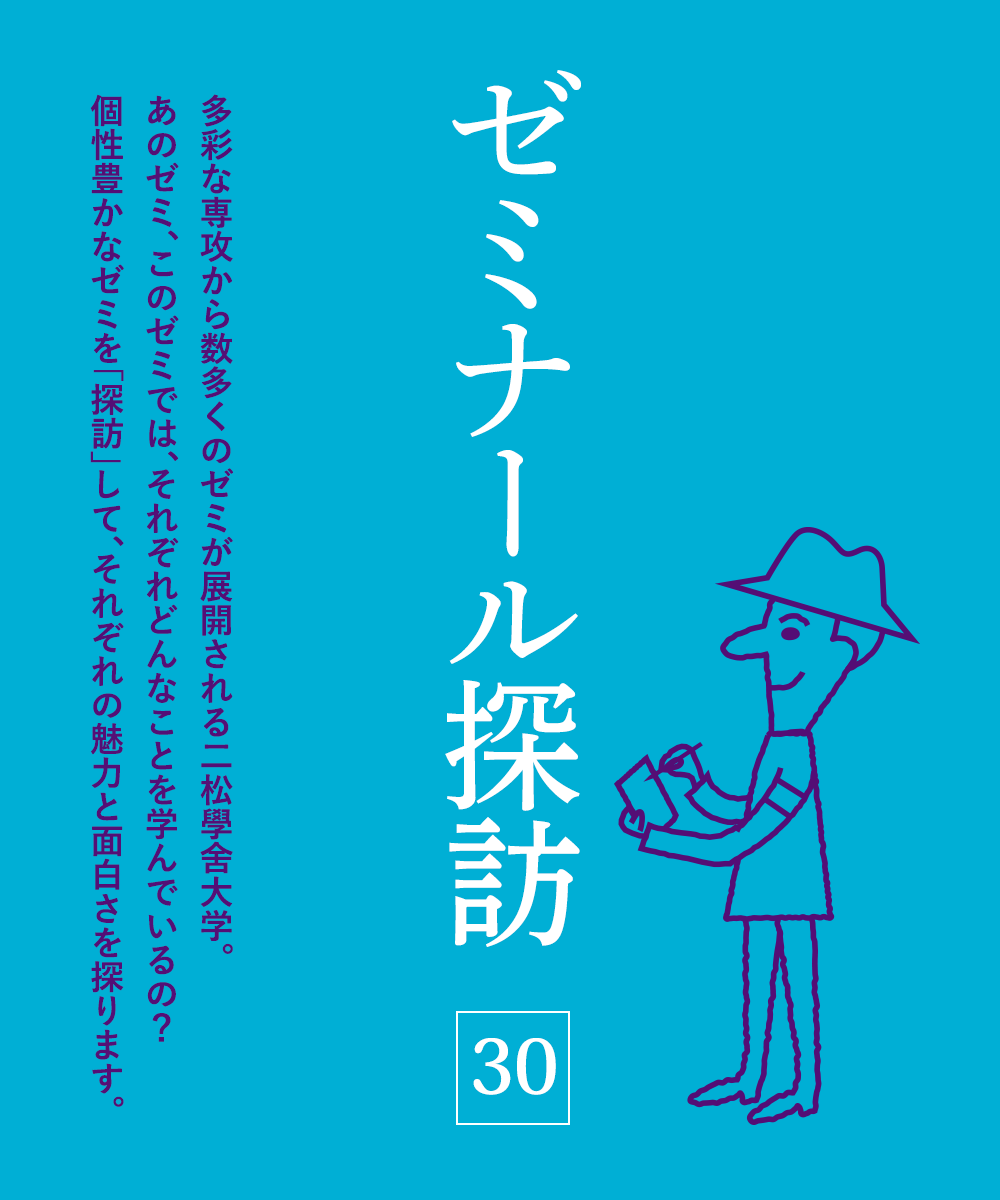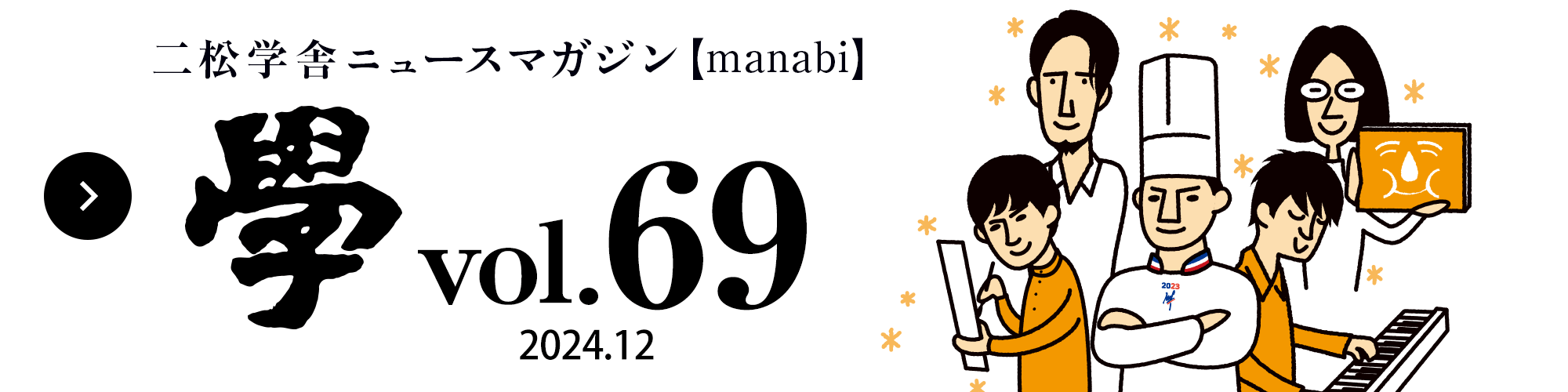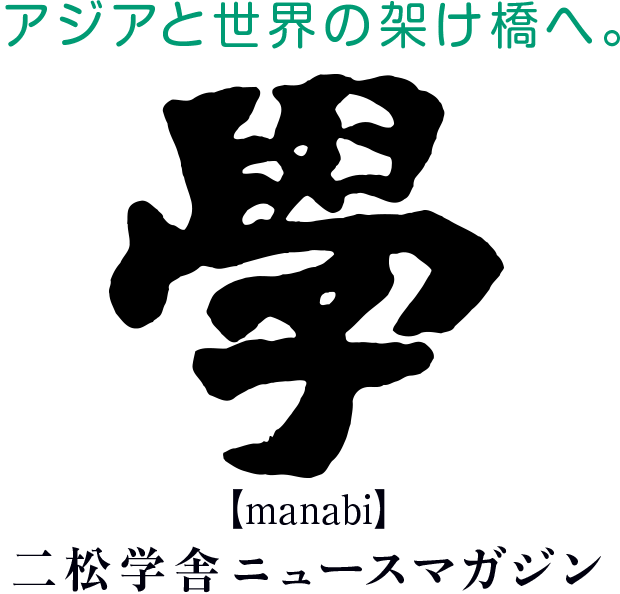書の本質を極め、視野を広げる。
批評された経験も「糧」となる
巻物の開き方や仕舞い方、掛け軸の掛け方。この日のゼミは、作品の取り扱いを実際に行ってみるところから始まりました。
「書道のゼミというと、学生が書いた作品を教員が批評するだけというイメージを持たれるかもしれませんが、ぼくは書をトータルで理解する人を育てたいと考えています。だから作品の取り扱いについてもきちんとした知識を得てほしい」
関俊史先生はこう話します。
「これからの書道界は、作家が自らの作品を解説できなければなりません。たとえば、その表現のためにどのような用具用材を使ったのか、どのような背景を持った作品なのかなど。そうしたことが説明できなければ人の心を動かすような作品はできません」
その方向性に共鳴しているのか、ゼミ生に書道を専攻した動機を聞くと「文字を芸術にまで昇華できる。それが魅力」といったものから、「書道を続けていると、自分の成長過程が目に見えてわかる」「人間は生きている間、字を書いているから」などの答えが返ってきました。また、ゼミ選択の決め手として「中国語と書道でゼミを迷いましたが、古典を通して書の技術を研鑽できる関先生のゼミがいいと思った」という学生もいました。
「一枚一枚の作品に真摯に向き合い、一生懸命取り組んだ記憶が糧になる。作品を厳しく批評されたことも自分の強さにつながっていくはずです」と語る関先生が、学生に期待することは、書道の本質を極めながら、あらゆることに対して興味を広げていくこと。
そのために心がけている指導の一つがマンツーマンです。「ぼくはゼミ生の表情や雰囲気を見ながら、授業の内容を考えます。作品をたくさん書いてくれば、この学生には、次はこのレベルを目指す指導をしよう。用具用材に興味のある学生が多ければ、学外に紙を漉きに行ったら面白いんじゃないか、などと考えます」(関先生)
学生たちの熱心さとともに広がり変化する学びの形。先生とゼミ生が一緒になってつくっていくのが関ゼミなのかもしれません。

二玄社作製 唐・孫過庭「書譜」複製
世界に関心を持つことが
より良い社会につながる
貧困、難民、差別、紛争。そうしたグローバルな課題を国際社会でどのように解決していくかが、阿部和美先生のゼミのテーマです。阿部先生は、「自分の考えを言葉にする」ことを重視しています。
「最近の学生は自分の率直な意見を言わない傾向があります。せっかくゼミで一緒になった仲間同士。自由に議論を交わせる。そんな雰囲気づくりに努めてきました」(阿部先生)
ゼミ生たちに阿部ゼミの魅力について聞くと、「貧困問題とSDGsに関心があった。卒業後は国際協力の現場で働きたい。環境問題に取り組む企業のインターンシップに参加する際には、ここで学んだことが活かせると思う」「卒業論文ではジェンダー問題、特に夫婦別姓をテーマに取り上げたい」「普段から積極的にニュースに接し、情報を取りにいく力がついた」と明確な答えが返ってきました。
積極的な議論が交わされるのは、先生とゼミ生の間に信頼関係があってこそ。自分の意見が尊重されるという実感をみんなが持っており、黙っていると先生や仲間が声をかけてくれるそうです。
後期では学術的文章の作成という授業も行われています。ゼミのメンバーが一枚の紙にまとめた序論、本論、結論を読み込み、文章表現の的確さや論理性の有無をチェックします。
「私はよく理解しないまま頷いてしまうところがあって、阿部先生からは『わからないことをはっきり伝えたほうがいい』と指導されました」「その場の思いつきで安直な意見を言うと、すぐに先生から質問されます。いい意味で緊張感があります」とゼミ生は語ります。
国際NGOや国連、防衛省などでの実務経験も豊富な阿部先生。ゼミ生の将来に向けて、次のようにメッセージを送りました。
「卒業後どんな職業に就いても、自分の仕事が世界とつながっていることを意識してほしいです。自分の生活の外に目を向ける人がひとりでも増えれば、社会はよくなる。それは自分自身が心地よく生きられる社会づくりにもつながります」