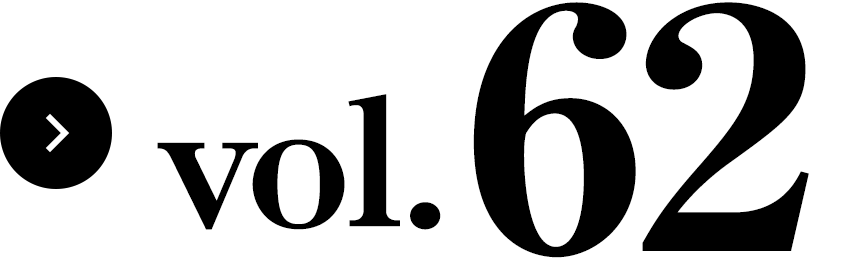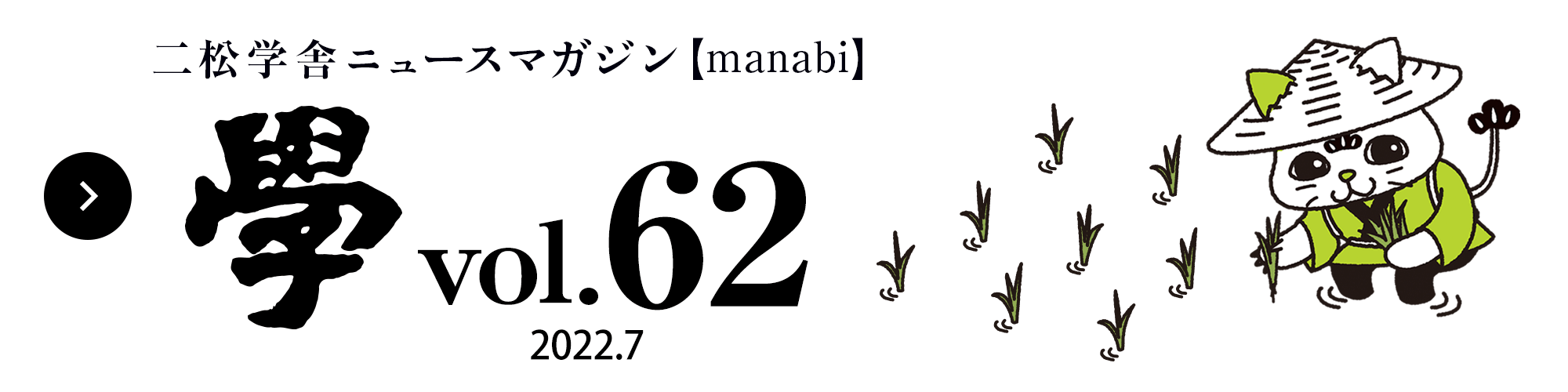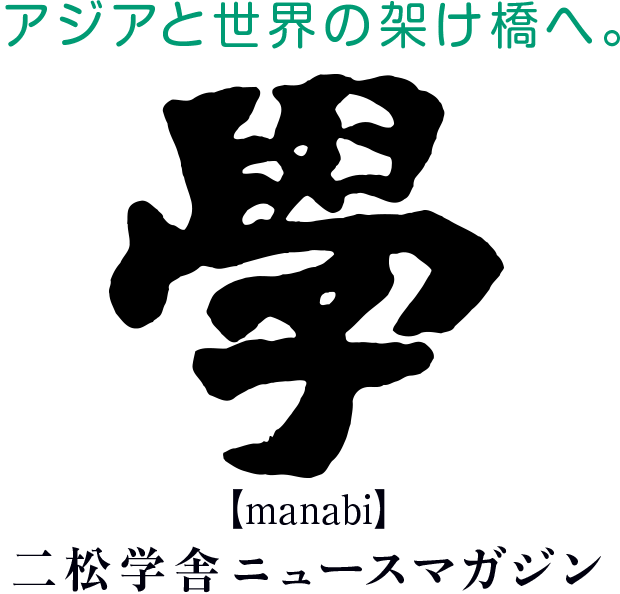世界的な気候変動が深刻化する今、持続可能な社会を実現するには一人一人の意識変革が求められています。本学では、創立145周年の節目を機に、過去の歴史を振り返りながら、新しい時代の教育のあり方を検討しています。国際社会共通の目標として「SDGs」(持続可能な開発目標)が掲げられていますが、江戸時代にはすでに循環型の経済システムが回っていたと言われます。なぜ、江戸時代にそれが可能だったのか? これからの社会や教育の目指すべき道のヒントはあるのか? 江戸文学・江戸文化研究者の田中優子先生と、本学国際政治経済学部国際経営学科の小具龍史准教授が対談しました。
江戸時代の大量伐採を幕府や藩はどう統治したか
小具 持続可能な社会の実現に向けて、SDGsでは17の目標を挙げています。中でも、私たちの社会生活を根底から脅かす気候変動問題は重要性が高いように感じます。気候変動が起きた背景について、田中先生はどのように捉えていらっしゃいますか。
田中 もともとはヨーロッパの近代化に端を発していると思います。15世紀末からの大航海時代では、ヨーロッパの人々がアメリカやアフリカの大陸を侵略し、植民地主義が広がりました。当然、農地は拡大し、森林伐採も始まりました。イギリスは、植民地にしていたインドから綿花と綿織物を輸入していましたが、18世紀後半に産業革命が起こると、自国で綿織物を大量生産するようになりました。イギリスは安価な綿織物をインドに大量に売り込み、インドの綿産業は廃れていきました。こうして、非常に長い年月をかけて大量生産・大量消費の構造が広がり、その限界を超えたことで急激な気候変動が起きたのではないでしょうか。
小具 日本では1960年代の高度経済成長期に、公害などの環境問題が噴出してきました。先生のご専門の江戸時代と比較して、現代の企業活動に相通ずるものはありますか。
田中 江戸時代にも、企業活動に近い商工業者の活動は始まっていました。ただ、資源の扱い方は、現代の企業とはずいぶん違います。
例えば木材は、非常に重要なエネルギー資源かつ建築資材でもありますから、お米の次に大切にされていました。火事が起きた時に備えて、深川にはたくさんの材木が浮かべられていたのです。それだけ需要が高いので、江戸時代の1660年代までは大量伐採が行われていました。その結果、山の樹木が少なくなり、大雨が降ると洪水が起こりました。
この問題を解決しようと、江戸幕府は「諸国山川掟」といって、河川の上流域の森林伐採を制限する掟を発令しました。木の根まで掘り起こすことを禁止したり、山の中でも伐採を不可とする場所を定めたりしたのです。伐採に制限をかけることで森林は維持されるだろうという「消極的管理」の時代でした。幕府だけでなく、同じような掟を設ける藩もありました。その後、1700年代に入ると「育林時代」に移ります。人口が増え、伐採を制限するだけでは間に合わないので、植林が始まったのです。
小具 非常に自制がきいていたのですね。日本の高度経済成長期の企業活動は、業績が上がればそれでよしとばかりに「行け行けドンドン」で突っ走っていました。後世であるにもかかわらず、江戸時代の知見があまり生かされていないことに衝撃を感じました。
「排泄物の循環システム」は農民の知恵から始まった。
田中 江戸時代は幕府や藩だけでなく、農民の中でも資源を大切に扱う知恵や工夫が生み出されました。一例を挙げると、当時の紙などは一年草が原料でした。その他の素材も含め、毎年栽培しなければなりませんから、翌年のことを考えて、収穫する時に根は残すなど調整していたのです。
よく知られる排泄物の循環システムも、農民から始まりました。江戸時代は、武士が都市部に集住し、消費生活に必要なものは周辺の農村が供給していました。その営みの中で、農民たちは都市部から排泄物を引き取って堆肥(下肥)を作るようになります。そのうち下肥は商品化され、問屋になる農民もいました。人を雇ってくみ取りに行かせ、作った下肥を売ったのです。さらに、農民たちは儲けるだけでなく、都市部から排泄物を引き取る時に下肥代を払っていました。少しでも報酬があると、排泄物を出すほうも積極的になり、経済循環へとつながっていったのです。同じように、ゴミを燃やした灰も肥料になるので、商品として取り引きされていました。
小具 地域が富む循環システムを自分たちで作り上げたのですね。現代では、企業のCSR(社会的責任)として環境保全などの社会貢献活動が行われています。2010年代以降は、もう一歩踏み込んで「CSV」(Creating Shared Value:共有価値の創造)という考え方も出てきました。企業は、利益を出しながら社会的課題を解決することが求められるようになったのです。でも、必要性はわかっていても、実践できている企業は限られています。江戸時代のように住民を巻き込み、地域経済に利益を還元する仕組みが必要なのではないかと、今のお話を聞いて感じました。

たなか・ゆうこ●1980年度より法政大学専任講師。その後、助教授、教授。2012年度より社会学部長。14年度より総長。21年度より名誉教授、江戸東京研究センター特任教授。専門は日本近世文化・アジア比較文化。研究領域は、江戸時代の文学、美術、生活文化。『江戸の想像力』、『江戸百夢』、『カムイ伝講義』、『未来のための江戸学』、『グローバリゼーションの中の江戸』、『布のちから』、『江戸問答』など著書多数。サントリー芸術財団理事。TBS「サンデーモーニング」のコメンテーターも務める。
田中 私も、当時の仕組みは大切な示唆を与えていると思います。と言うのも、江戸時代の人たちは、倫理観から循環型システムを作ったわけではありません。排泄物を回収しないと川が汚れる、ゴミが堆積すると舟が通れなくなるといった、目に見える危機があったわけです。それらを肥料にして売ることで、自分たちの生活が助かる。そういう動機付けがあって循環システムが徐々に作られていきました。今、私たちが直面している気候変動は重大な問題ですが、今日、明日どうにかなる話ではないだけに難しいですね。
小具 確かに、気候変動の影響も、二酸化炭素の排出量削減も目に見えるわけでありません。そこの情報をどう開示するかは、解決のカギになりそうですね。
田中 江戸時代の循環システムにはもう一つ、ものを使い尽くす文化も挙げられます。 一枚の着物も、誰かが着たあとに質屋や古着屋を回っていろんな人が着て、使い尽くされることが当たり前でした。紙も大事にされていて「すき返し紙」と言って、今で言うリサイクルペーパーがすでに作られていたのです。その根底には「もったいない」という価値観がありました。「もったい」とは、そのものの存在価値を意味する言葉で、「もったい」がなくなるというのは大問題だと考えていたわけです。
小具 現代のリサイクル企業は、大量生産・大量消費で公害が社会問題化してから登場しました。江戸時代のものを大切にする精神は、どこかのタイミングで置き忘れてしまったのですね。
田中 日本に先んじて近代化を遂げた欧米では、大量生産したものを売る市場を求めていました。日本が開国すると、大量にものを作って売り、お金を得るという経済システムがどっと押し寄せました。
繊維分野では、ずっと農家が行っていた機織りや糸取りなどが工場に集約され、女性たちが一斉に作業するようになりました。江戸時代は職住近接が普通だったところに、「会社に通って働き、一定の給料をもらう」というスタイルに置き換わったのです。こうして大量生産は、働く場所からお金の獲得方法までのすべてを変えていきました。
小具 大量生産システムは、人々の価値観にも影響を与えたのですね。同時に、明治期以降は「とにかく国を富ませよう」という大きな流れが生まれ、富国強兵、領土の拡大、外貨の獲得など拡大傾向に向かっていきました。
田中 そうですね。江戸時代の265年間は戦争がなかったのに、明治になった途端に戦争が起きたのは、やはり富を得るためです。戦争をすると企業に利益が出ますし、他国からの援助も来ます。企業同士の利益の勝負は、国の戦争とも明確につながっているわけですよね。そして、戦争は最大の環境汚染でもあります。
企業活動と社会貢献が両立する時代に。大学の役割は?
小具 国も企業も、営利優先の姿勢から変わっていかなければ、環境問題は非常に難しい展開になることでしょう。国民全員で危機意識を共有する場がなくては、気候変動からの脱却は進まないと思います。そこで、教育が果たす役割はますます重要になるわけですが、今の学生は環境問題に関する危機意識が非常に高いように見えます。田中先生は、どのように捉えていらっしゃいますか?
田中 社会の役に立ちたいという希望を持っている学生は確実に増えていますね。ボランティア活動のために地方を訪れ、そのまま移住する人もいます。私が学生だった1970年代は、大企業志向が強い時代でしたが、今はだいぶ変わってきています。むしろ「自分が生き生きと働ける場所はどこか?」という視点で将来を考える学生が多いのではないでしょうか。
ただ、彼らが企業の中で自分の意見を主張できるかどうか。そこが、これからの課題だと思っています。以前に比べると、企業の体質ははるかに柔軟になり、企業活動と社会貢献が対立しないようになってきました。若い社員も「これは社会貢献だけれども、会社への貢献でもある」と主張できるようになってきていますよね。以前より希望が持てると思います。

おぐ・たつし●二松学舎大学国際政治経済学部国際経営学科准教授。立教大学大学院経営学研究科経営学専攻博士課程後期課程修了、博士(経営学)。専門社会調査士。国内メガバンク系シンクタンク(現みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)を経て現職。専門は新製品開発、消費者行動論、マーケティング論。大手企業の新規事業開発支援、マーケティング戦略策定等のコンサルティング、官公庁の調査研究事業を多数推進。民間企業の経営顧問・アドバイザー等を務める。
小具 まさしくCSVの考え方ですね。若者の思いを受け止め、事業として取り入れる企業が増えると、持続可能な社会へと近づいていくように思います。そうした時代において、大学教育はどうあるべきでしょうか? 私の専門領域であるマーケティングの講義やゼミでは「消費者のニーズをもとに、環境志向型の商品を開発するには何が必要か」「社会的課題を組み込んだ事業を立ち上げる考え方」などを教えており、学生たちは真剣に考えています。
田中 私が総長を務めていた法政大学では、SDGsの17項目に当てはまる科目すべてに印をつけて「SDGs科目群」を作りました。その科目数は200以上にのぼり、一定以上の単位を取得するとSDGsを学んだことの証明をもらえる仕組みです。これからの若者たちには、企業の視点を超えた広い視野が必要です。企業が利益を得る方法だけではなく、世界はどう動いているか、本当に望ましい方向性はどっちかという視点を持たなければ、社会を変えるアイデアは生まれません。
小具 本学の国際経営学科では、1年次からすぐに経営学概論を勉強します。学部には法律・政治・経済が専門の教員がいますから、国際政治、海外事情、地政学、宗教のことまでも学べます。経営学科だからといって経営学だけを勉強していては、なかなか柔軟な発想が養われません。そのため、リベラルアーツの観点から幅広い教養を基礎から身につけた上で、高度な学習をしていくカリキュラムになっているのです。
また、本学の原点は漢学塾ということもあり、寺子屋式の少人数制ゼミを大切にしています。国際政治経済学部、文学部ともに横断的に学ぶこともできます。
持続可能な社会に向けて漢学を教え続ける大切さ
田中 漢学を基本にしている大学は、本当に貴重だと思います。入試から漢文の出題が減らされ、古典の授業もどんどん削られる今、漢学を学ぶ機会は非常に少なくなりました。でも、漢学は哲学としても非常に奥深い世界を持っているわけです。経済という言葉のもとになった「経世済民」は「世の中をおさめ、人民を救う」という意味ですが、江戸時代の大店の経営者たちも大きな影響を受けていました。特に初期の豪商は、自分たちの利益を使って川の開削をしたり、橋を架けたりして、社会に還元していました。お金を儲けるだけではなく、世の中全体を大切にしていたわけです。貴学には、そうした漢学の価値観を、ぜひこれからも学生たちに伝えていってほしいですね。
小具 二松学舎を創立した漢学者・三島中洲は、渋沢栄一が唱える「道徳経済合一説」で渋沢と意気投合しました。経世済民の精神に基づき、企業は営利の追求にとどまらず、社会的課題の解決も両輪としなくてはならないとする理念です。渋沢栄一はのちに、本学の第3代舎長に就任しました。本学では1年次に、自校の歴史を学ぶ科目があり、渋沢栄一の軌跡にも触れています。
田中 もう一つ、日本とアジアの関係も、これから非常に重要になると思います。私たちは中国、韓国のことも、東南アジアのことも知らなすぎます。戦争に備えるという話ではなく、もっと手前の段階で、日本とアジア諸国との関係性について大学で教えなければならないと思うのです。学生のうちはピンと来なくても、社会に出れば「日本って何だろう?」と思う機会はきっと訪れます。その時、アジア諸国とのつながりを理解していなくては、単なるナショナリズムに陥ってしまいます。
小具 まさしく、この『學』のキャッチフレーズも「アジアと世界の架け橋へ。」です。本学には中国など東アジアを専門に研究する教員がおり、資料も豊富です。東アジアはこれからも経済成長を続け、世界における重要性は増すことでしょう。持続可能な未来を切り拓く若者たちに、日本だけに閉じこもらず、広い視野を持つことを伝えていきたいですね。田中先生のお話を伺い、伝統を引き継ぎながらも、新しい価値観を教えていく意義を再確認しました。本日はありがとうございました。