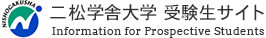上代から近現代までの
作品を読み解き、
深い考察を展開する。
国文学専攻
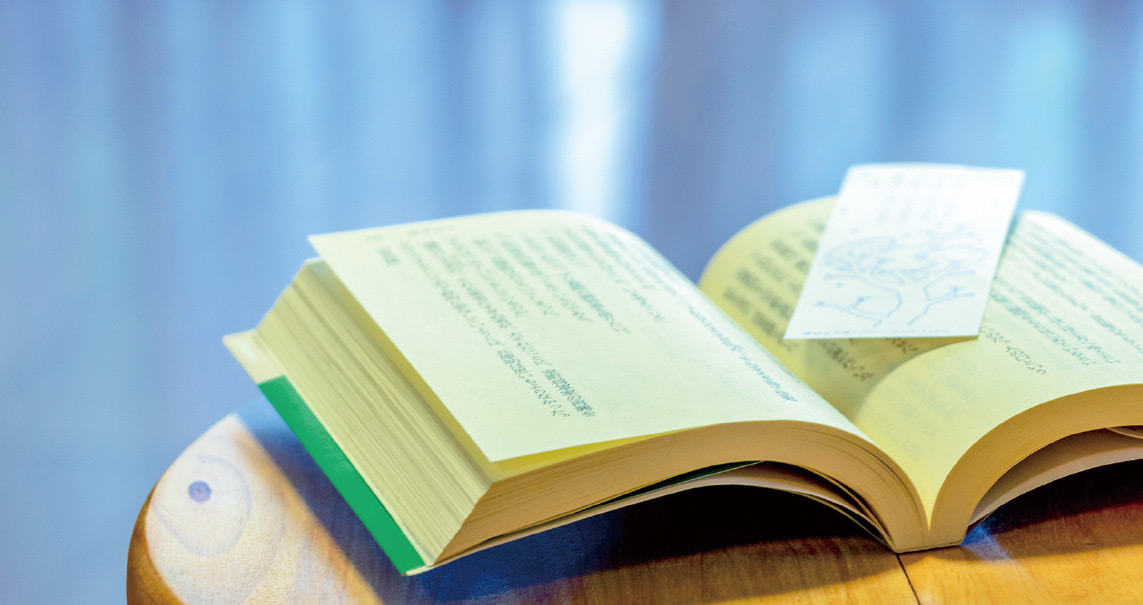
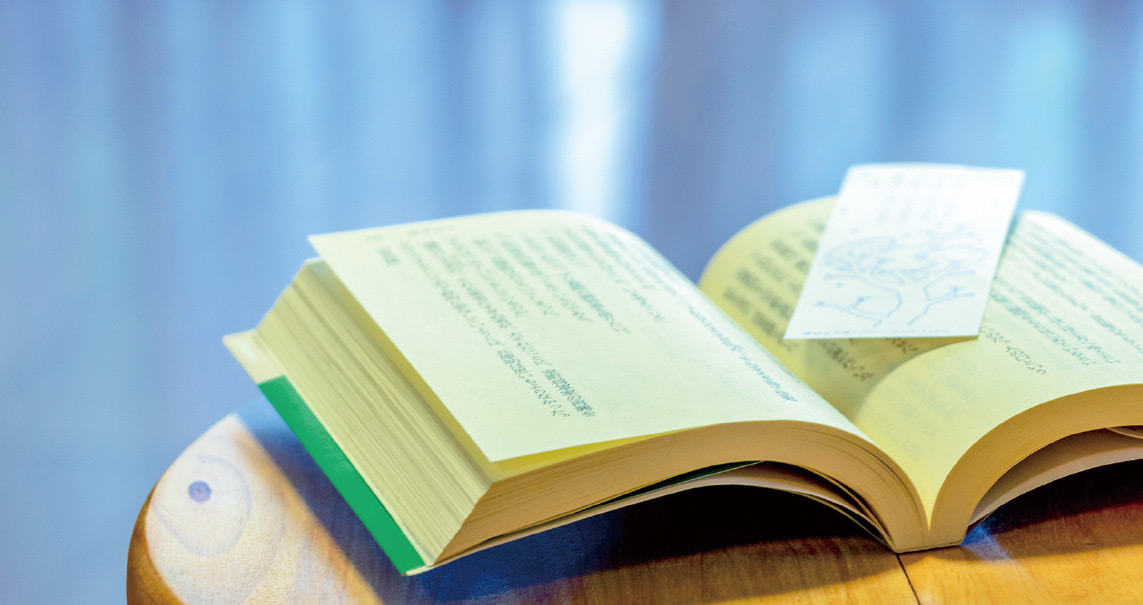
学びの特長
-
講義、演習、研究を通して文学作品を読み解いていく。
1・2年次は上代から近現代までの作品を広く学び、
3年次からはゼミナールを中心に専門領域を深めます。 -
小説・シナリオ・俳句等の創作を学び、日本文学への理解を深める。
3年次からは俳句の実作を学ぶ科目も履修できます。
小説・シナリオに加え、韻文創作を学べるのが大きな特長です。 -
国文学を広く、深く学ぶ。
上代から近現代まで、さまざまな視点や方法で研究する、多彩な授業を展開しています。
先生が語る! 国文学の面白さ
小説でも映画でもマンガでも、
自分の「好き」を大切にしてほしい。
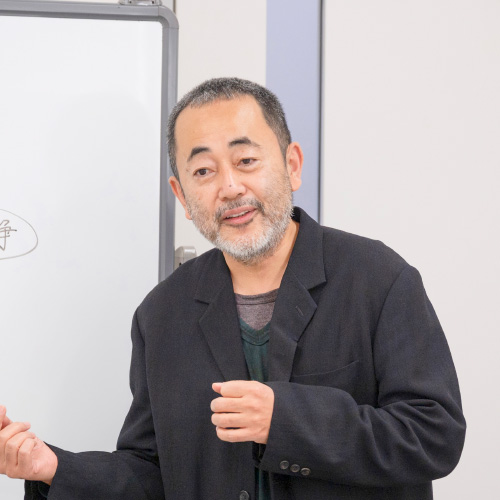
新たな読み方での読書体験が開く、
今までとは異なる小説世界。
日本近代文学について研究
五井 信 教授
普段から受講生に言っているのは、「作家が何を言いたいのか」は、小説を読み解くための一つの方法に過ぎないということ。文学は、もっと自由に読んでいいのです。私の授業では「小説とは何か」というところから学び始め、精神分析やフェミニズムなど、さまざまな他領域の成果を導入することで、テクストとしての「今までとは違う読み」を目指します。その結果として異なる小説世界が開けたときの快感は、一度体験するとなかなか忘れられないと思います。
国文学専攻の推しの授業!
-
ゼミナールⅠA・B
私達が現在読むことのできる最古の和歌集『万葉集』を読み、当時の人々の歌を中心とした文芸意識のありようを探る。そこから、学生自身が各自の研究テーマと研究方法を発見していくことを目的とする。
-
プレゼミ
(国文学・中世)『徒然草』を精読し、現在残っている中で最古の写本である室町時代の正徹本と、江戸時代から多くの人に読まれてきた写本・版本の本文を読み比べる。入念な調査を基に、読み続けられてきた作品の魅力を理解する。
-
源氏物語特殊研究
A・B源氏物語や平安時代について基礎的知識を修得する。『源氏物語』の幻巻、匂宮巻を対象に、くずし字を読み、理解し、校訂本文を作る作業を経験し、古文に親しむことを目指す。
-
ゼミナールⅡA・B
近代・現代小説の研究として、『神聖喜劇』を精読して作品の現在性に迫り、論文に考察をまとめる。批判意識を研ぎ澄ませ、幅広い読書と議論から思考を深めて歴史的に精確で、創造的な作品理解を目指す。
-
近代文学研究入門
短編小説を主な対象に、日本近代文学研究のための基本的な手続きを学ぶ。様々な研究方法を紹介し、具体的に作品を取り上げて分析を行い、理論を用いた考察を目指す。小説から多様な意味を発見する。
-
創作実践①A・B
(小説・エッセイ)主に小説の鑑賞と創作を通じて、文学とは何かについて考察する。小説の書評POPの作成や小説の共同制作に取り組む。世界観のこもった文章を発表し、授業内で朗読を行なう。