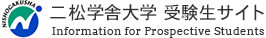思想・芸能文化を
歴史的に考察する。
思想・文化史
専攻

専攻

学びの特長
-
東洋の思想から人間の生き方を考察する。
本学の伝統を活かした思想史の研究により、時代にとらわれない思考を学びます。
-
伝統芸能・日本文化を深く学ぶ。
歌舞伎や落語などの近世芸能史を中心に、現代にも息づく芸能に触れます。
-
地理学、民俗学など多様な研究分野に触れる。
特定の分野を深めるゼミ以外にもさまざまな関連授業が展開され豊かな人間性と洞察力を育みます。
先生が語る! 思想・文化史の面白さ
歴史とは何か。人間とは何か。
大いなる命題に挑戦します。
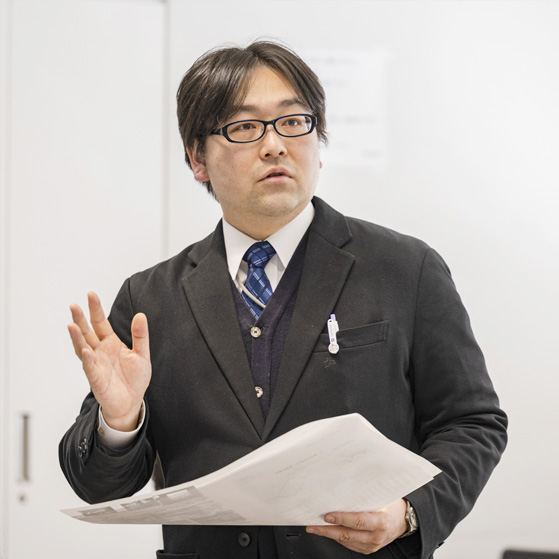
過去のテクストから思想や想いを
丁寧に読み解く力を得て、
他者への想像力を身に付けてほしい。
人文地理学、近代日本の地理思想とキリスト教思想を研究
麻生 将 講師
私の授業では、私たちが日々生活しているこの空間を近代の人々はどのように捉え、想いを巡らせながら生きていたのか、近代の人々が見た景色は現代の私たちにはどのように映るのか、を当時の人々が書き残した書物や記録、日記、手紙などを手掛かりに理解していきます。昔の人々が書き残した文章から書き手の思想や想いを丁寧に読み解く力を得て、そこから他者への想像力を身に付けてほしいと思います。歴史文化学科では「歴史とは何か」という問いから出発し、最終的には「人間とは何か」という大いなる命題に挑戦していきます。この問いと向き合い、考えることは社会の現状と将来を考えることにつながります。歴史を通してこそ学べるもの、得られるものを見つけていきましょう!
思想・文化史専攻の推しの授業!
-
芸能・演劇特殊研究
落語や歌舞伎など江戸期の代表的な芸能について、当時の文献資料を読みつつ、現在演じられている伝統芸能を鑑賞して日本の文化に親しむことを目的とする。
-
人文地理学研究
都市に注目しながら、現代世界・社会の諸問題への地理学の向き合い方を考える。地理学の主要な研究成果を通じ、地域や場所を超えた有機的なつながりに注目し、複数の空間スケールからのアプローチを考察する。
-
芸能文化史講読
江戸期の歌舞伎に関係する文献資料を講読する。歌舞伎の興行制度や慣習について知り、絵画資料も参照する。
-
日本思想史研究①
近世以前の日本の地理思想やその背景の歴史的事象を通して、人々の地理的認識や世界観の変遷を理解する。地図や絵図、屏風絵、浮世絵、名所案内記などの視覚的な史料から各時代の思想を読み解く。
-
日本文学と思想A
藤原俊成の歌論『古来風体抄』を読み、鎌倉時代までの和歌の歴史を学ぶ。また、仏教思想を踏まえた歌論についても理解する。古代和歌の通史を学び、日本の文学活動と日本思想との関係について考察する。
-
歴史文化
フィールドワーク内村鑑三と弟子たちが残した手書き原稿、手紙、日記、当時の写真などを整理し、データベースを作成する。また、適宜史料の修復も行う。