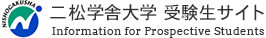大きな視座からこれまでの
世界の動きを学ぶ。
欧米・
アジア史専攻

アジア史専攻

学びの特長
-
3領域の知識を得る。
歴史・文化・交流の領域から、東洋・西洋の歴史や文化に関する基本的な知識を身に付けます。
-
複眼的な視点を持つ。
日本と世界の動きと結びつきを歴史から学び、多様な文化と価値観への理解を求め、多角的な思考力を持つことで、より幅広く考えます。
-
グローバルな対応能力を身に付ける。
分析力・論理力・説得力を涵養することで、国際化する社会で主体的に活躍します。
先生が語る! 欧米・アジア史の面白さ
Carpe diem(その日その時を大切に)
異文化(他者)に開かれた窓を増やしてください。

グローバル化社会では、
欧米・アジア、そして歴史世界という
異文化(他者)への理解が不可欠。
西洋史について研究
野村 啓介 教授
フランス第二帝政の政治史研究を皮切りに、同時代のフランス地域史、ワイン文化史、日仏外交史などの研究に取り組んできました。研究経験を欧米・アジア史専攻での教育実践に活かすのはもちろんですが、西洋史という角度から異文化理解を深めてもらうことに留意しています。日本語への翻訳・通訳など言語の解釈問題も重視していますので、ぜひとも外国語学修にも力を入れていただきたいです。われわれにとって欧米やアジアが「異文化」という他者であることはいうまでもありませんが、過去という歴史世界もまた、現代人にとっては異文化(他者)です。グローバル化時代には、こうした異文化(他者)の理解が不可欠です。欧米・アジア史専攻では、欧米とアジアの歴史学修を通じて歴史的考察力を養い、そうした理解力を身に付けてほしいと思います。
欧米・アジア史専攻の推しの授業!
-
文化交流史
イエズス会宣教師の来航から幕末開国期に至る欧米諸国のアジア政策を踏まえつつ、欧米人の対日理解のあり方がどのように展開したのかを考察する。
-
ヨーロッパ史特講
ローマ帝国滅亡以降のヨーロッパにおける諸帝国の興亡と皇帝理念の変容、および19世紀にナショナリズムが支配的になっていく史的展開を考察する。
-
東アジア史学講読①
司馬遷の『史記』から、「項羽」を選んで読む。本文以外に語釈、書き下し文、現代語訳が付いており、課題を通して学修内容を確認。中国の歴史書の体裁や内容の特徴を理解するとともに、漢文読解力を養う。
-
東アジア史学講読②
司馬遷の『史記』から、「刺客」を選んで読む。本文以外に語釈、書き下し文、現代語訳が付いており、課題を通して学修内容を確認。中国の歴史書の体裁や内容の特徴を理解するとともに、漢文読解力を養う。
-
欧米文化史特殊研究
ヨーロッパ外交体制がいかにしてアジア(漢字文化圏)に食い込んでいったかという歴史の展開を、条約体制や旧外交から新外交への転換といった観点から検討する。
-
中国文化史特殊研究
日中政治ではなく、日中文化関係を考える。明治時代以前の日中文化関係の確認、過渡期の日中文化関係の明確化、日清戦争後の日中文化関係のまとめを行う。各テーマの先行研究など、資料を読み解く。