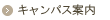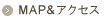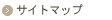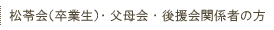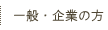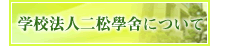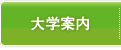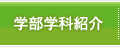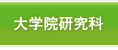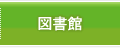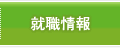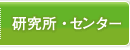平成22年度二松學舍大学公開講座
平成22年度二松學舍大学公開講座
平成22年度公開講座は、以下のとおり実施いたしました
九段キャンパス公開講座
【 教養講座 】 定員150名、資料代1,000円(全5回分)
| 日 程 | 時 間 | 題 目 | 講 師 |
| 8月2日(月) | 10:00~12:00 | 投票と選挙の経済学 | 岩田 幸訓 専任講師 |
| 8月3日(火) | 山上 憶良 | 土佐 秀里 准教授 | |
| 8月4日(水) | 盆行事と先祖祭祀 | 谷口 貢 教授 | |
| 8月5日(木) | 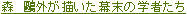 |
町 泉寿郎 准教授 | |
| 8月6日(金) | 『源氏物語』の享受 ―謡曲に現出した『源氏物語』 | 原 由来恵 准教授 |
※4回以上受講された方には修了証(無料)を授与いたします。
【 書道講座 】 定員80名、資料代1,000円(全5回分)
| 日 程 | 時 間 | 題 目 | 講 師 |
| 8月2日(月) | 13:00~16:00 | 書かなの美の抽出と結集 (1) 連綿美 | 福島 一浩 特別招聘教授 |
| 8月3日(火) | 漢字の歴史 ―木簡から石碑― (※書作はありません) |
髙澤 浩一 准教授 | |
| 8月4日(水) | 蘇軾・前赤壁賦(小楷)他 ―実技と鑑賞― | 難波 清邱 名誉教授 | |
| 8月5日(木) | 金文の新資料(解釈と鑑賞) (※書作はありません) |
浦野 黛岳 講師 | |
| 8月6日(金) | 竹簡」を科学する ―「郭店楚簡」筆意の研究― | 内田 征志 講師 |
※4回以上受講された方には修了証(無料)を授与いたします。
柏キャンパス公開講座
【 教養講座 】 定員150名、資料代1,000円(全5回分)
| 日 程 | 時 間 | 題 目 | 講 師 |
| 9月6日(月) | 10:00~12:00 | メディアとしての写真 ―その透明性、時間性 | 松本健太郎 専任講師 |
| 9月7日(火) | ネット社会における生き方を学ぼう! | 須藤 和敬 専任講師 | |
| 9月8日(水) | エゴグラムによる性格理解入門 | 改田 明子 教授 | |
| 9月9日(木) | 韓流ブーム(歴史ドラマ)と歴史の真実 |
小川 晴久 教授 | |
| 9月10日(金) | 同盟の距離感: 戦後のアメリカと日本・イギリス | 水本 義彦 専任講師 |
※4回以上受講された方には修了証(無料)を授与いたします。
【 書道講座 】 定員100名、資料代1,000円(全5回分)
| 日 程 | 時 間 | 題 目 | 講 師 |
| 9月6日(月) | 13:00~16:00 | 般若心経」を篆書で書いてみよう | 石野 黎峰 講師 |
| 9月7日(火) | 遷都1300年 奈良時代の書 (※書作はありません) |
杉浦 華桂 講師 | |
| 9月8日(水) | 「漢字かな交じりの書」を書こう | 寺内 眞道 講師 | |
| 9月9日(木) | 文人的書を目指して(竹の巻) | 伊藤 忠綱 講師 | |
| 9月10日(金) | 革新書道の第一 蘇軾の書の魅力 | 今川 佳香 講師 |
※4回以上受講された方には修了証(無料)を授与いたします。
お問い合わせ先
二松學舍大学 広報課
〒102-8336 東京都千代田区三番町6-16
電話 03-3261-1292
〒102-8336 東京都千代田区三番町6-16
電話 03-3261-1292
E-mail 

会場までのアクセス方法
※お車でのご来場はご遠慮ください。
講義内容、講師のプロフィール
8月 九段キャンパス教養講座
8/2(月) 投票と選挙の経済学
大は国会の議員の選挙から、小は家庭の献立の決定まで、意見や好みの異なる複数の人が集団として1つの意思決定をしなければならない場合があります。この講義では、どんな方法で集団的に意思決定をしたらよいのかという問題について経済学的な考え方を紹介します。講義は若干難解な印象を持つかもしれません。しかし、最後まで聴講してくださった方には民主的な意思決定の仕組みにはさまざまな困難が含まれていることが明らかとなるでしょう。
岩田 幸訓(いわた ゆきのり)専任講師
【 プロフィール 】
最終学歴:一橋大学大学院経済学研究科経済理論・経済統計専攻博士後期課程修了、
博士(経済学)(一橋大学)
専門分野は厚生経済学、社会的選択理論。最近は選択機会の内在的価値に関して理論的な研究を行っている。
【 主な著作・論文等 】
代表的な論文:
"A variant of non-consequentialism and its characterization", Mathematical Social Sciences 53 (2007) 284-295.
"Consequences,opportunities, and Arrovian impossibility theorems with consequentialist domains", Social Choice and Welfare 32 (2009) 513-531.
最終学歴:一橋大学大学院経済学研究科経済理論・経済統計専攻博士後期課程修了、
博士(経済学)(一橋大学)
専門分野は厚生経済学、社会的選択理論。最近は選択機会の内在的価値に関して理論的な研究を行っている。
【 主な著作・論文等 】
代表的な論文:
"A variant of non-consequentialism and its characterization", Mathematical Social Sciences 53 (2007) 284-295.
"Consequences,opportunities, and Arrovian impossibility theorems with consequentialist domains", Social Choice and Welfare 32 (2009) 513-531.
8/3(火) 山上憶良
万葉歌人山上憶良は、子供好きの「マイホームパパ」の如くに世間では理解されている。だがそれは本当だろうか。たしかに憶良には子供を詠んだ歌が多い。というより、他の歌人は誰も憶良のようには子供を詠もうとはしなかった。子供が歌の主題になるとは誰も思わなかったのだ。恋の歌を詠まず、子供という「特殊」な題材を敢えて選んだ憶良は、何を考えていたのか。いや、そもそも憶良とはどのような人であったのか。そんなことを少々確かめてみることにしたい。
土佐 秀里(とさ ひでさと)准教授
【 プロフィール 】
1966年千葉県市川市に生まれる。早稲田大学教育学部卒業。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。早稲田実業学校教諭・秀明大学専任講師などを経て現職。専門は万葉集を中心とする上代文学。上代文学会常任理事。早稲田大学文学部講師・朝日カルチャーセンター講師を兼任する。第36回早稲田大学国文学会賞(窪田空穂賞)受賞。
【 主な著作・論文等 】
1966年千葉県市川市に生まれる。早稲田大学教育学部卒業。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程満期退学。早稲田実業学校教諭・秀明大学専任講師などを経て現職。専門は万葉集を中心とする上代文学。上代文学会常任理事。早稲田大学文学部講師・朝日カルチャーセンター講師を兼任する。第36回早稲田大学国文学会賞(窪田空穂賞)受賞。
【 主な著作・論文等 】
| 共編著: | 『黄金の言葉 和歌篇』(勉誠出版・2010年)。 |
| 論 文: | 「藤原麻呂贈歌三首の趣向」(『国文学研究』145) 「東歌と仮名表記」(『古代研究』39)、 「『或本』と『一書』」(『文芸と批評』10-6) 「真間の手児奈と末の珠名」(『二松学舎大学論集』52)など。 |
8/4(水) 盆行事と先祖祭祀
近年、お盆の行事はしだいに簡略化される傾向にあるが、それでもなお家族や親戚縁者が集い交流を深める機会であり、お正月とともに年中行事の双璧をなす行事といえる。日本各地の「精霊迎え(迎え盆)」と「精霊送り(送り盆)」の具体的な姿を紹介しながら、盆行事はどのように営まれ、どんな意味があるのかについて、亡き人の供養と先祖祭祀との関連でみていくことにしたい。
谷口 貢(たにぐち みつぎ)教授
【 プロフィール 】
最終学歴 :駒澤大学大学院人文科学研究科博士課程
専門分野は民俗学。最近の研究課題は、日本社会の民俗文化の変容過程を、地域調査に基づいて解明する研究に取り組む。また民俗学の成立前史の研究にも関心をもつ。
【 主な著作・論文等 】
『民俗文化の探究』(共編著)、『日本の民俗信仰』(共編著)、『民俗学講義-生活文化へのアプローチ-』(共編著)、『現代民俗学入門』(共編著)、『民俗学の地平』(共著)、『シャーマニズム研究とその周辺』(共著)、『同郷者集団の民俗学的研究』(共著)等。
最終学歴 :駒澤大学大学院人文科学研究科博士課程
専門分野は民俗学。最近の研究課題は、日本社会の民俗文化の変容過程を、地域調査に基づいて解明する研究に取り組む。また民俗学の成立前史の研究にも関心をもつ。
【 主な著作・論文等 】
『民俗文化の探究』(共編著)、『日本の民俗信仰』(共編著)、『民俗学講義-生活文化へのアプローチ-』(共編著)、『現代民俗学入門』(共編著)、『民俗学の地平』(共著)、『シャーマニズム研究とその周辺』(共著)、『同郷者集団の民俗学的研究』(共著)等。
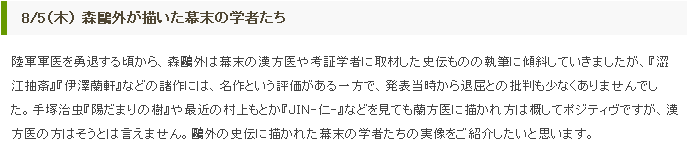
町 泉寿郎(まち せんじゅろう)准教授
【 プロフィール 】
最終学歴 :二松学舎大学大学院文学研究科博士後期課程国文学専攻
専門分野は日本漢文学(江戸期の学芸史―儒学と医学を中心に)。
最近の研究課題は
(1)曲直瀬流医学と医書―古活字本
(2)医学館を中心とした考証学―明学から清学へ
(3)近代化過程における漢字・漢文・漢学
所属学会: 日本近世文学会・日本思想史学会、日本中国学会・東方学会、日本医史学会・日本東洋医学会。
【 主な著作・論文等 】
最終学歴 :二松学舎大学大学院文学研究科博士後期課程国文学専攻
専門分野は日本漢文学(江戸期の学芸史―儒学と医学を中心に)。
最近の研究課題は
(1)曲直瀬流医学と医書―古活字本
(2)医学館を中心とした考証学―明学から清学へ
(3)近代化過程における漢字・漢文・漢学
所属学会: 日本近世文学会・日本思想史学会、日本中国学会・東方学会、日本医史学会・日本東洋医学会。
【 主な著作・論文等 】
| 主要論文: | 「新資料による前島密の漢字廃止建白書の再検討」『文学・語学』、 「閲微草堂筆記を読んだ考証学者たち」『江戸文学』、 「医学館の軌跡」『杏雨』、 「多紀元簡失脚の背景」『日本医史学雑誌』、 「小島宝素の京都訪書行」『東方学』、 「山脇東洋と徂徠学派」『日本中国学会報』、 「三島中洲と東京大学古典講習科の人々」 『三島中洲の学芸とその生涯』 |
8/6(金) 『源氏物語』の享受 ―謡曲に現出した『源氏物語』
『源氏物語』は、約千年の時を越えて今日まで読み継がれてきました。その過程にはその時々によっての『源氏物語』の受け入れ方や楽しみ方がありました。
今回は、能の台本となる「謡曲」に見られる『源氏物語』をとりあげ、『源氏物語』がどのように当時の人々に受け入れられ、親しまれていたのかを考えていきたいと思います。
また謡曲「葵上」をとりあげて、その詞章の面白さも体感していただきます。 。
今回は、能の台本となる「謡曲」に見られる『源氏物語』をとりあげ、『源氏物語』がどのように当時の人々に受け入れられ、親しまれていたのかを考えていきたいと思います。
また謡曲「葵上」をとりあげて、その詞章の面白さも体感していただきます。 。
原 由来恵(はら ゆきえ)准教授
【 プロフィール 】
最終学歴 :二松学舎大学大学院文学研究科博士後期課程国文学専攻、博士(文学)(二松学舎大学)
専門分野は、平安朝散文学伝承論。最近の研究課題は、『枕草子』。今まで解析されずにきた、地名類聚章段の解釈から、作者の執筆意識と作品の文学性を抽出し、作品の特質解明を目指している。また中京大学文化研究所準所員として児童文学と教育の研究も行っている。
所属学会:中古文学会・全国大学国語国文学会・日本文学風土学会・芸能学会。各学会において口頭発表・機関誌への論文掲載等の活動をしている。
【 主な著作・論文等 】
『枕草子大事典』(勉誠出版)に執筆。『古代中世文学論考』(新典社)へ論文を複数掲載など。
その他文化貢献として、(1)狂言会の舞台の解説、舞台配布資料「狂言豆知識シリーズ」執筆。
(2)小・中・高等学校における特別活動「狂言鑑賞」の解説。
最終学歴 :二松学舎大学大学院文学研究科博士後期課程国文学専攻、博士(文学)(二松学舎大学)
専門分野は、平安朝散文学伝承論。最近の研究課題は、『枕草子』。今まで解析されずにきた、地名類聚章段の解釈から、作者の執筆意識と作品の文学性を抽出し、作品の特質解明を目指している。また中京大学文化研究所準所員として児童文学と教育の研究も行っている。
所属学会:中古文学会・全国大学国語国文学会・日本文学風土学会・芸能学会。各学会において口頭発表・機関誌への論文掲載等の活動をしている。
【 主な著作・論文等 】
『枕草子大事典』(勉誠出版)に執筆。『古代中世文学論考』(新典社)へ論文を複数掲載など。
その他文化貢献として、(1)狂言会の舞台の解説、舞台配布資料「狂言豆知識シリーズ」執筆。
(2)小・中・高等学校における特別活動「狂言鑑賞」の解説。
8月 九段キャンパス書道講座
8/2(月) かなの美の抽出と結集(1)連綿美
かなの美を味わうには連綿美の分析が不可欠です。かな消息そして名品の数々、今回は高野切第一種、本阿弥切、曼殊院本古今集、針切、寸松庵色紙、伝西行系のかなを取り上げ各場面から連綿の方法と効果を分析し味わいます。又、抽出した美をどのように結集し現代のかなとして新たな美を創出してゆくのか、我々の使命を考えます。後半は扱った連綿(文字群)の中から各自選択し半紙に臨書、福島がワンポイントで助言いたします。
【当日持参するもの】
書道用具一式。
半紙は「かな専用」に限ります。にじみの出ない紙が適しています。
【当日持参するもの】
書道用具一式。
半紙は「かな専用」に限ります。にじみの出ない紙が適しています。
福島 一浩(ふくしま かずひろ)特別招聘教授
【 プロフィール 】
東京都出身。明治大学商学部商学科卒業。現在、二松學舍大学特別招聘教授。日展会友、読売書法会理事、社団法人全日本書道教育協会理事長などを務める。日本芸術院会員日比野光鳳に師事。専門分野は日本書道史、書道実技(かな)。最近の研究課題は、空海、佐理、光悦、良寛を通しての日本の書の質感、また、寸松庵色紙と継色紙から、かな書における時間と空間。
【 主な著作・論文等 】
「書道かな」<(社)全書教>、「寸松庵色紙」、「継色紙」、「書の古典とかなの書・思索と実践」、「日比野五鳳と仮名の実像」など多数。かなの書研究会主宰。個展<平成17年・銀座書廊>。日展、読売書法展、書教展、葛飾現代書展などに出品。
東京都出身。明治大学商学部商学科卒業。現在、二松學舍大学特別招聘教授。日展会友、読売書法会理事、社団法人全日本書道教育協会理事長などを務める。日本芸術院会員日比野光鳳に師事。専門分野は日本書道史、書道実技(かな)。最近の研究課題は、空海、佐理、光悦、良寛を通しての日本の書の質感、また、寸松庵色紙と継色紙から、かな書における時間と空間。
【 主な著作・論文等 】
「書道かな」<(社)全書教>、「寸松庵色紙」、「継色紙」、「書の古典とかなの書・思索と実践」、「日比野五鳳と仮名の実像」など多数。かなの書研究会主宰。個展<平成17年・銀座書廊>。日展、読売書法展、書教展、葛飾現代書展などに出品。
8/3(火) 漢字の歴史 ―木簡から石碑―
甲骨文字の誕生から青銅器の金文までを昨夏の講義ではお話ししました。そこで今夏は、木簡から紙の誕生、次いで石刻にいたる漢字文化の変遷についてをテーマとしてお話ししましょう。
近年の中国では、おびただしい漢字文化の遺産が出土し、既説の書道史の書き直しが余儀なくされています。私が中国を旅し、現地で取材した新情報を交えてお話いたします。(講義のみ) 。
近年の中国では、おびただしい漢字文化の遺産が出土し、既説の書道史の書き直しが余儀なくされています。私が中国を旅し、現地で取材した新情報を交えてお話いたします。(講義のみ) 。
髙澤 浩一(たかざわ こういち)准教授
【 プロフィール 】
二松學舍大学大学院文学研究科中国学専攻修士課程。専門分野は中国書道史、書道実技。最近の研究課題は、中国漢代の公用書体であった隷書が、いかなる経緯のもとに草体、行体へと変化していったのか、といった漢字書の変遷史。また、中国に書の歴史文化を訪ねての旅を重ねています。書学書道史学会に所属、俟清社会員。
【 主な著作・論文等 】
「王文治の書法鑑賞観『望岳室古文字書法論集』」、「何君閣道摩崖の書『書学書道史研究』」、「行書発生期試探『全日本高等学校書道教育研究論文』」等、多数。
二松學舍大学大学院文学研究科中国学専攻修士課程。専門分野は中国書道史、書道実技。最近の研究課題は、中国漢代の公用書体であった隷書が、いかなる経緯のもとに草体、行体へと変化していったのか、といった漢字書の変遷史。また、中国に書の歴史文化を訪ねての旅を重ねています。書学書道史学会に所属、俟清社会員。
【 主な著作・論文等 】
「王文治の書法鑑賞観『望岳室古文字書法論集』」、「何君閣道摩崖の書『書学書道史研究』」、「行書発生期試探『全日本高等学校書道教育研究論文』」等、多数。
8/4(水) 蘇軾・前赤壁賦(小楷)他 ―実技と鑑賞―
* 宋代の書法と蘇・黄・米の三大家。
* 蘇軾の書法と前赤壁賦。内容と小楷について。小楷の意義と表現。
* 寒食帖と黄庭堅跋の鑑賞。
* 半紙を中心とする臨書とその展開。
* 創作への方向。
【当日持参するもの】
書道用具一式。色紙。
* 蘇軾の書法と前赤壁賦。内容と小楷について。小楷の意義と表現。
* 寒食帖と黄庭堅跋の鑑賞。
* 半紙を中心とする臨書とその展開。
* 創作への方向。
【当日持参するもの】
書道用具一式。色紙。
難波 清邱(なんば せいきゅう)名誉教授
【 プロフィール 】
新潟県出身。新潟大学芸能学科書道科卒業。専門分野は、碑版法帖・文房四宝・写経研究、漢字かな交り書と東洋蘭。二松学舎大学名誉教授。各種書道団体、日本・中国蘭、日中文化交流など。書法研究・書峯主宰。
【 主な著作・論文等 】
『新和禄教程・書道史講座 写経講座・中國三千年原拓大観・安徽省古代文房至宝』(日本書道教育学会)。国宝・法隆寺伝来細字法華経、重文・四天王寺同経復元浄写。「六朝墓誌銘」「文房四宝」「書道理論」「書教育」「書と東洋蘭」他、多数。
新潟県出身。新潟大学芸能学科書道科卒業。専門分野は、碑版法帖・文房四宝・写経研究、漢字かな交り書と東洋蘭。二松学舎大学名誉教授。各種書道団体、日本・中国蘭、日中文化交流など。書法研究・書峯主宰。
【 主な著作・論文等 】
『新和禄教程・書道史講座 写経講座・中國三千年原拓大観・安徽省古代文房至宝』(日本書道教育学会)。国宝・法隆寺伝来細字法華経、重文・四天王寺同経復元浄写。「六朝墓誌銘」「文房四宝」「書道理論」「書教育」「書と東洋蘭」他、多数。
8/5(木) 金文の新資料(解釈と鑑賞)
書の作品制作において殷周時代の金文を用いた作品が多く見られる時代となっている。この講義では、新資料の中から書として優れたものを中心として紹介する。映像による鑑賞を通して、金文の持つ魅力を感じ取っていただきたい。文字についての説明に加えて、書作への応用のヒントにも触れる考えである。(講義のみ)
浦野 黛岳(うらの たいがく)講師
【 プロフィール 】
新潟大学教育学部芸能科書道科卒業。専門は中国古代文字学、書道教育。
最近は、近年出土殷周金文の考釈を研究課題としている。
【 主な著作・論文等 】
『書写書道教育史資料』(全3巻)、『書学体系碑法帖篇1甲骨文』、『歴代名家臨書集成』(全7冊)、『近出殷周金文集成』(第1集~第5集)、『ヴィジュアル書芸術全集』(第1巻)、『望学室古文字書法論集』、「戦国・秦・青川木牘の文字」「漢碑的分類与書風」「甲骨文による殷代金文の時期推定」「殷墟出土金文と甲骨文における共通語彙の考察」「西周初期金文の書風の形成」等、多数。
新潟大学教育学部芸能科書道科卒業。専門は中国古代文字学、書道教育。
最近は、近年出土殷周金文の考釈を研究課題としている。
【 主な著作・論文等 】
『書写書道教育史資料』(全3巻)、『書学体系碑法帖篇1甲骨文』、『歴代名家臨書集成』(全7冊)、『近出殷周金文集成』(第1集~第5集)、『ヴィジュアル書芸術全集』(第1巻)、『望学室古文字書法論集』、「戦国・秦・青川木牘の文字」「漢碑的分類与書風」「甲骨文による殷代金文の時期推定」「殷墟出土金文と甲骨文における共通語彙の考察」「西周初期金文の書風の形成」等、多数。
8/6(金) 「竹簡」を科学する ―「郭店楚簡」筆意の研究―
近年、出土した「郭店楚簡」。さまざまな物議をかもし、多方面での研究が盛んになっている。この講座では「郭店楚簡老子甲本」を竹片に原寸臨書し、更には半紙・条幅へ展開。肉筆から確認できる筆意を追求し、「楚国文字」を楽しむ。初心者の方も大歓迎。筆の持ち方、姿勢等も丁寧にご指導いたします。
【当日持参するもの】
書道用具一式(固形墨・小筆・中筆・半紙・条幅を含む)。
※当日受付にて、竹片2枚(100円)を販売いたします。
【当日持参するもの】
書道用具一式(固形墨・小筆・中筆・半紙・条幅を含む)。
※当日受付にて、竹片2枚(100円)を販売いたします。
内田 征志(うちだ まさし)講師
【 プロフィール 】
大東文化大学卒。二松學舍大学講師。国立学校法人東京工業大学附属科学技術高等学校講師。松坂屋カルチャー講師。第44回中日以文展文部科学大臣賞受賞。書宗院参与理事。研心書院理事。中日以文展審査員。墨華書道展審査員。靜藍社主宰。
【 主な著作・論文等 】
「書道Ⅱ」共著・大阪書籍。「書道Ⅱ」指導編 共著・教育出版。「何君閣道碑の研究・新出土文物の指導法」教育出版。「書写指導の可能性を探る」共著・光村図書。「墨華」「張猛龍碑の研究」、「墓誌銘を科学する」、「十七帖三井本断筆の研究」、「孟法師碑の筆意をさぐる」、墨華書道研究会。「龍門石窟報告記」、「良寛の里を訪ねて」書宗院研究会報。「日本語がきれいに見えるボールペン字練習帳」共著・パッチワーク通信社。等
大東文化大学卒。二松學舍大学講師。国立学校法人東京工業大学附属科学技術高等学校講師。松坂屋カルチャー講師。第44回中日以文展文部科学大臣賞受賞。書宗院参与理事。研心書院理事。中日以文展審査員。墨華書道展審査員。靜藍社主宰。
【 主な著作・論文等 】
「書道Ⅱ」共著・大阪書籍。「書道Ⅱ」指導編 共著・教育出版。「何君閣道碑の研究・新出土文物の指導法」教育出版。「書写指導の可能性を探る」共著・光村図書。「墨華」「張猛龍碑の研究」、「墓誌銘を科学する」、「十七帖三井本断筆の研究」、「孟法師碑の筆意をさぐる」、墨華書道研究会。「龍門石窟報告記」、「良寛の里を訪ねて」書宗院研究会報。「日本語がきれいに見えるボールペン字練習帳」共著・パッチワーク通信社。等
9月 柏キャンパス教養講座
9/6(月) メディアとしての写真――その透明性、時間性
本講義では、記号学やメディア論など複数の分野における理論的知見を参照しながら、写真というメディアの特性を、おもに「透明性」と「時間性」に着目しながら考察していく。写真とは被写体の姿をあるがままに映像化する透明な表現形式であり、また、時間を超えたその映像の保存を可能にするテクノロジーでもある。それらの表象特性を把握したうえで、19世紀における写真の発明が人類にもたらした衝撃を照明していく。
松本 健太郎(まつもと けんたろう)専任講師
【 プロフィール 】
最終学歴 :京都大学大学院人間・環境学研究科文化・地域環境学専攻博士課程、 博士(人間・環境学)
【 主な著作・論文等 】
最終学歴 :京都大学大学院人間・環境学研究科文化・地域環境学専攻博士課程、 博士(人間・環境学)
【 主な著作・論文等 】
| 著書: | 『知のリテラシー 文化』(共著・ナカニシヤ出版)、 『『明るい部屋』の秘密―ロラン・バルトと写真の彼方へ』(共著・青弓社) 『よくわかる異文化コミュニケーション』(共著・ミネルヴァ書房) 『メディア・コミュニケーション論』(共編著・ナカニシヤ出版・近刊予定) |
| 論文: | 「言語活動の終焉に向かって―ロラン・バルトの記号論的テクストにおける
視覚関係の変遷」 (『映像学』第69号、日本映像学会)、 「ロラン・バルトの写真論における言語批判的要素について」 (『記号学研究』第23号、日本記号学会)、 「記号論とメディア論の架橋を目指して―『言語』と『装置』の媒介作用・ 延長作用に関する 一考察」(博士論文、京都大学大学院人間・環境学研究科) |
9/7(火) ネット社会における生き方を学ぼう!
わずか20年足らずの間に世界を席巻したインターネット。その直接的・間接的利用を通じて、今では我々の社会や生活に欠かせない技術のひとつとなっている。
ではそもそもインターネットとは何なのか。よく耳にするネット社会・デジタル社会とはどういった社会のことだろうか。
本講義では、インターネットの利点や欠点を含めて、その発展の歴史と、予測される未来像について解説する。
ではそもそもインターネットとは何なのか。よく耳にするネット社会・デジタル社会とはどういった社会のことだろうか。
本講義では、インターネットの利点や欠点を含めて、その発展の歴史と、予測される未来像について解説する。
須藤 和敬(すどう かずたか)専任講師
【 プロフィール 】
最終学歴:神戸大学大学院博士後期課程 自然科学研究科 構造科学専攻。博士(理学)(神戸大学)
専門分野は情報科学、素粒子・原子核物理学。最近の研究課題は、ハドロンのスピン構造・分光・生成機構の研究。情報リテラシー。量子情報の研究にも興味をもっている。 所属学会:日本物理学会
【 主な著作・論文等 】
最近の代表的な論文:
“Exotic nuclei with open heavy flavor mesons”, Physical Review D80, 034008 (2009). “Novel two-to-three hard hadronic processes and possible studies of generalized parton distributions at hadron facilities”, Physical Review D80, 074003 (2009).
“Proposal for exotic-hadron search by fragmentation functions”, Physical Review D77, 017504 (2008).
“New heavy-light mesons Q anti-q”, Progress of Theoretical Physics 117, 1077 (2007). “Determination of fragmentation functions and their uncertainties”, Physical Review D75, 094009 (2007).
最終学歴:神戸大学大学院博士後期課程 自然科学研究科 構造科学専攻。博士(理学)(神戸大学)
専門分野は情報科学、素粒子・原子核物理学。最近の研究課題は、ハドロンのスピン構造・分光・生成機構の研究。情報リテラシー。量子情報の研究にも興味をもっている。 所属学会:日本物理学会
【 主な著作・論文等 】
最近の代表的な論文:
“Exotic nuclei with open heavy flavor mesons”, Physical Review D80, 034008 (2009). “Novel two-to-three hard hadronic processes and possible studies of generalized parton distributions at hadron facilities”, Physical Review D80, 074003 (2009).
“Proposal for exotic-hadron search by fragmentation functions”, Physical Review D77, 017504 (2008).
“New heavy-light mesons Q anti-q”, Progress of Theoretical Physics 117, 1077 (2007). “Determination of fragmentation functions and their uncertainties”, Physical Review D75, 094009 (2007).
9/8(水) エゴグラムによる性格理解入門
アメリカの心理学者J.M.デュセイによるエゴグラムは、生活の中ではたらく心のしくみを知る上で役立つ考え方であり、医療、教育などさまざまな領域で広く利用されている。エゴグラムでは、考えや行動の傾向を表す5つの領域のパワーバランスから、性格を理解する。本講座では、実際に体験学習を行いながらエゴグラムを紹介し、さらにエゴグラムを利用して日頃の対人関係やストレスを見直す手掛かりを提供する。
改田 明子(かいだ あきこ)教授
【 プロフィール 】
最終学歴:東京大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士後期課程
専門分野は認知心理学。最近の研究課題は、対話を通じた、体験過程の理解。具体的には、痛みやかゆみなどの身体症状体験および大学生の生活体験に関する認知過程。 所属学会は、日本心理学会、日本教育心理学会、日本認知心理学会など。
【 主な著作・論文等 】
自然カテゴリの認知に関する論文として、「カテゴリー群化における典型性効果」、「日常的カテゴリの概念構造」、「自然カテゴリの属性に関する信念の研究」などがある。身体症状の認知に関しては、「身体症状に関する認知の研究」などがある。
最終学歴:東京大学大学院教育学研究科教育心理学専攻博士後期課程
専門分野は認知心理学。最近の研究課題は、対話を通じた、体験過程の理解。具体的には、痛みやかゆみなどの身体症状体験および大学生の生活体験に関する認知過程。 所属学会は、日本心理学会、日本教育心理学会、日本認知心理学会など。
【 主な著作・論文等 】
自然カテゴリの認知に関する論文として、「カテゴリー群化における典型性効果」、「日常的カテゴリの概念構造」、「自然カテゴリの属性に関する信念の研究」などがある。身体症状の認知に関しては、「身体症状に関する認知の研究」などがある。
9/9(木) 韓流ブーム(歴史ドラマ)と歴史の真実
私は17世紀~19世紀の東アジアの実心実学を研究してきたが、近年韓国のテレビドラマで17世紀~18世紀の朝鮮の王宮や庶民の生活が茶の間に飛び込んでくることを無上の喜びとしている。しかし、一つ重大な問題がある。ドラマに虚構(フィクション)がかなりあることであり、その内容を歴史上のこととしては誤りであることである(『許浚』、『不滅の李舜臣』)。18世紀の朝鮮の実心実学者朴趾源の漢文小説を紹介し、かかる問題を考えてみたい。
小川 晴久(おがわ はるひさ)教授
【 プロフィール 】
最終学歴:東京大学大学院人文科学研究科中国哲学専門課程博士課程
専門分野は東アジア思想史。最近の研究課題は、実心実学研究(東アジアの主として17世紀から19世紀間の実心を重んずる実学研究)。唐甄研究、李二曲研究。 所属する学会・研究会・市民運動体で力を入れているのは、「梅園学会」(代表)、「日本東アジア実学研究会」(代表)、「北朝鮮帰国者の生命(いのち)と人権を守る会」(名誉代表)、「NO FENCE(北朝鮮強制収容所をなくすアクションの会)」(副代表)。
【 主な著作・論文等 】
『三浦梅園の世界』『朝鮮実学と日本』『南の発見と自立』(すべて花伝社刊)『実心実学の発見-いま甦る江戸期の思想』(編著、論創社)で近代以前の価値と17~18世紀の実心実学の魅力を探究。
最終学歴:東京大学大学院人文科学研究科中国哲学専門課程博士課程
専門分野は東アジア思想史。最近の研究課題は、実心実学研究(東アジアの主として17世紀から19世紀間の実心を重んずる実学研究)。唐甄研究、李二曲研究。 所属する学会・研究会・市民運動体で力を入れているのは、「梅園学会」(代表)、「日本東アジア実学研究会」(代表)、「北朝鮮帰国者の生命(いのち)と人権を守る会」(名誉代表)、「NO FENCE(北朝鮮強制収容所をなくすアクションの会)」(副代表)。
【 主な著作・論文等 】
『三浦梅園の世界』『朝鮮実学と日本』『南の発見と自立』(すべて花伝社刊)『実心実学の発見-いま甦る江戸期の思想』(編著、論創社)で近代以前の価値と17~18世紀の実心実学の魅力を探究。
9/10(金) 同盟の距離感:戦後のアメリカと日本・イギリス
超大国アメリカとどうつきあえばよいのか?アメリカの同盟国が共通して抱える課題である。この講義では、対米関係にみる日本とイギリスの比較を試みる。戦後アメリカの最良の同盟国を自任してきたイギリス。「特別な関係」とも称される英米関係の実体とはどのようなものか。今後日本はイギリスを手本にして、「極東のイギリス」を目指していくべきなのだろうか。「世界の中の日米同盟」に内在する諸問題を考察してみたい。
水本 義彦(みずもと よしひこ)専任講師
【 プロフィール 】
最終学歴:英国キール大学大学院国際関係論博士課程修了、博士(Doctor of Philosophy)
専門分野は国際政治史、イギリス政治外交史。最近は、ベトナム戦争の終結とその東南アジア国際関係への影響について研究をすすめている。
【 主な著作・論文等 】
『同盟の相剋-戦後インドシナ紛争をめぐる英米関係』千倉書房、2009年
最終学歴:英国キール大学大学院国際関係論博士課程修了、博士(Doctor of Philosophy)
専門分野は国際政治史、イギリス政治外交史。最近は、ベトナム戦争の終結とその東南アジア国際関係への影響について研究をすすめている。
【 主な著作・論文等 】
『同盟の相剋-戦後インドシナ紛争をめぐる英米関係』千倉書房、2009年
9月 柏キャンパス書道講座
9/6(月) 「般若心経」を篆書で書いてみよう
般若心経は文字数もそう多くはなく、多くの人々に親しまれているお経である。この心経を篆書で書いた著名な人物に鄧完白と呉昌碩がいる。鄧完白は清朝における碑学派の基を開いた人物であり、呉昌碩は中華民国を代表する書家である。この二人の作を対比、参考にしながら、篆書で般若心経を書いてみよう。篆書の技術向上と精神の安定に絶好である。
書き方は基本用筆の練習から順次応用へと進め、わかりやすく指導する。(実習主体)
【当日持参するもの】
書道用具(筆・紙・墨など)一式。
書き方は基本用筆の練習から順次応用へと進め、わかりやすく指導する。(実習主体)
【当日持参するもの】
書道用具(筆・紙・墨など)一式。
石野 黎峰(いしの れいほう)講師
【 プロフィール 】
兵庫県出身。新潟大学教育学部書道科卒業。書道団体勤務を経て、書家、篆刻家として独立、現在に至る。財団法人日本書道教育学会評議員。本学の他、千葉大学、日本大学、上智大学、和洋女子大学講師。
【 主な著作・論文等 】
『書の基本資料「篆刻」』(中教出版)、「はじめての篆刻」(日本習字普及協会)、「墨場必携・唐詩選を書く」他(日本習字普及協会・共著)等、多数。
兵庫県出身。新潟大学教育学部書道科卒業。書道団体勤務を経て、書家、篆刻家として独立、現在に至る。財団法人日本書道教育学会評議員。本学の他、千葉大学、日本大学、上智大学、和洋女子大学講師。
【 主な著作・論文等 】
『書の基本資料「篆刻」』(中教出版)、「はじめての篆刻」(日本習字普及協会)、「墨場必携・唐詩選を書く」他(日本習字普及協会・共著)等、多数。
9/7(火) 遷都1300年奈良時代の書
710年に元明天皇が奈良に遷都してから、今年はちょうど1300年を迎えます。「青丹よし」と詠われたこの都は、唐の長安にならった美しい都でした。中央集権国家の威容を内外に示した奈良時代は、書道史上においても後世の日本の書のあり方を決定づけるさまざまな要因があり、大きなターニングポイントとなりました。本講座は、そのいくつかにスポットを当てて、日本書道史上における奈良という時代を検討していきたいと思います。(講義のみ)
杉浦 華桂(すぎうら かけい)講師
【 プロフィール 】
神奈川県横須賀市出身。東京学芸大学特設書道専攻科卒業。現在二松學舍大学の他、國學院大學講師。書学書道史学会理事。
【 主な著作・論文等 】
『扇に書かれた書』(平成12年)、『色紙の体裁の変化についての一考察』(平成14年)、『法性寺忠通の出現と書風の変化について』(平成15年)、『藤原定家の書に見る文字の面貌』(平成16年)『日本・中国・朝鮮 書道史年表事典』(共著)(平成17年)等、多数。
神奈川県横須賀市出身。東京学芸大学特設書道専攻科卒業。現在二松學舍大学の他、國學院大學講師。書学書道史学会理事。
【 主な著作・論文等 】
『扇に書かれた書』(平成12年)、『色紙の体裁の変化についての一考察』(平成14年)、『法性寺忠通の出現と書風の変化について』(平成15年)、『藤原定家の書に見る文字の面貌』(平成16年)『日本・中国・朝鮮 書道史年表事典』(共著)(平成17年)等、多数。
9/8(水) 「漢字かな交じりの書」を書こう
我々が日常最も多く使用しているのは「漢字かな交じりの表記」である。しかし書の世界では最も遅れた分野である。今回はこの身近な表記に筆でトライしてみようではないか。心から発せられた短い語句、感銘を受けた詩句、なんでもよい。作品にしてみよう。本講座では、江戸以降にみる漢字かな交じりの作品や、中国古典にも目を向け、現代に合った書の表現について考えていきたい。
【当日持参するもの】
書道用具一式 (用紙は全紙二分の一や半切二分の一、三分の一が使いやすい。
筆は細めの長鋒などもおもしろい。)
【当日持参するもの】
書道用具一式 (用紙は全紙二分の一や半切二分の一、三分の一が使いやすい。
筆は細めの長鋒などもおもしろい。)
寺内 眞道(てらうち しんどう)講師
【 プロフィール 】
栃木県立栃木高校卒。二松學舍大学大学院文学研究科修士課程(中国学専攻)修了。
【 主な著作・論文等 】
『山岡鐵舟自用印譜』(共編、平成3年)、「篆刻家圓山大迂の印学とその作品」(平成3年)、「圓山大迂と山岡鐵舟の印Ⅰ―大迂と徐三庚」(平成4年)、「鐵舟印とその側款」(平成5年)、「端渓のふるさとを訪ねて―老坑」(平成11年)、『方谷印譜』(共編、平成16年)、『来栃120年記念 山岡鐵舟遺墨展』(平成16年)、「九成宮醴泉銘‐新資料による考察と新たな展開」(平成19年)、「山岡鐵舟の書-真贋にまつわる一管見』(平成22年)他多数。
栃木県立栃木高校卒。二松學舍大学大学院文学研究科修士課程(中国学専攻)修了。
【 主な著作・論文等 】
『山岡鐵舟自用印譜』(共編、平成3年)、「篆刻家圓山大迂の印学とその作品」(平成3年)、「圓山大迂と山岡鐵舟の印Ⅰ―大迂と徐三庚」(平成4年)、「鐵舟印とその側款」(平成5年)、「端渓のふるさとを訪ねて―老坑」(平成11年)、『方谷印譜』(共編、平成16年)、『来栃120年記念 山岡鐵舟遺墨展』(平成16年)、「九成宮醴泉銘‐新資料による考察と新たな展開」(平成19年)、「山岡鐵舟の書-真贋にまつわる一管見』(平成22年)他多数。
9/9(木) 文人的書を目指して(竹の巻)
四君子を対象として、詩文を鑑賞し、絵を描き(竹画)、書く文字を選び、落款に工夫をこらし、自刻印を押す。昔日の文人ならば当然の書画構成を学び、半切(もしくは半切1/2)程度の作品を一点作る事を目標とします。今年の対象は四君子の竹とします。お習字でもなく、絵手紙でもない、詩・書・画・印による伝統的文人趣味に則って講義、実技、添削を進めたいと考えています。
【当日持参するもの】
書道用具一式(大筆を使います)。
半切もしくは半切1/2。
筆洗(紙コップ)。
お持ちの方は自用印と印泥。
【当日持参するもの】
書道用具一式(大筆を使います)。
半切もしくは半切1/2。
筆洗(紙コップ)。
お持ちの方は自用印と印泥。
伊藤 忠綱(いとう ただつな)講師
【 プロフィール 】
東京都出身。二松学舍大学大学院文学研究科修士課程(中国学専攻)修了。
北京師範大学 華東師範大学に留学。宋代文学を専攻。本学の他、日本大学、明星大学で講師を
務める。
【 主な著作・論文等 】
『三島中洲の学芸とその生涯』(共著・雄山閣)、『名言格言事典』(共著・東京書芸館)、
『橄欄』(宋代詩文研究会)、『書道ジャーナル』等の雑誌にも執筆中
東京都出身。二松学舍大学大学院文学研究科修士課程(中国学専攻)修了。
北京師範大学 華東師範大学に留学。宋代文学を専攻。本学の他、日本大学、明星大学で講師を
務める。
【 主な著作・論文等 】
『三島中洲の学芸とその生涯』(共著・雄山閣)、『名言格言事典』(共著・東京書芸館)、
『橄欄』(宋代詩文研究会)、『書道ジャーナル』等の雑誌にも執筆中
9/10(金) 革新書道の第一 蘇軾の書の魅力
宋代、太宗の命により、中国書道史上画期的事業といえる『淳化閣帖』が復刻された。全十巻の中、王羲之と王献之が半分をしめ、二王の書法をもって正統とした。しかし、新風が台頭し、宋の四人家の登場となる。この講座では、文芸面でも豊かな天分を残し、革新的な書を残した四大家の一人蘇軾を中心に解説を行なう。王羲之を学びつつも顔真卿を復興し、鋭敏な感受性で新様式を創造した蘇軾の書美に迫りたい。
【当日持参するもの】
書道用具一式(半紙、半切適宜)
【当日持参するもの】
書道用具一式(半紙、半切適宜)
今川 佳香(いまがわ かこう)講師
【 プロフィール 】
北海道出身。二松學舍大学文学部中国文学科卒業。(学)日本書道美術専門学校卒業。現在、二松學舍大学の他、共立女子大学講師、麗澤大学講師、法政大学エクステンション・カレッジ講師。日本表装研究会幹事。年、1・2回のペースで『書と掛け軸の意匠展』の個展活動をしています。
【 主な著作・論文等 】
『李柏文書』(日本書道研究所)、『不易と流行』(綜芸舎)等、多数。
北海道出身。二松學舍大学文学部中国文学科卒業。(学)日本書道美術専門学校卒業。現在、二松學舍大学の他、共立女子大学講師、麗澤大学講師、法政大学エクステンション・カレッジ講師。日本表装研究会幹事。年、1・2回のペースで『書と掛け軸の意匠展』の個展活動をしています。
【 主な著作・論文等 】
『李柏文書』(日本書道研究所)、『不易と流行』(綜芸舎)等、多数。