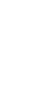
「楽しい漱石」は、たくさんのみなさまにご来場いただき、
大盛況のうちに終えることができました。どうもありがとうございました。
2016年は作家夏目漱石がこの世を去って100年目。『吾輩は猫である』・『坊っちゃん』・『夢十夜』・『三四郎』・『行人』・『こころ』・『明暗』など、小説を通じて近代における個人の自由と責任とを追求した漱石の作品は、今も読み継がれています。二松学舎は、若き時代の漱石が漢学を学び、教養を培った場です。節目の年、二松学舎大学文学部では、漱石文学が現代に持つ意味を考えるため、特別なプログラムを用意しました。題して「楽しい漱石」。有名な作品を耳で味わい、また、笑いながら読みどころを探していきます。漱石作品の奥深さに触れ、考える面白さに気づくきっかけになれば幸いです。
痛快な皮肉とユーモアに満ちた『吾輩は猫である』(1905-06年)や『坊っちゃん』(1906年)。
底深いエゴイズムの果ての孤独を凝視した『それから』(1909年)や『こゝろ』(1914年)。
人間の心の多面性をありありと描いた夏目漱石(1867-1916年)は、言わずと知れた日本の文豪です。
慶応3年生まれの漱石は、明治の年号と実年齢が一致します。その人生は、日本が西洋諸国を手本として急速な近代化の道を突き進んだ「明治」という時代と共にありました。
最高学府・東京帝国大学で英文学を学び、イギリスへの国費留学を果たした漱石は、日本の近代化を牽引するためのエリート教育を受け、当時最もよく「西洋」を知る人物の一人だったと言えます。その一方、少年期に二松学舎で漢学を学び、大学予備門で知り合った親友・正岡子規と俳句にのめり込むなど、儒学的・東洋的な世界観を生涯愛しました。
英文学者として「西洋」を熟知し、俳句や漢詩を通じて「東洋」の深みを愛好したからこそ、漱石は日本の性急な近代化を危惧していました。「西洋」が長い時間をかけて形成してきた「個」や「自由」といった概念が、本当に日本に存在し得るのか悩み続けました。
松山中学・第五高等学校・第一高等学校・東京帝国大学の講師を歴任し、英文学者としてのキャリアを築いた漱石は、だれもが尊敬する東京帝国大学教授の内示を辞して朝日新聞社に入社し、40歳にして職業作家としての道を歩み始めます。
以降、持病の胃潰瘍に苦しみ、精神的苦悩に悩まされながらも、『虞美人草』(1907年)、『三四郎』(1908年)、『門』(1910年)、『彼岸過迄』(1912年)、『道草』(1915年)などの名作を次々に生みだし、近代日本における「個」の自由と責任を追及しました。
文壇の派閥に属さず、独自の創作を貫き続けた漱石のもとには、その人柄と作品を慕って、寺田寅彦(1878-1935年)、森田草平(1881-1949年)、鈴木三重吉(1882-1936年)、内田百閒(1889-1971年)、芥川龍之介(1892-1927年)といった若者たちが集い、後に「漱石山脈」とも評されました。
作品ばかりでなく、人脈においても、漱石が近代文学に及ぼした影響の大きさは計り知れません。
女優。東京出身。07年、劇作家・演出家の藤田貴大が旗揚げしたマームとジプシーに参加。08年、岡田利規率いるチェルフィッチュに参加。以降、両劇団を中心に国内外で活動。近年は飴屋法水(演出家)や金氏徹平(現代美術家)とも共作を発表。主な出演作品に、マームとジプシー『あ、ストレンジャー』(10年、13年)、『cocoon』(13年、15年)、『まえのひ』(13年、14年)、『カタチノチガウ』(15年)、チェルフィッチュ『三月の5日間』(08年-11年)、『現在地』(12年)、『地面と床』(13年)、東京芸術劇場『小指の思い出』(14年)『書を捨てよ町へ出よう』(15年)。16年3月チェルフィッチュ新作「部屋に流れる時間の旅」(京都国際舞台芸術祭)に出演予定。その他の活動として、漫画家今日マチ子との共作漫画エッセイ「いづみさん」を筑摩書房のPR誌ちくまで連載中。また、ミュージシャンの青葉市子とユニット・みあんを結成し、音楽活動も行う。
作家・クリエーター。東京出身。編集者、ヒップホップMCとして活躍しながら、執筆活動を行なう。第一作の『ノーライフキング』(88年)で注目を集め、同作はベストセラーとなった。代表作に『ワールズ・エンド・ガーデン』(91年)、『想像ラジオ』(13年)など。ラジオ・舞台・映画などで幅広い活動を続けている。2003年より奥泉光とライブトーク「文芸漫談」を始め、現在シーズン4に到る。
小説家。山形出身。『石の来歴』(94年)で芥川賞受賞。ミステリーの手法を用いて本格的な物語を構築しながら、合理性が崩れる境界に迫る創作を精力的に展開する。代表作に『神器――軍艦「橿原」殺人事件』(09年、野間文芸賞)、『東京自叙伝』(14年、谷崎純一郎賞)など。夏目漱石の愛読者でもあり、『「吾輩は猫である」殺人事件』(94年)、『夏目漱石、読んじゃえば?』(14年)などの著作がある。
夏目漱石は夏目家に生まれ、金之助と名づけられました。塩原家に養子に出され、塩原金之助となり、夏目家にもどった後も二十歳を過ぎるまで、名字は塩原のままでした。
漢学塾時代の二松学舎に通っていたのは塩原金之助です。満十四歳から満十五歳にかけての約一年、二松学舎で学びました。
金之助は東京府立第一中学校(今の日比谷高校)正則科を退学して、二松学舎に入り、二松学舎を辞めた後は成立学舎(今でいう予備校)に通い、次に東京大学予備門に入学します。ここに西洋と東洋のあいだで揺れる金之助の心を見ることができます。
東京大学予備門に入るためには西洋を学ぶために不可欠な英語ができなくてはいけないが、東京府立第一中学校の正則科では英語の勉強ができないとわかり、金之助は「それならいっそ、嫌いな英語を学ぶのをやめ、大好きな漢学の塾に入ってしまえ」と二松学舎に入学するのです。しかし、将来を考え直した金之助は成立学舎で英語を学び、東京大学予備門についに入学します。
英語教員、英文学研究者として世に出た金之助(夏目漱石)は、作家になる前から、俳句や漢詩を作り、禅の修行をし、東洋的な境地を理想としました。〈東洋と西洋〉は漱石が生涯をかけて考え続けたテーマだったと言えるでしょう。そう考えてみれば、二松学舎で学んだ一年は、漱石の生涯の中でも独特の意味合いをもつ重要な一年でした。
さて、明治三十九年に発表された「落第」という談話の中で、漱石は二松学舎時代について回想しています。まとめて、以下に示してみます。
・学校の建物が不十分で、きれいでなかった。
・机もない古い畳の上で、カルタ取りの時のような姿勢で勉強した。
・輪講の順番を決めるくじも漢学流で、何事も徹底して漢学式だった。
・講義は朝の六時か七時から始まった。
・寺子屋のようで、学校らしくはなかったが、学費や寄宿料も安かった。
清潔な環境に慣れた現代人から見ると、劣悪な環境のようにみえるかもしれませんが、二十年以上も昔を語る漱石の口ぶりはちょっと楽しそうです。
朝六時から始まる漢学の講義に間に合うように、早朝の東京の街並みを颯爽と歩く十四歳のやんちゃな金之助少年を想像すると、想像する方まで楽しい気分になってきます。
このコーナーでは二松学舎大学が所蔵する漱石関連の資料を紹介します。
第1回は、夏目漱石漢詩文屏風です。2015年の12月に東京神田の古書店から二松学舎が購入しました。夏目漱石の書としては最大規模のもので、二枚折一双の屏風仕立ての作品は、ほかに知られていません。2016年1月25日にお披露目の記者会見を行いましたが、大きな反響があり、全国の新聞で紹介されました(記者会見の模様は、こちらをご覧ください)。
漱石自身は、この屏風について何も語っていませんが、さまざまな間接的証拠から、漱石の教え子で『中央公論』の編集者であった滝田樗陰(たきた・ちょいん)がお願いして書いてもらった最晩年の作品である可能性が高いと思われます。滝田の証言によれば、屏風を完成するまでに漱石の家に三四回通い、漱石は60枚前後の書き損じを作る苦労の末、仕上げたとのことです。
記されているのは、禅に関わる言葉を集めた『禅林句集』に収められた五言対句四種です。
始随芳草去又逐落花回
風狂蛍堕草雨驟鵲驚枝
白鷺沙汀立蘆花相対開
夜静溪声近庭寒月色深
書き下し文、出典、現代語訳は次のようになります。
始(はじめ)は芳(ほう)草(そう)に随(したが)って去り、又落花を逐(お)うて回(かえ)る。【『碧巌録』】
最初は香るばかりの若草に誘われて行き、さらに桜の花が散るのを追って帰ってきた。
風(かぜ)狂(きょう)して蛍(ほたる)草に堕ち、雨驟(にわか)にして鵲(かささぎ)枝に驚く。
急に強まった風に蛍が草に堕ち、にわかに降り出した雨に木の枝に止まった鵲が驚く。
白(はく)鷺(ろ)沙(さ)汀(てい)に立ち、蘆花(ろか)相対(あいたい)して開く。【『禅林類聚』】
白鷺が砂浜に立ち降り、蘆の花が向かい合うように咲き開いている。
夜静かにして溪声(けいせい)近く、庭寒うして月(げっ)色(しょく)深し。【『三体詩』】
静かな夜、渓川の流れの音が間近に聞こえ、寒さがみなぎる庭にかかる月の色が深みを帯びて感じられる。
春夏秋冬の自然の風景が詠まれていることがお分かりだと思います。晩年の漱石が小説において近代人の卑俗さや我欲を追究したことはよく知られていますが、ここでは作品で描かれる事態とは対極的な静かな世界が記されています。
草書で書かれた文字は、のびやかでかつ力強く、前衛的な筆遣いも見られます。最高級の紙、最高級の墨を使った本作は、書家の漱石の到達点を示す傑作です。今回、「楽しい漱石」の開催に合わせて、大学資料展示室にて屏風を特別に先行公開することになりました。ぜひこの機会にご覧ください。
夏目漱石の「夢十夜」は1908(明治41)年7月25日から8月5日まで、全十回にわたって、『東京朝日新聞』『大阪朝日新聞』に連載されました(『大阪朝日新聞』の連載は7月26日から)。「第一夜」から始まり「第十夜」で終わる、ひとつひとつの話は文庫本で三頁ほどの短い小説から成る小説集です。
「坊っちゃん」のようなユーモラスな小説、「こころ」のような人間の複雑な内面を微細に分析した小説で漱石は有名ですが、「夢十夜」を読むと、漱石はファンタジックで美しい小説や、深層心理が反映されたと見える不可思議な小説を書く方でも、とびきりの才能の持ち主だったことに気づかされます。
第一夜・第二夜・第三夜・第五夜の冒頭には「こんな夢を見た。」とあり、第九夜の末尾には「こんな悲い話を、夢の中で母から聞た。」(表記は原文のまま)とあります。他の五つの話では、語り手が「この物語は夢の話なのだ」とはっきり説明してはいませんが、全体のタイトルが「夢十夜」であるし、すべての話が夢の設定になっていると考えてよいでしょう。
ただし、漱石が実際に見た夢を小説に焼き直したものではありません。漱石は、常識や現実に囚われないファンタジックな物語を、夢の設定のもとで虚構したのです。「夢十夜」は、のびやかに表現された漱石の想像力を楽しみ、味わい、考える作品です。
全十回の物語は連作にはなっておらず、独立した世界が構築されています。それぞれの物語における主題は多様ですが、愛・不信・死・悟り・煩悩・意識・無意識・子殺し・原罪・無常・芸術・自然・歴史・西洋化・近代化・絶望・自殺・母性・欲望など、さまざまなイメージや理念が折り重ねられて、ときに美しい織物のように、ときに理解不能な抽象芸術のように、多層的な世界が紡ぎ出されます。
現代人にとっては、この不思議で美しい物語たちこそが最も良い漱石文学への入り口になるかもしれません。圧縮された濃厚な漱石ワールドにどうぞ触れてみてください。
夏目漱石の「行人」は1912(大正元)年12月6日から1913(大正2)年11月17日まで、全百六十七回にわたって『東京朝日新聞』『大阪朝日新聞』に連載された長編小説です(『東京朝日新聞』の連載は11月15日から)。ただし、胃潰瘍で倒れたために長い休載期間がありました。なお、漱石が亡くなるのは、「行人」連載終了から2年後の1916(大正5)年12月なので、漱石晩年の作品といえます。
小説は、「友達」・「兄」・「帰ってから」・「塵労」の四つに分かれているのですが、病気で倒れた後に発表されたのが最後の「塵労」です。「行人」自体が、男と女の問題を中心に、近代を生きる人間の矛盾や弱さをさまざまにあぶり出す小説ですが、特に「塵労」では、それが突き詰めて考えられます。「死ぬか、気が違うか、それでなければ宗教に入るか。僕の前途にはこの三つのものしかない」という有名な一節は「塵労」にありますが、この部分は「塵労」の、そして「行人」の特徴をよく表しています。
鋭敏な感受性と豊富な知識は幸福や社会的成功に導いてくれるはずなのに、一郎はかえってこれらのために孤独になり、苦しみます。一郎は大学の中でも特に誠実で優秀な研究者ですが、その彼は、親もきょうだいも妻も友も信じられず、妻と弟の仲を疑い、超能力の可能性に賭けようとし、ついには妻に暴力を振るってしまいます。
死・発狂・宗教の三つの選択肢の中で、宗教だけに救済の可能性があることを理解していながら、自己や個人という価値観を払拭できない知識人は宗教に身をゆだねることができない。一郎という人物は、近代以降の社会を苦しみながら生きる知識人の典型といえるでしょう。漱石は百年前に、このような人物を造形したのです。一郎は「人間全体が幾世紀の後に到着すべき運命を、僕は僕一人で僕一代のうちに経過しなければならないから恐ろしい」と語っています。
後期三部作という言葉で、連続して発表された「彼岸過迄」・「行人」・「こころ」を呼ぶことがあります。主題は知識人の孤独や絶望という点で共通していますが、形式的にも共通点があります。
小説の最後に手紙が重要な働きをするところや、異なる一人称の語り手による物語が組み合わされているところなどもそうです。ちなみに、「こころ」の最後の手紙は400字詰め原稿用紙で200枚以上、「行人」の最後の手紙も100枚近くになるそうですが、「こころ」と「行人」は異常に長い手紙の引用で、そのまま終わってしまうところが同じです。
「彼岸過迄」も「行人」も、主題が難解で物語の構造も複雑で、決してわかりやすい小説ではありません。しかし、この二作を読んだあとに「こころ」を読むと、「こころ」が小説についての大胆な実験によって初めて作られ得たのだということが、よく見えてきます。「こころ」が難しいなぁと思っている人、一度「行人」を読んでみませんか?

このコーナーでは、二松学舎大学の教員の夏目漱石に関する仕事を紹介していきます。漱石が学んだというゆかりがあり、国文学科と中国文学科とを擁する二松学舎大学文学部には、漱石についての豊富な研究の蓄積があります。
第1回は、『『坊っちゃん』事典』(勉誠出版、2014年10月20日)です。題名にあるように、『坊っちゃん』についての情報を網羅した事典です。近代文学に関する事典はたくさんありますが、一つの作品だけに特化した事典は珍しいと言えるでしょう。学長を務めた今西幹一が企画したもので、佐藤裕子・増田裕美子・増満圭子・山口直孝が編集を担当しました。漱石の専門家を始めとする書き手を結集し、最新の研究成果も織り込みながら作ったものです。
本事典は、三部構成になっています。Ⅰは、「作品用語篇」。「おれ」・赤シャツ・山嵐を始めとする登場人物、四国辺のある中学校・古町の停車場・小日向の養源寺などの場所、筒っぽう・透綾の羽織・菜飯などの風俗に関わることに詳しい解説を付け、時代背景を明確に理解できるようにしました。Ⅱの「関連項目篇」では、漱石の生い立ちや『坊っちゃん』発表前後の仕事、さらにはゆかりの人々についての情報を集め、『坊っちゃん』がどのような状況で生み出されたのかを立体的に把握できる材料を提供しています。Ⅲの「コラム篇」は、「坊っちゃん(おれ)の性格」・「研究史」・「『坊っちゃん』関連史蹟」・「『坊っちゃん』のパロディーたち」など、『坊っちゃん』に関するさまざまなトピックを集めたもので、楽しく読める内容になっています。
『坊っちゃん』は、「親譲りの無鉄砲」を自認する江戸っ子の「坊っちゃん」が、数学教師として赴任した四国の中学校での痛快な言動を描いた作品として知られています。むろん、それは間違いではありませんが、詳しい知識を得てから読み直すと、また別の顔が見えてくる小説でもあります。本事典を活用して、ぜひ『坊っちゃん』の面白さ、奥深さをさらに知ってもらえればと思います。
文学部国文学科・中国文学科の3,4年生が所属しているゼミナールです。3年生のゼミナールI、4年生のゼミナールIIとも夏目漱石の作品を中心に研究しています。担当しているのは国文学科所属の増田裕美子教授。専門は比較文学です。夏目漱石は二松学舎で培った漢文の素養に加えて、英文学者であったため、英語や英文学をはじめとする西洋文学の知識も深く幅広いものがあります。
増田ゼミでは英文学を代表するシェイクスピアの作品も合わせて読むことで、漱石作品の理解を深めています。また、外国人がどのように漱石作品を理解しているのかという視点から、外国人研究者が書いた漱石についての文章(英語)も翻訳して読んでいます。
増田ゼミの特徴はディスカッションにあります。同じ作品をゼミ生全員が読んできて、教室で発表者の発表資料をもとに意見をたたかわせます。漱石の作品には様々な象徴と謎が仕掛けられていて、一つの解釈、一つの読み方ではおさまらないところがあります。ゼミ生がそれぞれの解釈を持ち寄ることで、作品を多様に、また深く読むことができます。
ゼミでは処女作『吾輩は猫である』から絶筆の『明暗』まで主要な作品はすべて読んでいます。さらに漱石の作った英語の詩を翻訳して読んでいます。また、シェイクスピアの作品を読んでいるので、漱石が『ハムレット』『リア王』『ヴェニスの商人』などシェイクスピアの作品にあわせて作った俳句も取り上げています。
その俳句を一つ紹介しましょう。
She never told her love,
But let concealment, like a worm i’ th’ bud,
Feed on her damask cheek.
伏す萩の風情にそれと覚りてよ
英語の原文はシェイクスピアの『十二夜』第2幕第4場で、男装したヴァイオラがオーシーノ公爵に公爵への恋心を妹の話として語るセリフです。
ゼミ生の考察の例を紹介しましょう。
「男装したヴァイオラが公爵に対して自分の気持ちを話すが、自分の隠している気持ちを、目立ちにくい萩の花に例えている。その萩の良さに気付いてほしいということを現代風にいうとするなら「わたしが好きってこと気付いてよ!!!」と感じとれた。」(ゼミ生T・I)
増田ゼミでは11月の学園祭で「ロミオとジュリエット」の上演をおこなっています。また2月上旬には、4年生の卒業研究発表会をおこなっています。
平成28年2月9日に行われた卒業研究発表会のスケジュールは以下の通りです。
| 時間 | 発表者 | 題目 | 査読者 |
|---|---|---|---|
| 12:30~13:00 | 桑島文彬 | 漱石作品における夫婦とは | 小針拓也 安養なつ美 |
| 13:00~13:30 | 吉田絵里 | 漱石作品における描写表現について ~喜怒哀楽~ |
柴田和貴 山崎浩之 |
| 13:30~14:00 | 阪下幸輝 | 夏目漱石作品における「高等遊民」について | 小浜早紀子 成田茉由 |
| 14:00~14:30 | 小浜早紀子 | なぜ漱石作品は現代でも受け入れられるのか ~『吾輩は猫である』における自己本位~ |
時吉大稀 榎本明彦 |
| 14:30~15:00 | 小針拓也 | 『吾輩は猫である』の金持ち批判 | 阪下幸輝 大友優人 |
| 15:20~15:50 | 柴田和貴 | 『こころ』のホモ ~「先生」の思う二人の男~ |
永井萌奈美 矢吹潔活 |
| 15:50~16:20 | 時吉大稀 | 『夢十夜論』 | 清水理江 眞下万里恵 |
| 16:20~16:50 | 清水理江 | 夏目漱石作品における「自然」 ~生死との関係性について~ |
吉田絵里 近藤里歩 石澤拓也 |
| 16:50~17:20 | 永井萌奈美 | シェイクスピア悲劇と漱石作品における「死」 ~メメント・モリ~ |
桑島文彬 郡裕子 |
この中から3番目の卒業研究「夏目漱石作品における「高等遊民」について」の目次と、査読者によるコメントを紹介します。
序論から結論まで一貫性があり、スムーズに読み進めることができた。引用の仕方も適当で論拠として納得することができた。着眼点の良さとして、孤独を抱える中で迷いながらも自己本質を見極めさせ、いかにそれを克服するかが、漱石が「高等遊民」につきつけた課題とした点が挙げられ、面白い。はじめにや結論において筆者の自分自身と高等遊民を重ね合わせたような指摘や論文の流れもユニーク。ひとつ課題点を挙げるとすれば、時おり一文が長い箇所があり、読み下しにくい点くらいである。 小浜早紀子(4年)
「楽しい漱石」、おかげさまで大盛況のうちに終えることができました。当日は、300人を超える方に足を運んでいただきました。京都や山形からの参加者の方もいらっしゃり、漱石への関心の深さを再認識しました。
参加されたみなさん、第一部の「『夢十夜』朗読」では、青柳いづみさんの抑揚をあえて抑えた声と凛としたたたずまいとが作る世界に酔いしれ、第二部の「文芸漫談特別篇『行人』では、いとうせいこうさんと奥泉光さんとの絶妙なかけあいを楽しみながら、作品の新たな魅力に触れていました。会場となった中洲記念講堂があれほど笑い声に包まれることは初めてではなかったでしょうか。第一部・第二部の詳細については、上記タブの印象記をご参照ください。
青柳いづみに漱石作品の朗読を依頼したのは、「世紀を超えて輝き続ける伝統的な古典」と「表現の最前線を伐り拓こうとする現代の女優」の共演を観たいという、こちらの(ほとんど一方的な)願いからだった。幾度かのやりとりを経て、朗読作品が『夢十夜』に決まった後も、どのようなパフォーマンスになるのかなど、まったく想像もつかなかった。
思うに、『夢十夜』は「姿を変える小説」だ。読む者の読み方次第で(あるいは読む時の心の状態次第)で、コメディにもホラーにも、シリアスにもナンセンスにもなる。1908(明41)年に書かれたこの作品は、当時としては驚くほど新しかった。100年という時間が経過した今も、決して古びていない。古いのに新しくて新しいのに古い『夢十夜』は、「とらえきれなさ」が眼目となる。朗読するには、ひどくやっかいな作品だ。
しかし、青柳いづみの声は、想像以上に「『夢十夜』向き」だった。むしろ私には、「この作品はこの声でしか再現できないのではないか」とさえ感じられた。彼女の声は、幼くて細い。でも、はっきりと鼓膜を打つ。感情と抑揚を抑えているのに、張りつめた緊張感がある。たぶん、聴く者の「心の可聴音域」によって姿を変えてみせるのだろう。あどけなくて妖艶で、慎み深くて意地悪で、まるく柔らかくてするどく尖った声だ。
「朗読を聴く」ことは、「耳を頼りに小説世界を歩く」ことだ。青柳の朗読を聴いて、通い慣れた道を淡々と歩くように感じた人も、薄闇の中を更に暗い方へと歩くように感じた人もいるだろう。
私にとって「青柳いづみ朗読『夢十夜』」は、「きれいで、こわかった」。「明治の夢」をイメージしたという黒い和服。一話ごとに意味ありげに変えられる姿勢。(たぶん)計算された息づかい。自信と不安が交錯する目線……。それらすべてを合わせて、「きれいで、こわかった」。(この「こわい」の半分は「畏」で、できれば「きれい」と「こわい」という文字を重ねて表記したい)。まるで「これ以上見続けたら戻ってこられなくなる夢」へと、手を引かれているような40分だった。(荒井裕樹)
今回、二松学舎大学ではいとうせいこうさんと奥泉光さんに「文芸漫談」の特別編をお願いしましたが、本篇は下北沢でこれまで30回以上開催されている大人気の企画です。今回は、漱石作品の中でも陰気でわかりにくい印象の『行人』をあえてとりあげていただきながらも、幅広い聴衆(高校生から八十代の方まで)を爆笑の渦に巻き込んでいただきました。
「文芸漫談」本編のホームページには、「芥川賞作家奥泉光と稀代の仕掛け人のいとうせいこうが捨て身で挑む“漫談スタイル”の超ブンガク実践講座」と出ているのですが、今回の特別編でも、文学的な視点や文学的に考えることの楽しさや意味を、漫談という形式で「実践」的に教えてくれました。
「文芸漫談」は落語と同じくマクラから始まります。今回のマクラは、奥泉光さんが最近購入されたばかりのスマートフォンでした。スマホのライトが消せずにサービスショップを探して奔走するという話に、会場は大笑い。ボケ役の奥泉さん、ツッコミ役のいとうさんの役回りに聴衆が慣れた頃に本題へ入りました。
おふたりの「文芸漫談」の流儀は、お笑い芸人の漫談(スタンダップ・コメディ)同様、小道具は一切なしでステージに立つこと。マイク以外に持つのは、文庫本だけです(机や台も置きません)。時に頁数や行数を示しながら本文を朗読して、そこにコメントをつけるのはまさに大学の講義。ただ、大学の授業のやり方と違うのは、いとうさんと奥泉さんは妥当な解説をつけるのではなく、ツッコミを入れることです(奥泉さんも本文にはツッコミます)。
アフタートークで「大学生に向けて小説の読み方をアドバイスしてください」と求められた時に、いとうさんは「ツッコミを入れること」と答えていましたが、作品を信頼し、容赦なく本音でツッコミを入れることで、読み手と作品とのコミュニケーションが発生し、作品に潜在する構造も発見できるのでしょう。
『行人』での実験的な一人称小説の取り組みから『明暗』での三人称への展開、作品終盤になり急に重要人物として登場するHさんが『吾輩は猫である』の猫と似ていること(ともにノイローゼの人物を客観化する存在)、兄嫁のお直は水神であるという仮説(これについては、本学の増田裕美子さんも同じ考えを論文にしていて、アフタートークで「我が意を得たり」と喜びを口にしていました)など、多くの斬新な〈読み〉に触れることができました。また、アフタートークでは、いとうさん・奥泉さんそれぞれの夏目漱石像と、強いリスペクトの念も語っていただきました。
「文芸漫談」の締めくくりは、奥泉さんのフルート演奏といとうさんの本文朗読のセッション。文学+お笑い+音楽の豊かなコラボレーションで、聴衆のみなさんは深く満足されているように見えました。終了後、楽屋に戻ってから、「おふたりはいつもユーモアに満ちていますが、まったく緊張していないのですか?」とたずねると、「ひとりだと場を作るために緊張することもあるけれど、ふたりだから緊張はしないよ」とおっしゃっていました。
笑いや音楽とのコラボレーション、ひとりで講義するのではなく、信頼感で結ばれたふたりでセッションしながら発信・表現すること。大学のやり方とは異なる、稀有な文学の表現方法に触れ、たいへん良い刺激を受ける機会になりました。「楽しい漱石」という入口から入った多くの聴衆の方々は、「深く豊かな漱石」を感じて会場を後にされたように思います。(瀧田浩)
『行人』を読んだのは、確か学生時代。ただ、最後まで読み切った記憶がないんです。「こんなめんどくさい兄ちゃんがいたらイヤだな」漠然とそんなことを思ったことは覚えているのですが。この程度のボンヤリした認識で、今回の『楽しい漱石』に参加しました。こんなタイトルがついているんだから、肩肘張る必要もないでしょう。気軽でいいんでしょう?
いとうせいこうさんと奥泉光さんお二人の文芸漫談、というか『行人』についてあーでもないこーでもないと、日常の言葉で見解を投げ合う姿を目にして、「ああ、これでいいんだ」と思えたことが、このイベントに参加して得た一番の収穫だったかもしれません。漱石という100年前に生き、そして100年後にまで残る作品を生み出した作家に対して、私たちは“とてもすごい人”という認識で向き合ってしまう。軽い言葉で作品について語ってはいけないような気になってしまっているように思います。しかしちょっと考えてみれば、この『行人』は新聞に連載された小説です。今に置き換えれば朝の連ドラのような存在でしょうか。朝ドラを見て会社に行って、ドラマの筋や登場人物の言動について無責任にヤイヤイお喋りをする、それと同じような役割を新聞小説が担っていたのではないかと思うんです。せいこうさんと奥泉さんがお話する様子を見ながら、文学作品を高尚なものだと思い込んだり、難しい言葉で論じる必要はない、文学を楽しむためにはどのような言葉で自分の中に落とし込んでもいいんだとホッとしました。もちろん学問として難しく論じてもいいんですけど。
日常的に、身勝手に、文学について“お喋りをする”。本を読むことが何となく特別なことようにとらえられがちな今だからこそ、この軽さを私は求めていたんだな、そんな自分の気持ちを確認できたような気がします。日常の言葉で楽しく無責任に理解をぶつけ合うことで見えてくる、作品の新しいカタチがあるはず、ですよね。
作家としての漱石の活動期間は10年ほど。その間にこれほど多くの名作を残している。名曲しか残さないミュージシャンのようだね。そのようなことをせいこうさんと奥泉さんはおっしゃっていましたが、音楽が好きな私には、この言葉によって漱石が突然実体を持って目の前に現れたように思えました。身近なものに置き換えることで、遠い世界に感じられていた物事が、途端にこの手で触れられるように思える。このような自由な視点が、文学で楽しく遊ぶための道具なのかもしれません。(橋本幸季)
ご来場のみなさまにアンケートをお願いし、たくさんの方からご回答をいただきました。ご協力ありがとうございました。いただいたご感想・ご意見の一部をここでご紹介させていただきます。
なお、当日の運営(受付・進行など)や施設(音響・照明・空調など)に関して、さまざまなご提言をいただきました。二松学舎大学文学部としてこのような催しは初めてであり、スタッフが不慣れであるゆえに、ご参加いただいたみなさまにいろいろとご不便・ご迷惑をおかけしたかと思います。至らなかった点、深くお詫びいたします。お寄せいただいたご意見を踏まえて、改善に努めていきますので、今後ともよろしくお願いいたします。
会場
二松学舎大学九段キャンパス1号館中洲記念講堂
アクセス
地下鉄 東西線・半蔵門線・新宿線「九段下」駅下車 2番出口より徒歩8分JR「市ヶ谷」「飯田橋」駅下車 徒歩15分
お問い合わせ
二松学舎大学国文学共同研究室「楽しい漱石」事務局
〒102-8336
東京都千代田区三番町6-16
TEL:03-5962-3304
https://www.nishogakusha-u.ac.jp/news/h28bungakubusoseki.htm
「あっという間でした。「楽しい漱石2」希望!!」(男性・20歳)
「読んだことのない作品でしたが、漫談がおもしろかったです」(女性・18歳)
「文芸漫談がとても良かった。/あまりメジャーではない「行人」を知らない人にもこれは読みたい!と思わせる語りが素晴らしい。/また「行人」をきっかけに他の夏目漱石作品(あるいは別作家作品)にも言及していく形が非常に分かり易く、また「ボケ」と「ツッコミ」的なお二人の構図も面白く、どこか堅苦しいイメージを持った作品をネタにここまで興味深くかつ楽しい話を聞けるとは…。/本当にありがとうございました!」(女性・21歳)
「ステキな企画をありがとうございました。前半のリーディング、不思議なふんいきにつつまれました。/後半の漫談 文章表現や場面の1つ1つを深くよむことができて「行人」がとても身近で印象深い作品となりました。/「行人」=歩く人だとすると、最初の場面で兄と弟が歩く場面が目にうかびました。」(女性・公務員)
「青柳さんの朗読は、独特な読み方はもちろんの事、読み上げている時の仕草が印象的でした。読み進めていくうちに引き込まれる朗読でした。/文芸漫談では、いとうさんと奥泉さんのテクストの読み込みの深さと、「行人」という全体的に暗い作品で漫談をしてしまうという変化球が上手いと思いました。」(男性・21歳)
「○朗読 あまり表情のない朗読で、「夢十夜」の持つ特有の色が表現されていると感じました。とくに、第一夜、第三夜、第七夜、第九夜は作品の持っている雰囲気が似ているとかねてより感じており、さらに青柳さんの雰囲気ととても重なるものがあって、惹き込まれました。/○文芸漫談 初めて文芸漫談というものを拝聴しましたが、普段研究でゼミ生等と交わすような会話、本文への疑問や興味関心、読みこみをとても楽しく繰り広げていて、聞いていて参加したくなるような、文学への愛を唆られるような、心をくすぐられる飽きない時間でした。」(女性・21歳)
「プロだな…と思いました。/「楽しい漱石2」をお願いします。」(女性・51歳)
「『夢十夜』も『行人』も読んだことがなくて参加したのですが最後までとても興味深くひきこまれました。/小説が身近になった気がしました。」(女性・41歳)
「漱石の文は漢字が多いので、かまえて読むことが多かったが、耳から聞いてみて意外なくらいわかりやすく、景色が目に浮かぶので楽しかった。読みこなす側の力量もあったと思う。/漫談、大変おもしろかったです。帰ったら『行人』読みます。/次回希望!」(女性・49歳)
「今日は用事の関係で第二部からの参加になってしまいましたが、お二人のかけ合いはテンポもよく、あけすけな表現に笑いを誘われて、とても楽しい時間でした。/また、奥泉さんのフルートといとうさんのフルートと朗読の相しょうも抜群で、聞いていて怖く感じるほどの迫力を感じました。/直が「水神」という説を聞いて、もう一度「行人」を読みたくなりました。 ※外で第一部も見ていたんですが、やはり漱石はギ音の使い方が上手だなぁ…!と思います…やはり朗読っていいですねぇ/またやってくれると嬉しいです!楽しみにしています」(女性・18歳)
「青柳さんの朗読、いとうさん、奥泉さんの漫談、共に楽しく聴かせて頂きました!/是非“楽しい漱石2”の開催も宜しくお願いします!」(女性・21歳)
「夏目漱石に興味があり参加させていただきました。/朗読という形で、小説を聞く側にまわることはなかなか無いと思うので、とても新鮮でした。/自分で実際に読む時とはまた異なる感覚で、声を通じて作中人物の言葉を聴くと、より想像力がかきたてられてより『夢十夜』の不思議な世界に引き込まれました。青柳さんの声もとても美しかったです。一話ごとに読む体勢を変えていて、声だけでなく身体での表現にも魅せられました。/文芸漫談はとにかく面白かったです。「漱石の人物のキャラの印象のつけ方が上手」という所になるほどなと感じました。今まで大学の講義では、専門的な目線から見ていくことが多いのですが、様々なジャンルの事がらとつなぎ合わせて進めていくことで、わかりやすく親近感がわきました。『こころ』もまた読み返していきたいです。/この度は二松学舎大学にお越しくださり本当にありがとうございました。/先生方もお疲れ様です。またこのようなイベントを開いていただきたいです!!是非「楽しい漱石2」を!!」(女性・19歳)
「漱石の本をもっと読みたくなりました。/「楽しい漱石2」をお待ちしております。(女性・18歳)
「無料で内容がとてもこくてすばらしかったです。/とくに文芸漫談は大笑いしました。/四月、五月のも行きたいです。/そしてぜひ「楽しい漱石パート2」を!!!」(女性・47歳)
「初めてこのような会に参加したのですが、とても楽しかったです。/第1部、第2部ともに興味深く、貴重な時間を過ごさせてもらいました。ありがとうございました。」(女性・20歳)
「朗読のときの間の取り方が聞きやすいと思った。声が可愛かった。/いとうさんのツッコミや奥泉さんのエピソードが面白かった。/「行人」はまだ読んだことがなかったので読んでみたいと思えた。」(女性・18歳)
「文芸漫談面白かったです。/こういう本の読み方もあるんですね。」(女性・68歳)
「・大変楽しい時間でした。/・これが無料なんてすばらしすぎる。/・心が豊かになって帰路についた。/今後もこういった企画があったら必ず来たい。」(女性・68歳)
「第一部の朗読、いつもは文字で読むだけですが、声で聴く夢十夜、とても心地良い体験でした。声で聴く夢十夜がいかに「笑える」作品なのか。という発見がありました。(第四夜)/非常に楽しく面白い時間でした。漱石が、こんなに面白いということを、初めて、こうして話しを聞けた経験でした。一人歩きする「漱石」のイメージですが、もっと面白がっていいんじゃないかと、やっぱり感じます。/いとうせいこうさんの、最後に仰った、短期間だけで存在を残したパンクなバンド、本当に自分の漱石観と同じで、驚きました。たった10年ちょっと、しかも「たかが」新聞小説作家が、「国民作家」になっている、それも言ってみれば、モノスゴク「変」だと思います。でも、だからこそ、漱石は、みんな大好きなんだと思います。現在まで愛され続けている人間性が、漱石の漱石たる由縁なんだなぁと感じました。漱石、知れば知るほどオチャメですよね。/今日はまことに貴重な時間ありがとうございました。」(男性・28歳)
「とても良い企画でした。/文芸漫談も面白かったです。/これは、本に興味の無い人に興味を持たせるのにとても良いと思う。/NHKの番組にしたらいいと思う。」(男性・21歳)
少し難しい内容になるのかと思いましたが、楽しく一緒に勉強ができました!/漱石の本をもっと多く読みたくなる企画でした。/朗読もシンプルな演出だったので、朗読に集中して聴くことができました。/文芸漫談ということだったので笑える所も多く、楽しかったです。(女性・18歳)
楽しい時間でした。/次回、その次をお願いします。(女性・50代)
文学散歩MAPを活用するのが楽しみです。ありがとうございます。/ライブパフォーマンスだったので難しくなく、楽しめました。/進行役の先生や副学長のお話に、漱石のことが知れる知識が多く、もっと聞いていたくなりました。知らない事だらけでした。/文芸漫談は初めてでしたが、笑って学べるなんて面白く楽しすぎでした。いい機会でありがとうございます。漱石が38歳から書いたとは、知らなかったです。人物紹介があって尚わかりやすかったので感謝!!本の読み方が変わりそうです。読みたくなりました。(女性・43歳)
とても良かった。「楽しい漱石」の名に違わない、良い講演でした。/またやって欲しいです。(男性・24歳)
リーディングもトークも良かったです。行人を読んだことがないので今度読みまたいと思いました。あと奥泉さんのフルートが生で聴けてうれしかったです。(女性・18歳)
続きを見る