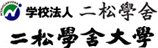第1回 アイルランドの選択 国際政治経済学部 専任講師 井上 裕司
国際政治という舞台では、ときに主役である大国ではなく、脇役に甘んじてきた小国にスポットライトが当たるときがあります。今日は、そんなスポットライトをまさに浴びているヨーロッパの小さな国について話しましょう。
ロンドンで用事を済ませた後、飛行機といっても1時間くらい乗っただけ。新幹線なら東京から静岡に行くくらいのもんです。これだと飛行機も一番上まであがったと思ったら、もうすぐに降下開始しちゃいます。気圧の変化に弱い耳をもつ私はおちおちのんびりもしてられません。そうして、私がヘタな耳抜きに一生懸命になってる間に着いてしまったのがダブリンでした。

アイルランドという国についてよく知っているという人はそんなにいないでしょうね。かつて世界の7つの海を支配したイギリスが日本と同じ島国であることは有名ですが、そのイギリスのあるグレート・ブリテン島に寄り添うようにして浮かんでいる小さな島国がアイルランドです。北海道と同じくらいの面積しかありません。人口はわずかに400万強の小国。そのうち120万人ほどが首都であるダブリンに住んでいます。
小さいとはいっても、日本でも有名なアイルランドのモノってけっこうあるんですよ。いろんな分野の世界一を集めたギネスブックは、アイルランドのビール会社ギネス社が発行したものですし、U2やエンヤといったアイルランドの歌手を知っている人は多いでしょう。また、驚くべきは、本国アイルランド以外の地にいるアイルランド系の人たちです。なかでも、アメリカには3000万を超えるアイルランド系アメリカ人がいます。本国には400万くらいしかいないのにですよ。しかも、そのアイルランド系アメリカ人には、例えば故ケネディ元大統領のようにアメリカ政界のトップに昇りつめた人までいるんです。

そのアイルランドに行ったんですが、正直、例えば同じロンドンからユーロスターでドーバー海峡を越えてパリに着いたときほどの感慨はありません。アイルランド語(ゲール語)はありますが、実際はほとんどの人が英語で暮らしてます。街並みもイギリスとほとんど変わらないです。パっと写真だけみたらイギリスの地方都市と間違えてしまっても不思議ではないほどです。人と話してみないと、とにかく外国に渡った気がしません。
それもこれもアイルランドの歴史に秘密があります。イギリスに寄り添うようにある島ですから、古い時代からイギリスとの関係が深い国です。ただ、その関係は対等な関係ではありません。簡単に言えば、イギリスにやられっぱなし。17世紀には事実上植民地化されてしまいました。1840年代の有名な「ジャガイモ飢饉」のときには、国内で100万人とも言われる人が餓死しているのに、イギリスに食料輸出を続けなければならないという悲惨な状況にまで追い込まれます。このときアイルランドから逃げるように大量の人々が新大陸に向かっていきました。今の多くのアイルランド系アメリカ人の先祖たちです。
また、アイルランド本国でも飢饉を放置したイギリスに対する憎悪が燃え上がりました。独立運動の始まりです。約100年の歳月をかけて1949年にようやくイギリスから完全に独立を果たします。といっても、イギリス経済への依存は変わらず、貿易の8割はイギリス向け、主たる産業も農業くらいで、西欧における最貧国のひとつと言われつづけます。政治的な独立と経済的な自立は、同じことではないんですよね。

そんなアイルランドにとって大きな転換点になったのが1973年にEC(欧州共同体)に加盟したことです。80年代後半からECの市場統合が進んでいき、90年代にEU(欧州連合)が設立されると、このヨーロッパの片田舎にある農業国が世界中から注目を集めました。
ユーロという通貨についてご存じの方は多いでしょう。
それまでフランスではフラン、ドイツではマルクとそれぞれ国ごとに別々だった通貨を、ひとつの共通の通貨にしたのがユーロです。EUの経済統合の象徴のような通貨ですね。ただ、ユーロは、EU加盟国すべてで通用する通貨ではありません。
例えば、イギリスでは昔と同じようにポンドを使っています。では、アイルランドはどうかというと、イギリスとは違ってユーロを導入した国のひとつになりました。イギリスでは通用しないのに、アイルランドでは通用する。これはつまり、アイルランドは、英語圏で唯一のユーロ導入国になったということです。
このことが大きな追い風になり、アイルランドにはEU諸国だけでなく、アメリカを中心としたEU域外の諸国からも投資が活発に行われるようになります。この外国からの投資によってアイルランド経済は昇竜の勢いで発展していきます。
いえ、竜ではなく虎でした。「ケルトの虎」。超高度経済成長を遂げたアイルランドを専門家たちはそう称賛しました。産業も農業からIT産業や金融を中心とした工業国に生まれ変わりました。
一人当たりのGDPは、イギリスも日本も追い越して、世界でも有数の裕福な国になりました。ただし、残念ながら話はそこで終わりません。スポットライトが当たったのはこの時ではないんです。

経済統合と外国からの投資によってようやく経済的な豊かさも手に入れたアイルランドですが、現在世界を襲っている経済危機を避けることはできませんでした。この経済危機では、似たような名前のアイ「ス」ランドが国家破綻の寸前にまでいったことが日本でもニュースになりましたが、アイルランドも他人事と笑ってられません。
外国からの投資によって開発を進めたアイルランドでしたが、その外資が金融危機によって一気引き揚げてしまい、開発・不動産バブルがはじけてしまいました。それによって国内銀行が抱えることになった負債はGDPの数倍にものぼると言われています。
雇用情勢も悪化し、失業率は9%を超えました。実際に話を聞くと、ダブリンでは、繁華街のそこかしこで物乞いをする若者が増えているようです。外国から投資を集め、工業化を果たし、世界市場に打って出たところをカウンターパンチ。まさに天国から地獄です。
さて、こういう状況になった今、とうとうアイルランドにスポットライトが当たることになりました。ヨーロッパ中の国家がアイルランドの動静を注視しているんです。

アイルランドが経済開発を進められたのは、多くの部分EUによる経済統合のおかげと言えるでしょう。ただ、それは必ずしも良いことばかりではありませんでした。アイルランドは、ユーロを導入しましたが、それは単に通貨をユーロに変えるだけのことではありません。ユーロを導入する国には一定のルールを守る義務もあるんです。
そのひとつが政府が使うお金、財政のルールです。GDPの3%までしか財政赤字を出してはいけないとされています。これでは不景気に陥ったとしても、政府が赤字覚悟でお金を使って経済を支えるということが自由にはできません。また、不景気で税収が減れば、必要なお金は国民の負担を増やすしかなく、それは国内の政治不安をもたらす可能性があります。
事実、私がアイルランドに渡る1週間前には、政府が提案した公務員に対する年金保険料の増額案に反対する10万人規模のデモが行われました。人口120万人のダブリンで10万人のデモはすごかったでしょうね。

また、EUに加盟するということは、貿易がしやすく、外国から投資が入りやすくなるというだけのことではありません。人も同じ流れにのってやってきます。好景気に沸いたアイルランドにはポーランドをはじめとする東欧のEU加盟国から労働者が大量に押し寄せてきました。外国人労働者の数は、人口の10%を軽く超えています。好景気で労働力が不足しているときならいいでしょう。でも、失業者が街にあふれるなんてことになると、外国人労働者に職を奪われてしまったと思う人も出てくるわけです。
こうして、景気の浮き沈みのなかでEUに加盟するメリットとデメリットがはっきりと目にみえるようになった今、アイルランドで実施されようとしているのが、EUのリスボン条約についての国民投票です。EUは、国ではなく国際機関ですから、加盟国がその基本となる条約を締結する必要があります。これまで数年ごとに新しい条約を締結し、EUは、時代に応じて常に変化しながら存在してきました。その最新版の条約がリスボン条約です。
実は、アイルランドは、既に一度、この条約について賛否を問う国民投票を実施しています。そのときは、なんと条約を認めないと否決してしまったんです。加盟国すべてが条約を認めなければ、リスボン条約は効力を持ちません。そこで、もう一度、改めて国民投票が実施されようとしています。新条約が承認されるかどうか。EUに加盟諸国の5億人の人々の命運をアイルランドの400万人が握っているわけです。これがアイルランドにスポットライトが当たっている理由です

アイルランドにも、これまたイギリスと同じパブという酒場があります。ただ、カラフルで凝った外観をしているところが、ちょっと違うかもしれません。なにより見ず知らずの日本人の私が一人で飲んでいると、陽気に話しかけていろいろな話を聞かせてくれた親父さんたちの気さくなアイルランド人気質もイギリス、特にイングランド人との違いを感じさせます。この人たちがいったいどんな選択をするのか、私も興味津々に見守っています。