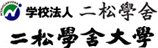- HOME
- スペシャルコンテンツ
- 国文学科教員の外国見聞録
- 第3回 漱石が見たパリ
第3回 漱石が見たパリ 文学部国文学科 教授 山口 直孝

夏目漱石(1867年~1916年)がイギリスに留学したことは、有名です。漱石は、日本政府から英語研究を命じられ、二年間ロンドンで不自由な暮らしの中、神経症に苦しみながら、与えられた課題とは異なる文学研究に打ち込みました。その成果は後に『文学論』ほかの評論で実を結び、また、『吾輩は猫である』に始まる創作にも影響を及ぼしています。
イギリスの留学体験に対する注目は高く、研究書も多く出されています。それに対して、ロンドンに到着する前に漱石がパリに一週間立ち寄っていたことは、あまり知られていません。滞在期間も短いため、詳しい検証は行われてきませんでした。近年ようやく、山本順二『漱石のパリ日記――ベル・エポックの一週間』(彩流社、2013年12月)が刊行され、空白を埋める機運が生じているところです。
この夏、116年前に漱石が滞在した家を訪ねることができました。きっかけは、パリ在住の立松弘臣さんからお誘いをいただいたことです。実業家であり、日仏文化交流に尽力されてこられた立松さんは、パリ暮らしを始めて約50年。フランス近代史に精通し、地図や作家の自筆物の収集家としても著名な立松さんにご案内いただけるのは、願ってもない話です。ご厚意に甘えて、うかがうことにしました。フランスを訪れるのは、初めて。フランス語はまったくできず、頼りない出発となりました。
パリを訪れたのは、7月12日~17日の6日間。漱石が滞在したのは、1900年の10月21日~28日なので、それよりも短い、慌ただしい旅となりました。7月は一年で最も過ごしやすいと言われる時季で、湿度が低く、空の青さがひときわ鮮やかに感じられる日中は快適そのものでした。
現地をめぐる前にまず、下調べをしておかなければいけません。パリ17区のニエル大通りにある立松さんのお宅にお邪魔し、お話をうかがいました。貴重な資料を間近に見ながら、漱石の足取りを確認する作業は、贅沢な時間でした。
漱石は、9月8日、ドイツ客船プロイセン号に乗って横浜を出航しました。一か月以上の船旅を経て、10月18日にイタリアのナポリに到着、翌19日、ジェノバで船を降り、一泊した後、鉄路でパリを目指します。リヨン駅に着いたのは10月21日の9時ごろ。馬車を利用して16区のギュスタブ・クールベ通りの宿を目指しました。漱石たち留学生の一行は、以後この宿に一週間滞在し、万国博覧会を見物したり、パリ在住の日本人を訪ねたりしています。10月28日、漱石は一行と別れ、一人ロンドンへ向かいます。サン・サザール駅から西部鉄道を利用し、ディエップからニューヘヴンへの海路を経て、ロンドンに向かったという説が有力視されています。
パリの近代史は、立松さんの関心領域の一つ。当時の雑誌、新聞、広告、絵葉書、写真、切符、レストラン・メニューなどを豊富に所持されています。それらを踏まえてていねいなご解説をしていただいたことで、漱石のたどった道のりを具体的に知り、彼が見た風景を彷彿とすることができました。見せていただいた資料のうち、彩り鮮やかな2枚の絵葉書を紹介させていただきます。

7月14日、いよいよ漱石の滞在した宿や万国博覧会が開かれていた場所を実地踏査する日が来ました。この日は、ちょうどフランスの独立記念日、いわゆる「パリ祭」の日です。戦闘機が轟音を立てて上空を横切る中、立松さんとシャンゼリゼ通りに向かいました。大勢の見物人を前に騎兵隊や音楽隊が、また最新型の火器や戦車が行進していきます。独立記念日の催しが軍事パレードにほかならないことを改めて認識させられました。

パレードを見物できたのはよかったのですが、大規模な交通規制がかけられ、シャンゼリゼ通りを横断することができなかったのは想定外でした。昼食休憩を取って規制が解かれるのを待って、アレクサンドル三世橋に向かいました。この橋は、フランスとロシアとの友好の証として、パリ万博に合わせて建てられ、パリ市に寄贈されたもので、渡るとすぐにアンヴァリッド会場になります。

セーヌ川沿い、万博開催中は動く歩道が敷設されていた道を進み、主会場であったシャン・ド・マルス地区を目指していくと、エッフェル塔が間近に見えてきます。またも交通規制に引っかかってしまったため、漱石たちが登り、下界を見渡して感嘆したエッフェル塔に行くのは断念せざるをえませんでした。手前で再びセーヌ川を渡り、会場入口であったトロカデロ宮を通過すると、漱石の滞在先はもうすぐです。偶然ですが、漱石たちの宿は、会場から徒歩約十分の場所にありました。漱石は二度万博を見学しています。「規模宏大にて二日や三日にて容易に観尽せるものにあらず。方角さえ分らぬ位なり」(10月22日)は、一回目に訪れた後に日記に記された感想です。西欧文化の先端に触れた漱石の衝撃は、今の私たちが想像する範囲を越えるものであったのかもしれません。

漱石が滞在した家は、ギュスタブ・クールベ通り22番地の6階建てのアパルトマンです。一行は、三階の一角に泊まりました。中の設備は現代の生活に応じて改められているでしょうが、階段や入口のたたずまいは、当時とほとんど変わりません。通り全体の雰囲気も、駐車している自動車を除けば一世紀前と同じです。古い建物がそのまま残っているのは、地震がなく、石造の家屋が基本であるヨーロッパでは珍しくありません。しかし、都市の景観が目まぐるしく移ろい、生家を始めとして漱石が住まった場所の多くが失われていることと比較すると、建物が維持され、生活空間として今も利用されていることは、やはり驚きです。漱石にとっても、街並みや寝泊まりする空間の異なりは、強い印象をもたらしたことでしょう。「停車場を出でて見れば丸で西も東も分らず恐縮の体なり」(10月21日)という記述は、漱石のパリ体験を凝縮して表していると考えられます。何もかもが日本と違う場所の中で、「恐縮」することを常に余儀なくされる。漱石にとっての西洋とは、まずはそのような身体的な経験として受け止められたのではないか。アパルトマンの前にしばしたたずみながら、想像をめぐらせました。
書かれたものを読むだけでは気づきえなかったところに目を開かせてもらえたことは、大きな収穫でした。フランス語を解さない人間が町をさまようこともなく、漱石の足跡をたどることができたのは、立松弘臣さんのご案内のおかげです。改めて深く感謝を申し上げます。(山口 直孝)