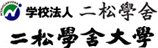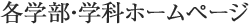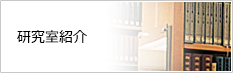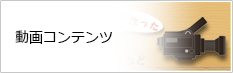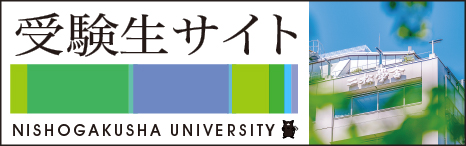関 俊史 SEKI Toshifumi専任講師

専門
中国書学・書道史、書道実技、書写書道教育
中国書論を中心に、なぜ「書」が価値を持ち、「芸術」として認められるようになったかを研究しています。
教員からのメッセージ
書の表現は、一般に”文字(主に漢字と仮名)”を使用するという約束の下にある。漢詩にせよ和歌にせよ文章を書くことが主であるため、その制約もある。また、自分の好き勝手に書いてはいけない。歴史的価値付けがなされた「古典」に基づいて表現する。こうした数々の制約の中でいかに表現するかを個々人が探求する。そこに面白みがある。
その面白みは例えていうなら、天体観測をしていて星を見つけた時のようであるかもしれない。一等星もあれば六等星もあり、はっきりとした光から微かな光まであるものの、それは確かに自分が見つけた輝きである。その集めた輝きを使って新たな宇宙を作る、書とはそういうものではないかと思う。
私のオススメ
現在の言い方をすれば「沼る」とでもいうべきでしょうか、自分の興味関心を強く持ち、そのことについて広く知ることや、見ることが大事だと思います。情熱をいかに傾けることができるか。それがあるだけで人生は少しは楽しくなるかとおもいます。
ただ、その際に大切なのは、闇雲に見るのではなく、「本物」と「一流」を見ることです。自分の推しの舞台でのパフォーマンス、一流のスポーツ選手の動き、好きな絵画作品など、どこまでバーチャルが拡張しようとも、リアルな体験に勝るものはありません。そして、一流のものを知ることです。一流のパフォーマンスからは、一流の気品とも呼べるものが漂っています。そうしたものは自分が全く知らない世界であっても、「本物」のすごさはわかるものです。そういうことがあるのを知ることも大切です。
バークリも「存在するとは、知覚されることである」というように、あなたがものを知ることでそのものが存在していることを認識します。まずは「知る」ということから始めましょう。特に現在は検索である程度の想定ができる時代になってしまいました。自分の想像が及ばないことをしたり、見たりすることが、あなたの想像力を鍛えてくれると思います。そして、ものを見るときには、最初はおおまかにしか見えなかったものが、経験を重ねることによって、だんだんと細部が見えるようになっていきます。「神は細部に宿る」といいますが、「細部」を突き詰めていくことで、そこから単なる形状や動態のさらに向こうを感じるようになっていきます。
大学生の時分は、とにかく本物を見るようにしていました。書を見るのはいうまでもありませんが、博物館へ行っては全く知らない西洋絵画を見てみたり、映画館でB級映画を見たり、文無しで古本屋を練り歩いては、店主に本について聞いたり、今思えばほとんど大したことはしてませんし、ほとんどが無駄だったかもしれません。ですが、その無駄を知ったからこそ、本物もわかるわけです。本気で「沼る」とは、コスパもタイパも実に悪いことですが、本来、生きること自体がそんなもんですから、つまんないことを気にして、人生を無駄にするよりは、いろんなことに目を向けて人生を謳歌するほうが、あとあと見返して楽しいんではないでしょうか。
最近の活動
・講演「「三国志」と書――当時の状況と書法を中心に」(「第9回”三国志”の作り方講座」)
・ラジオ出演「おとなレクリエーション」(ラジオ大阪ほか9局)
・論文「王羲之の幻影 ――「盡善盡美」をめぐって―― 」(『六朝学術学会報』(23)、2022年)など
ゼミの様子、活動内容など
実作面では、3年次は自身の選定した書体を究めるようにし、いくつかの古典を選択して精修することで、基礎的な表現力を養うようにします。4年次では、学んできた古典を生かして、卒業作品の制作を行っていきます。理論面では、3年次に自身のテーマを決定し、それについての先行研究や理解を深め、4年次で卒業論文を執筆していきます。夏と春に合宿を行い、集中して作品制作や研究を行います。時には筆墨硯紙の講習や、拓本や複製等の鑑賞などを行います。ゼミの雰囲気としては、楽しむ時は楽しく、集中するときは集中し、書の表現と理論探求にみんなで日々努めています。