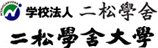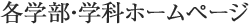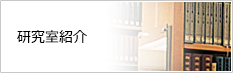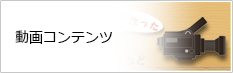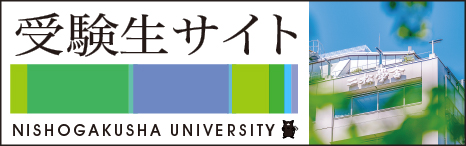著書紹介
江戸時代落語家列伝
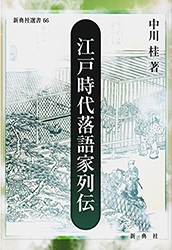
- 著者:中川桂(二松学舎大学文学部)
- 出版社:新典社
- B6版 240頁 1,700円+税
- ISBN:978-4-7879-6816-6
- 発売日:2014年6月11日発行
著書の内容
近世の芸能史を専門分野とする立場から「日本芸能史」などの講義をする機会は以前からありましたが、その中でも教えていてもっとも面白く感じられるのが、自分自身いちばんの趣味である落語の歴史の紹介でした。本学では3年生以上対象の専門科目で、近世落語史に関する資料(史料)を順々に読んでいく講義を行うようになりました。難しくなりすぎないように笑いのある噺本も講義に取り入れ、また「芸人の変遷」という側面からも興味を持ってもらおうと考えました。そんな取り組みがきっかけで、一般書としてこのような本をまとめてみようとの思いに至りました。
現在の落語や落語家についての本はかなり出されているのですが、その中で江戸・東京の落語に比べて上方落語(関西の落語)の扱いは小さいのが現状です。落語の歴史についての本はさらに少なく、とくに近世の上方落語史は寂しい扱われ方をされてきました。本書では江戸・上方を総括して近世の落語の成立と発展をたどっていますが、実は最大のねらいは、両者を取り上げつつ上方落語に正当に分量を割く、という点でした。その結果、江戸より上方の記述量が多くなっていますが、これは近世のある時期までに限れば、落語の歴史を追う上では当然の帰結なのです。
さて、本書では初期の落語の成立から、現在の姿が整うまでを、落語家の活動ぶりを中心としつつ、興行(上演)の様子、ネタの変化といった面も含めて、一般読者向けに紹介しています。座布団に座り、扇子と手拭いを小道具として使用し、室内で演じる…という今のスタイルは、決してはじめから定まってはいなかったことが知られます。では、どのあたりから今の形に変化したのか…。それは、本書をお読みください。そうすると、今もおなじみの「桂」や「林家」といった落語家の亭号と、上演形態との関連も見えてきます。
学生の皆さんへ
本書では落語家個々人を基軸としつつ、落語の歴史をたどっていますが、随所で今も演じられている落語の元ネタとなった小ばなしを紹介し、また、図版も多めに掲載して理解の一助としています。落語をあまり知らなくても、掲載の小ばなしを読んで笑えれば、あなたもじゅうぶん落語を楽しめる資格あり、です。落語を聴いてから本書を読むか、本書に目を通してから落語に触れてみるか…。どちらも大歓迎します。
(文学部国文学科 中川 桂)