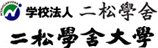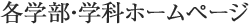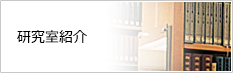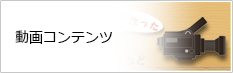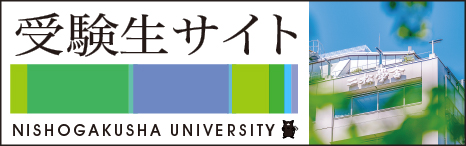著書紹介
東京 文学散歩
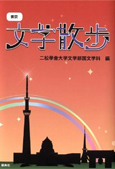
- 編集:二松学舎大学文学部国文学科
- 出版社:新典社
- A5判 144頁 1,200円+税
- ISBN:978-4-7879-7553-9 C0026
- 発売日:2014年2月28日発行
著書の紹介
今回、『東京 文学散歩』を国文学科編として発行しました。2007年に出した『東京〈都市〉文学散歩』(戎光祥出版)と同様、東京を舞台とした文学散歩のコースを紹介した本です。発行元が新典社になってからは、『奈良・京都 文学散歩』(2010年)、『神奈川 文学散歩』(2013年)の2冊を国文学科として出してきました。今回もこれまでのように、国文学科に所属するほぼ全教員が執筆に携わっています。緑が基調の『奈良・京都』と鮮やかな青の『神奈川』の2冊に今回の赤い表紙の『東京』を加えると、本箱が少し華やかになるようです。もちろん担当した者とすれば執筆時の苦労が思い出されたりもするのですが、無粋な研究書に挟まれたカラフルな3冊は、なりは小さくとも目立つ存在となっています。本屋などで見つけた際には、ぜひ手にとってみて下さい。
新しい『東京』で、国文学科が案内するのは全20コース。「23区東部編」「23区西部編」「区内各地・多摩地域編」の大きく3つに分かれて紹介されています。タイトルを見渡すと、「忠臣蔵」『たけくらべ』「漱石」といった誰もが納得する国文学科コース? だけにとどまらず、「ゴジラ」「キツネ」「アニメ」「2次元と3次元」……などのキーワードも並んでいます。もちろんこれらのコース、卒業生をはじめとして、国文学科のスタッフを知る方にはご理解いただけるに違いありません。執筆者の名前を見て、肯いたりニヤリとされたりする方も多いことでしょう。各自が自分の専門をもとにしながら、あるときには趣味に走り、またあるときは専門を大きく逸脱して、自分の紹介したいコースを執筆しました。その意味で東京を含めた3冊は、本屋さんに数多く並んでいる他の文学散歩本とは、一味違うそれぞれの空間案内であると自負しています。
最初の本に学内編集として加わった私にとっては、あれから数年以上を経ながらも、国文学科のスタッフがみな変わらずバイタリティに溢れていることに感銘を受けました。時間経過による若干の顔ぶれの変化があるにせよ、いざというときに、あれだけ専門も個性も異なるスタッフ全員が結集するパワーは、国文学科ならではのもの。そんな国文学科「らしさ」がよくあらわれた一冊といえると思います。
学生の皆さんへ
高校までの「国語」の授業での学びとは、少し違った「文学体験」を味わってほしいと願っています。作家ゆかりの場所や物語の舞台を歩くことで、それまで以上の意味をテクストから読みとるという体験です。とくに今回の東京編は、近代文学の多くが主要な舞台としている場所。二松学舎の全学生が4年間を過ごす東京を、「文学」という点から歩き直してみて下さい。きっといままで気付かなかった東京の一面や、文学の楽しみに触れることができるはず。古典に興味があるなら『奈良・京都』篇もオススメです。また、変化に富むという点では『神奈川』篇も魅力あふれる一冊です。
(五井信)
『東京 文学散歩』・『奈良・京都 文学散歩』・『神奈川 文学散歩』の目次は、下記の通りです。
『東京 文学散歩』目次
- まえがき
- 23区東部編
-
- 番町文人通りを歩く――白樺派の文学者たちを中心に(瀧田浩)
- 皇居から泉岳寺――『忠臣蔵』の世界を訪ねて(原由来恵)
- 作家の家、曲亭馬琴のすみか――元飯田町中坂・神田同朋町・茗荷谷(稲田篤信)
- 舞姫につづく道――森鷗外ゆかりの地を訪ねて(塩田今日子)
- 歴史の息づく道、日本近代化のいぶき――西ヶ原~王子~滝野川(島田泰子)
- キツネゆかりの地・王子(中川桂)
- 『たけくらべ』を歩く(土佐秀里)
- 東京スカイツリーを遠く望んで――向島を歩く(山崎正伸)
- 上野公園――正岡子規「上野紀行」を歩く(渡邊了好)
- ゴジラVS東京(森野崇)
- 23区東部編コラム
-
- 森鷗外――紫の花をもとめた散歩みち(齋藤祐一)
- 蝉丸――「かつら」の考案者(矢澤喜成)
- 綾瀬の天神と稲荷(大山由美子)
- 街を貫く人間の想い――永代橋から銀座ヘ(片山聖英)
- 大学の伝統――文学散歩を伝える(片山聖英)
- 23区西部編
-
- 近代初期の留学生教育事情――清国留学生を中心として(林謙太郎)
- 漱石の東京(増田裕美子)
- 駒場に辿る文学・芸術・歴史――東大から前田尊経閣文庫まで(松浦史子)
- 渋谷から新宿を歩く――100年間の「青春」像を求めて(五井信)
- 池袋のもう一つの顔――先端文化の発信地(山口直孝)
- 23区西部編コラム
-
- 都内一の外国人居住区に息づく明治日本の理解者、小泉八雲(高橋映子)
- 史蹟 関口芭蕉庵(佐藤修)
- 赤坂の歴史(渡辺大雄)
- 区内各地・多摩地域編
-
- 三鷹駅から吉祥寺へ、玉川上水を行く(磯水絵)
- アニメの町・田無を歩く(五月女肇志)
- 2次元と3次元のあいだ――『耳をすませば』の舞台となった街を歩く(松本健太郎)
- 富士塚巡り――下谷坂本富士・駒込富士・品川富士(谷口貢)
- 韓国近代文学先駆者たちの通った学舎(まなびや)――文学の青春期(芹川哲世)
- 東京おまつり歳時記
- 編集後記
既刊
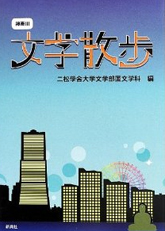
- 『神奈川 文学散歩』
- 編集:二松学舎大学文学部国文学科
- 出版社:新典社
- A5判 142頁 1,200円+税
- ISBN:978-4-7879-7552-2 C0026
- 発売日:2013年3月27日発行
目次
- まえがき
- 鎌倉編
-
- 金沢街道を行く――金沢文庫・金沢八景から鎌倉ヘ(磯水絵)
- 漱石と鎌倉――北鎌倉から小坪ヘ(増田裕美子)
- 鎌倉の禅寺に、道教の神々をみる――伽藍神・十王(松浦史子)
- 耕餘塾と鎌倉アカデミア――理想の学舎をめざして(林謙太郎)
- 鎌倉編コラム
- 鎌倉の守り(井上興正)
- 「金沢八景」管見(松丸由文)
- 鎌倉 多宝谷山妙伝寺(平野光治)
- 江ノ島・湘南編
-
- 由比ヶ浜から歩く浄土への道――鎌倉仏教ゆかりの寺院めぐり(小山聡子)
- ――伝説と恋の道(原由来恵)
- 鵠沼海岸に魅せられた文学者たち――徳冨蘆花から横溝正史まで(山口直孝)
- 湘南海岸文学散歩――藤沢から大磯ヘ(江藤茂博)
- 大磯を歩く――西行から村上春樹まで(山崎正伸)
- 江ノ島・湘南編コラム
- 「えのすい」を満喫する(原由来恵)
- 義経の思いに心を馳せる――満福寺(原由来恵)
- 鱗形(原由来恵)
- 映画で見る80年代若者の湘南(江藤茂博)
- その他エリア編
-
- 元箱根を歩く――箱根神社・芦ノ湖(五月女肇志)
- 連歌師と室町武将の足跡を歩く――箱根湯本と伊勢原(稲田篤信)
- 大山参り――大山阿夫利神社と大山寺(谷口貢)
- 映画と歴史の街を歩く――蒲田から六郷ヘ(五井信)
- 川崎大師を訪ねる――落語の創建説話とは(中川桂)
- その他エリア編コラム
- 禅寺丸柿(小林孝彰)
- 呼ばわり山(天野重男)
- 前田夕暮の世界(小磯純子)
- 箱根にも来たゴジラ(森野崇)
- 横浜・横須賀編
-
- 横浜中華街を歩く――関帝廟に参拝しよう(伊藤晋太郎)
- ――山下公園・港の見える丘公園など(土佐秀里)
- 、横浜襲来――山下公園からみなとみらいヘ(森野崇)
- 横浜の山手を歩く――中島敦の世界を求めて(吉崎一衛)
- 「横浜写真」を歩く――フェリーチェ・ベアトの写真を手がかりに(松本健太郎)
- キリスト教文化の史跡を歩く――横浜指路教会から宗興寺まで(芹川哲世)
- 横須賀を歩く――三笠が守る軍港の町(渡邊了好)
- 横浜・横須賀編コラム
-
- 戸塚――東海道の宿場町(五月女肇志)
- 港町横浜――歴史と異国情緒と北欧料理を味わう(中川俊一郎)
- 海軍の街横須賀(山本静男)
- 新聞発祥の地、横浜(山口直孝)
- 芥川龍之介と横須賀(五井信)
- 神奈川おまつり歳時記
- 編集後記(日本語・中国語・韓国語)
既刊
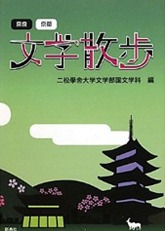
- 『奈良・京都 文学散歩』
- 編集:二松学舎大学文学部国文学科
- 出版社:新典社
- A5判 142頁 1,200円+税
- ISBN:978-4-7879-7551-5 C0026
- 発売日:2010年10月10日発行
目次
- まえがき
- 奈良編
-
- 飛鳥を歩く――古代史の舞台(針原孝之)
- 山の辺の道を歩く――万葉のふるさと(清水道子)
- 今井町の由来とその町並み(末吉榮三)
- 『伊勢物語』と奈良――在原業平ゆかりの寺・不退寺(五月女肇志)
- 説話の舞台を歩く――興福寺・元興寺(磯水絵)
- 平曲・謡曲を歩く――中世芸能の奈良(櫻井利佳)
- 奈良公園を歩く――『万葉集』から『鹿男あをによし』まで(土佐秀里)
- 奈良編コラム
-
- 岡寺の三重塔には和琴が鳴り響く(磯水絵)
- クロコ(煦露粉)珈琲館――大和西大寺駅から平城京址へ行くなら(磯水絵)
- 大仏殿の試みの堂――喜光寺(奈良市菅原町508)(磯水絵)
- 奈良の食べものあれこれ(土佐秀里)
- 志賀直哉旧居(奈良市高畑大道町)のシャワー(磯水絵)
- 奈良の鹿にも歴史あり(土佐秀里)
- 当麻寺の練供養会式(磯水絵)
- 京都編
-
- 嵐山・小倉山を歩く――和歌と物語の舞台(山崎正伸)
- 『源氏物語』宇治十帖を歩く――宇治(竹野静雄)
- 『枕草子』を歩く――賀茂神社・伏見稲荷ほか(原由来恵)
- 和泉式部の姿を求めて――貴船神社・誠心院・東北院(増田裕美子)
- 子育てをする幽霊――六道の辻を歩く(谷口貢)
- 若き西行を動かしたもの――嵐山(五月女肇志)
- 葵祭―― 説話の舞台で(青木信策)
- 松原通りを歩く――『宇治拾遺物語』の世界(磯水絵)
- 『徒然草』を歩く――吉田神社・仁和寺ほか(田中幸江)
- 清水の舞台から――上方落語を歩く(中川桂)
- 映像のなかの京都文化/京都のなかの映像文化(松本健太郎)
- 極私的京都古書店事情(慈幸正法)
- マンガの都・京都(松本健太郎)
- 奈良・京都おまつり歳時記
- 京都編コラム
-
- 京の「通り名の歌」のルーツ『便用謡』(磯水絵)
- 鴨川の恋人たち(土佐秀里)
- 大福光寺本『方丈記』のふるさと(磯水絵)
- 粟餅所「澤屋」(磯水絵)
- 歌舞伎と落語の「はじまり」(中川桂)
- こってり京風味(土佐秀里)
- 食べ歩き(且坐喫茶「七条甘春堂」/虫養い「半兵衛麩」/くづきり「鍵善良房」/
山中貞雄監督も通った山家料理の店「鳴瀬」)(磯水絵) - 『夜は短し歩けよ乙女』と歩く(土佐秀里)
- 奈良・京都おまつり歳時記
- 編集後記