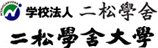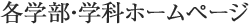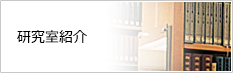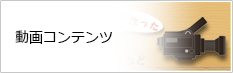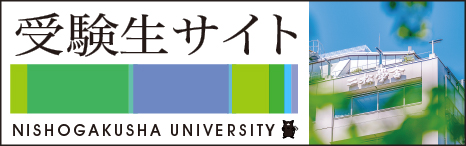著書紹介
『全訳・漢辞海』第三版
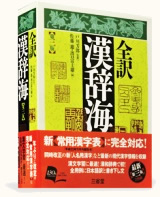
- 監修:戸川芳郎(二松学舎大学名誉教授)
- 編著:佐藤進(二松学舎大学教授)・濱口富士雄(群馬県立女子大学教授)
- 出版社:三省堂、2011年2月25日発行
- B6版 1,936頁 3,045円(税込)
- ISBN 978-4-385-14047-6
『全訳・漢辞海』の特徴
私たちの編集した『全訳・漢辞海』第三版は、従来の漢和辞典にはない以下の特徴をもっています。
- (1)例文にはすべて書き下し文と現代日本語訳がついています(だから全訳)。
- (2)親字の解説はすべてに品詞を記載しました。訓読の際に、中国の品詞が日本で変わることも書いてあります(「乱」は中国では形容詞、日本では動詞「みだる」で読む)。
- (3)日本漢字音は推定でつけるのを退け、徹底して確かな字音資料によっています(本居宣長が棄てた「玄=グヱン」なども採録)。
- (4)中国の「韻」が分かるだけでなく語頭子音も分かるように、中古音の枠組みを声韻調の代表字で記述しました。
- (5)常用字のマークだけでなく、独自に調査した漢文重要漢字約二千五百字にマークをつけました。
- (6)虚字の解説には現代中国における古代漢語研究の成果をできるだけ盛り込みました。
これらは今では他書も採用しているものがありますが、すべて『全訳・漢辞海』が日本で最初の試みとして提供したものです。
編集スタッフ及び命がけの改訂作業
1991年にたまたま本学にもゆかりの戸川芳郎先生から古漢語辞典の編集を手伝ってほしいというお誘いがあり、これまでの不満を解消できるような辞書を作ろうと参画しました。戸川先生と私などは、熟語項目や和訓などのつかない古代漢語の字典を作るつもりでした。しかし、三省堂編集部は商品力を失った『新明解漢和辞典』のかわりになる漢和辞典がほしかったようです。で、いま見るような漢和辞典に変貌したのです。私は中国語として漢文を扱ってきましたが、共編の濱口富士雄先生は筋金入りの訓読名人です。共同作業を実行するには理想的な組み合わせだと思います。
作業を開始してから最初三年間は、編集部のスタッフがいままでの辞典にはなかった上の(1)~(6)について理解できるように、かなりの時間をかけてブレーンストーミングを行ないました。それを含めて八年間で初版が出来ました。幸い、編集部の担当者に英語の得意な途中入社の社員があてられて、漢字を単なる文字として扱うのではなく、文脈の中に存在する「語」として扱うという姿勢を素直に理解していただけました(英語などの外国語辞書なら当たり前の姿勢です)。
八年の作業を経て、初版は2000年に刊行されました。2002年から、初版では親字にエネルギーをそそいだために、若干手薄になった熟語記述の見直しを中心に第二版の作業に入りました(書き下しも第二版からつきました)。翌年、身体からのおかしな下血に悩みましたが、熟語の見直しを完成するまでは病院に行くのを控えました。改訂作業と言っても、すべて原典にさかのぼって語義を検討するのです。ほかの人にまかせるわけにはいきません。この作業中、一度も『大漢和辞典』を引くことはありませんでした。それよりは、その語を含む原典の文章を実際に見て語義を確認したのです(もっとも中国で刊行された≪漢語大詞典≫は頻繁に引いて参照しました)。それが済んだのが2004年の秋でした。それから病院に行くと、あに図らんや直腸癌ということでした。その癌は進行していたので直腸を全摘して人工肛門になりましたが、幸い2006年の年初に第二版を手に取ることができました。たとえではなく、本当に命をかけた改訂だったわけです。
さらに2009年の春から、もう一度やり残した確認作業を加えて2011年の初春に第三版が刊行されたという次第です。その付録に「訓読のための日本語文法」をつけましたが、これまでの辞書のみならず参考書にもなかった解説だと自負しています。これなどは癌と戦いつつ癌を征服したからこそなし得たことで、しみじみ生きていてよかったと思いました。
学生諸君に伝えたいこと
「漢字は一字一字意味をもつ」などという俗説に惑わされると、漢文読解の力はつきません。すべてほかの漢字と組み合わされたときに、はじめてその漢字の意味が立ち現れてくるものなのです。「本」だけだとどの意味か分かりませんが、「根本」だと植物の根の意、「写本」だとbookの意です。どうか『全訳・漢辞海』の例文を十二分に活用して、正確な理解に役立ててください。 (文学部中国文学科 佐藤 進)